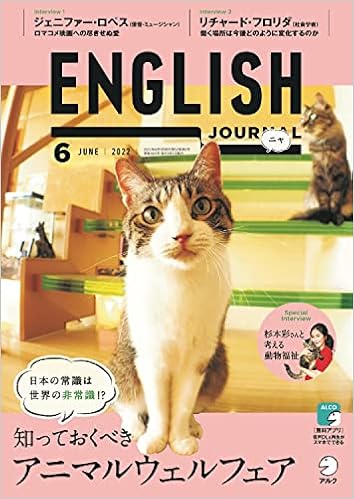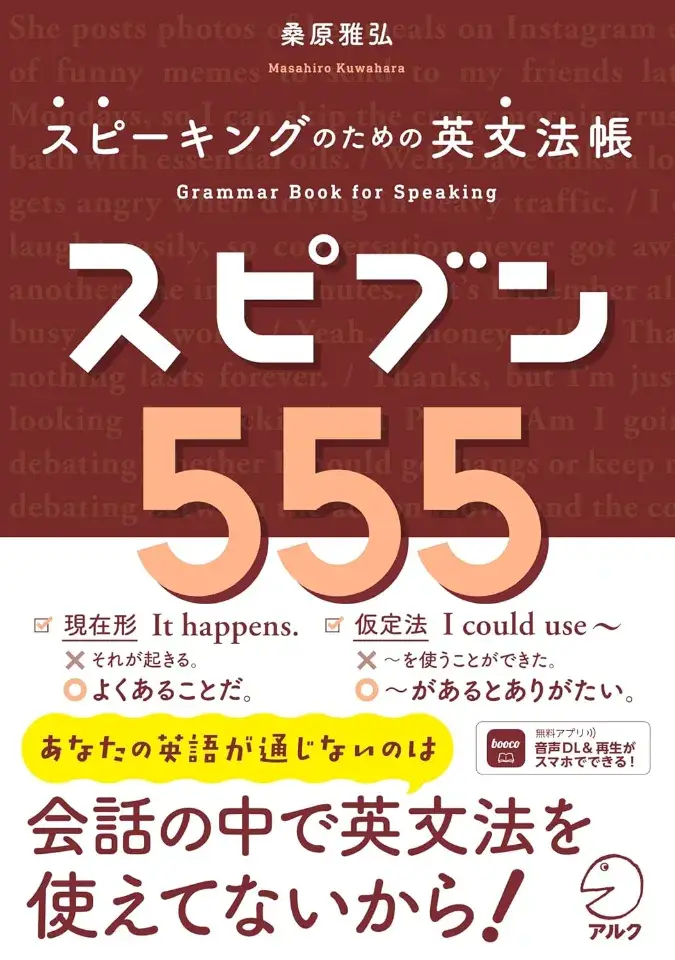食料安全保障、気候変動対策、動物愛護などの観点から注目を浴びる「培養肉」。皆さんはそれが具体的にどんなものか、そして英語でなんと言うのか、ご存じですか?今回は世界中で研究・開発競争が激化している「培養肉」について考えます。
培養肉って英語でなんて言う?
調べてみると「培養肉」の呼び方には、
cultivated meat
lab-grown meat
cell-based meat
clean meat
biomeat
など、さまざまな呼び方があることが分かりました。日本では、培養肉そのものの認知度がそこまで高くありません。これからどのような呼称で日本に広まっていくのか、注目すべきところです。
この記事の中では、簡便に「培養肉」と呼んでいきたいと思います。
培養肉はなぜ注目されてる?
培養肉とは、実際の肉から細胞を取り出し培養して増やしたミンチ肉や、筋肉組織の立体構造を人工的に作ったステーキ肉(これはまだ実現していません)のことです。植物由来の大豆ミート、プラントベースフードとは違い、本物の「肉」を研究室内で培養したり、人工的に作られたりするのが培養肉です。
ではなぜ、培養肉に注目が集まっているのでしょうか。なぜ、人工的に肉を作る技術が開発されなければならないのでしょうか。やがて私たちの日常に培養肉が溶け込む日々がやって来るのでしょうか。食料安全保障、気候変動、動物倫理の観点から説明していきます。
食料安全保障の観点から
農林水産省によると、日本の食料自給率は令和3年度(2021年)の時点でカロリーベースでは38%、生産額ベースでは63%にとどまっています。
「和牛」など、誇れる肉文化を持つ日本ですが、肉の自給率は全体よりも低く、牛肉は9%、豚肉は6%、鶏肉は8%となっています(飼料自給率を反映させた自給率、農水省)。つまり、ほとんどを輸入に頼っているということです。輸入に頼っているということは、もしも輸入先の国で緊急事態が起こったら日本には肉が送られてこない、日本国内で肉不足が起きる、ということです。
実際に、2003年ごろに「牛海綿状脳症(BSE)」が流行した際には、アメリカからの牛肉の輸入が停止し、吉野家から牛丼がなくなる!という緊急事態が発生しました。
そんな現状から脱却するため、日本は令和12年度(2030年)までに、カロリーベース総合食料自給率を45%、生産額ベース総合食料自給率を75%に高める目標を掲げています。特に肉に関して言えば、日本の消費量を補完するだけの家畜を飼育できない上、もし飼育できたとしてもその飼料となる大豆やトウモロコシ、大麦などを栽培する土地が不足します。この点で、日本における培養肉の研究価値は非常に高いのです。
気候変動の観点から
日本の温室効果ガス排出量のうち、農林水産分野は4%を占めており、そのうちの約27%が家畜の消化管内発酵(げっぷ)や排せつ物に由来しています(参照:農林水産省 第2回持続的な畜産生物の在り方検討会)。また、牛1頭の生産には3600万リットルの水が必要であり(参照:環境省 バーチャルウォーターとは)、私たちが入浴する際に浴槽にためる水の量が1回200リットルだとすると、入浴18万回分になります。
このように、家畜の飼育が気候変動に与える影響は、少なからず無視できないと言えます。そのため、研究室の中で培養可能であり、なんの排せつ物も出さない培養肉に注目が集まるのです。
動物倫理の観点から
培養肉は、動物と人間の関係性を研究し、同等の権利の可能性を主張する動物倫理の観点からも注目されています。
全ての肉が培養肉に置き換われば、全く殺生することなく肉を食べることができるのです。動物と人間が共生する社会を実現するためにも、開発研究が進んでいます。
動物倫理、アニマルウェルフェアについては過去のEJの記事で詳しく紹介していますので、ぜひそちらもご覧ください。
今後の動向
日本では、日清食品グループが東京大学と共同して「培養ステーキ肉」の研究を2017年から始めています。もともと再生医療や筋組織の研究が進む日本において、培養肉を作る技術にも長(た)けていると東京大学の竹内昌治教授は言います。
世界では、シンガポールで鶏肉の培養肉の販売認可が2020年に下りています。シンガポールは国としての面積が小さく、現在1割程度しかない食料自給率への危機感を抱えています。食べ物を輸入に依存しないという価値観が世界でも主流になってきているようです。
培養肉を含むフードテック業界の市場規模は2050年までに10倍以上に成長するともいわれており、日本の活躍が期待されています。
日本語ではどう呼んだらいい?
日本国内でこれから培養肉の認知が拡大していくにあたり、この肉をなんと呼ぶのか、どう表記するのか、ちょっとした論争があるようです。
アメリカでは屠殺(とさつ)をしないことから、一時期「clean meat」と呼ばれていましたが、動物の筋肉細胞から培養するという製造方法が正しく伝わらないことから、「cell-based meat」という呼び方に移行しているようです。
英語での呼び方をそれぞれ日本語に直訳すると、下のようになります。
cultivated meat 培養肉
lab-grown meat 研究室育ちの肉
cell-based meat 細胞由来の肉
clean meat 潔白な肉
biomeat 生物工学肉
培養肉を社会に浸透させるためには、どう呼称するのかが良いか思案所です。生産者が「人工的」「倫理観」「生産方法」のどこに焦点を当てるのかで、呼び方は変わってきそうです。
培養肉の業界はこれから注目すべき世界です。興味があれば、関連する本もぜひ読んでみてください。
boocoで読める!アルクの新刊、続々登場
語学アプリ「booco」なら、アルクのベストセラー書籍200タイトル以上が、学習し放題!
「キクタン」などアルクの人気書籍800冊以上が音声対応。「読む」に対応した書籍では、本文と音声をスマホで手軽に利用できるほか、一部の書籍では、学習定着をサポートするクイズ機能で日々の復習や力試しも可能です。さらに、Plusプランに加入すれば200冊以上の書籍が学習し放題に!
boocoの「読む」機能では、次のような使い方ができます。
① 学習したいページを見ながら音声を再生できる
② 文字サイズや画面の明るさを調整できる
③ 書籍内検索ができる
※ これらの機能には一部の書籍が対応しています。

▼「booco」の無料ダウンロードはこちらから