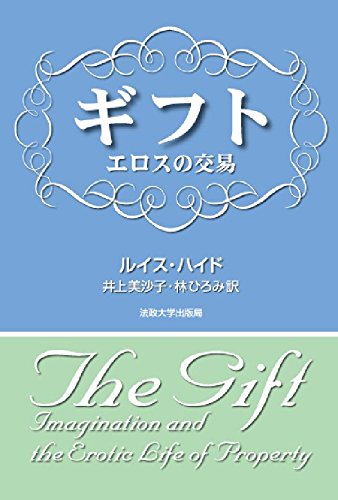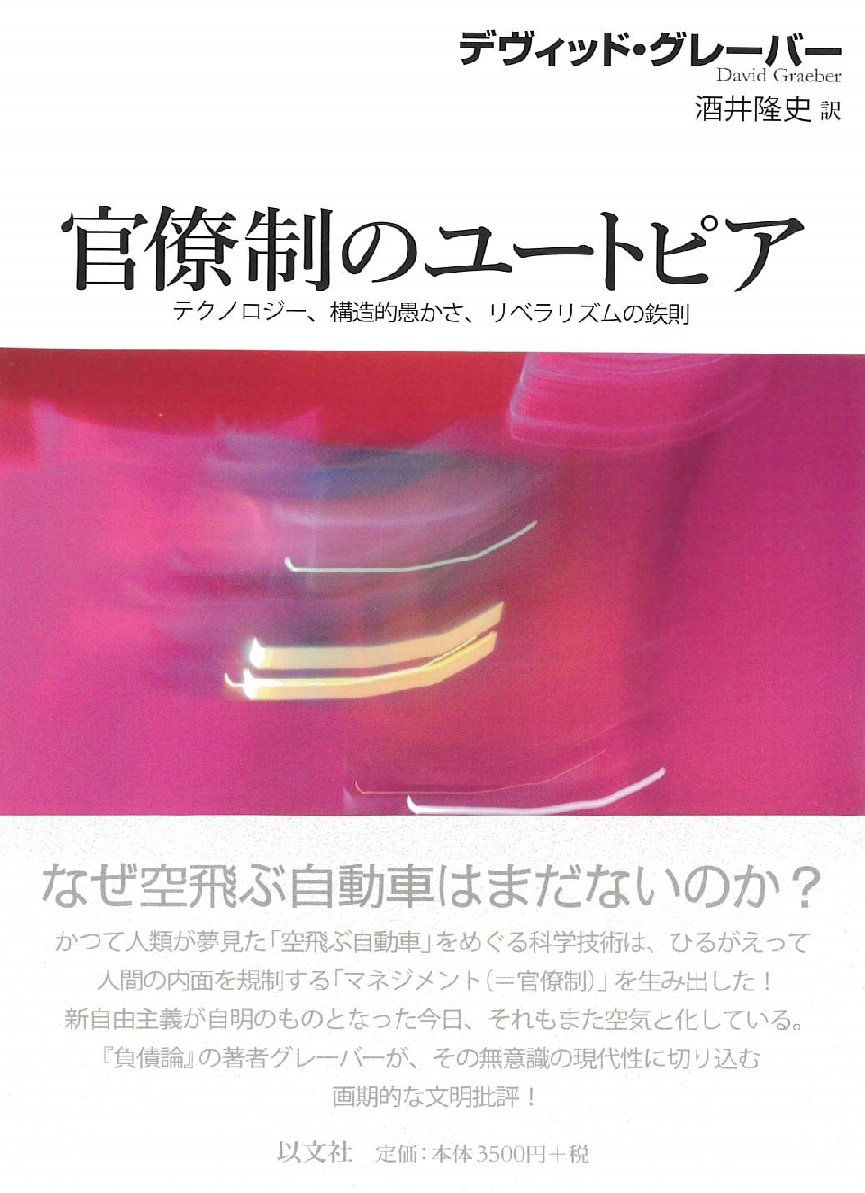多くの方の調べものに役立っているオンラインの大事典「ウィキペディア」。どうせ使うなら、その本当の姿をよく理解して使いたい――。ウィキペディアの執筆者・編集者のお一人である北村紗衣さんに、今回は、設立以来の理念を堅持しつつ知識の民主化を目指すウィキペディアの姿について、詳しくお話しいただきます。
編集合戦の背後にあるコミュニティの理想
ここまでこの連載を読んでくださった方はなんとなくお分かりでしょうが、ウィキペディアは実にひどい所です。荒らしが横行し、誤情報や低品質記事があふれ、悪質なプロパガンダの現場にもなります。編集合戦が始まると、ノートで悪夢のような議論に時間が費やされます。まったく最低の場所です。
一方で、ウィキペディアは恐らくインターネット上の著名な大規模プロジェクトとしては唯一、ボランティアによる運営で20年以上もまともに続き、設立当初の理念を守って人々に知識を提供し続けている場でもあります。
長くウィキペディアに住んでいるウィキペディアンたちは、欠点は十分認識しつつ、昔ながらの理想を失っていないところがあります。ウィキペディアは「信頼されるフリーなオンライン百科事典、それも質・量共に史上最大の百科事典を、共同作業で創り上げることを目的とするプロジェクト」です。始まったのは2001年ですが、この頃はまだインターネットが世の中を良くしてくれるはずだというユートピア的な理想が存在した時代でした。
少なくとも私は、ウィキペディアのようなプロジェクトには大きな意味があると考えています。そこで今回は、私が考えるウィキペディアの姿とその文化的背景を説明します。
無料でプレゼントを交換しまくろう
ウィキペディアの根底にある理想は、知識は自由で無料でみんなに開かれているものでなければいけないという考え方です。お金がある人にだけ知識が提供される社会は民主的ではありません。知識は慈雨のようにあまねく広く降り注いで、地面を潤すものでなければならないのです(たまにとんでもないニセ知識が台風のように荒れ狂うこともありますが)。
ウィキペディアは贈与経済で動いています。無償どころか時間と体力とお金(資料代など)を持ち出して活動するウィキペディアンは、気前よく知識というプレゼントを無料で大盤振る舞いしている贈り手です。
ウィキペディアを読む人はそのもらい手です。もらい手が贈り手になっていつか社会に返してくれるかもしれませんが、その確証はありません。ウィキペディアコミュニティ内で褒めてもらえればうれしいですが、ほとんどのプレゼントはだいたいお返しが戻ってきません。それでもウィキペディアンは大盤振る舞いし続けます。
しかしながら、ウィキペディアンは元々はプレゼントのもらい手でした。ほとんどのウィキペディアンは、ウィキペディアの記事を読む受け手を経て書き手になります。書く方になる前に知識をもらって恩恵を受けていますし、自分が書いたのではない良い記事に巡り合えたときの楽しさもよく理解しています。そういうプレゼント交換の場所に参加するのがウィキペディアンになるということです。
市場主義に抵抗するウィキペディア

こうした贈与経済は、芸術や学問の世界では昔からあるものでした(このあたりは研究者のルイス・ハイドが『ギフト――エロスの交易』という本で詳しく論じているので、興味のある方はぜひ読んでみてください)。
私が住む学術研究の世界では、伝統的にかなりの量の知識が無料で贈られます。「書きかけの論文を見てくれないか」とか「このアイデアにコメントが欲しい」みたいな知識のやりとりが日常的にお金が発生しない形で行われます。最近はそうしたものも労働としてお金を払うという考え方が浸透していますが、これは諸刃の剣です。知識に値段がつきまとうようになり、生産過程でかかったお金を払わないと知識にアクセスできなくなる可能性があります。
ウィキペディアは市場経済以前の贈与で成り立つ世界観によって立つプロジェクトです。このため、ウィキペディアは現在のインターネットを支配している、市場中心主義的で何でもお金に換えようとする考え方とは真っ向から対立しています。無料ばらまきこそウィキペディアの神髄なのです。
贈り物を持ってこないヤツは帰れ
ウィキペディアは誰でも参加して記事を編集できるプロジェクトですが、一方で貢献をしないと思われる者に対しては厳しい所です。記事を書くだけではなく、技術的な問題を解決するとか、著作権関係のアドバイスを行うとか、何でもいいのですが、とにかく何かしなければなりません。困ったことがあれば自分で調べてどうにかするか、しかるべき人に聞いて解決する必要があります。記事に文句だけ言って自分で編集しない人はものすごく嫌われ、ウィキペディアは誰でも編集できるんだから自分でやれ、と言われます。ハッカー文化ではDIY的発想が尊ばれますが、ウィキペディアもそういう所です。
ウィキペディアの素晴らしさの理由の一つである贈与経済的な発想は、参加のハードルを高くしているところがあります。基本的にウィキペディアはちゃんとした贈り物を持ってこないヤツは帰れ、という発想で運営されています。
プレゼントをするときにはTPOに沿ってやり方を変えたり、適切な包装をしたりする必要がありますが、ウィキペディアが複雑なルールでかんじがらめの官僚的なシステムを取っているのは、言ってみれば爆発物とかゴミみたいなとんでもないものを贈ろうとする人を排除するためでもあります。荒らしや誤情報への警戒が高まるほど、こうした贈り物のルールは厳しくなります。
共同創設者ジミー・ウェールズの影響力
拝金主義的な現代のインターネットの世界では、マネタイズできないのに価値あることを成し遂げており、かつ20年以上ちゃんと続いているウィキペディアはある意味で脅威です。
お金で何でも買えると思われている世の中なのに、ウィキペディアも、私たちウィキペディアンも、お金で買うことができないからです。金もうけに汲々とするITビジネス業界の中で、ウィキペディアでは毎日変人どもがプレゼントの無料大盤振る舞いを楽しく続け、さらに世界中がそこから知識という利益を得ているのです。
Twitterを買収したイーロン・マスクは以前からウィキペディアに敵対的でしつこく攻撃しています。
Have you ever wondered why the Wikimedia Foundation wants so much money?
— Elon Musk (@elonmusk) October 22, 2023
It certainly isn’t needed to operate Wikipedia. You can literally fit a copy of the entire text on your phone!
So, what’s the money for? Inquiring minds want to know …
英語圏のメディアでは、非営利で民主的に良いものを提供し続けているウィキペディアをマスクが嫌うのは当たり前だと指摘されています。マスクを批判する記事でウィキペディアが「人類の最も素晴らしい成果のひとつ」とか言われると、毎日ろくでもない記事を見つけているウィキペディアンとしては冗談でしょ・・・などと思いますが、一方で私は、心の底ではウィキペディアは最高のプロジェクトだと思っていますし、そこに参加できてうれしいと思っています。インターネット上にこんな昔のユートピア的理想を残したまま生き続けている場所は、もうあまり存在しません。
ウィキペディアの共同創設者の一人であるジミー・ウェールズは以前からイーロン・マスクに対して「ウィキペディアは売り物じゃない」と反論しています。
Not for sale. https://t.co/8by52xEgg4
— Jimmy Wales (@jimmy_wales) December 7, 2022
オープンソース系プロジェクトなどでは、コミュニティ全体に影響力を持つ開発者を「慈悲深き終身独裁官」(Benevolent Dictator For Life)などと呼ぶ習慣があるのですが、ウェールズはウィキペディアにおける慈悲深き終身独裁官と見なされています(ウェールズ本人はこの呼び方を嫌がって「立憲君主」という呼び方を好んでいるようですが)。
別にウェールズがウィキペディアにおいてシステム上絶大な権力を持っているわけではないのですが、どのコミュニティでも一目置かれており、発言は重視されます。東日本大震災が発生したときには、編集の過熱ぶりに「東北地方太平洋沖地震」の記事がほぼ何もない状態で保護されてしまいましたが、ノートでウェールズが情報提供は必要なので半保護でいいのではないかとコメントしたところ、雰囲気が一気に変わって半保護になったということがありました。
集合知で運用される民主的空間のはずのウィキペディアに独裁官がいるとは一体・・・と思うかもしれませんが、これまでこの連載を読んできてくださった方にとっては、能力がある者が評価される文化が強いのでまあ理解できることかなと思います。ウェールズは批判もある人物ですが、これまで言論の自由と知識への無料アクセスのために努力してきました。ウィキペディアンとしては、うちの独裁者がまともで良かった・・・と思うばかりです。
次回は私が執筆者に名を連ねる記事としてはこの連載の最終回になります。特別ゲストをお呼びして行う対談記事になり、そのゲストに連載を引き継ぐ予定です。ウィキペディアについていろいろな話題を扱う対談になる予定です。
参考文献
本文画像:Linus / Adobe Stock
北村紗衣さんの新刊
注目のシェイクスピア研究者、北村紗衣さんが、海外文学や洋画、洋楽を、路地裏を散歩するように気軽に読み解きながら、楽しくてちょっと役立つ英語の世界へとご案内。英語圏の奥深いカルチャーに触れながら、高い英語運用能力を得る上で重要な文化的背景を探求します。“路地裏”を抜けた後は、“広場”にて著者自身が作問し解説する「大学入試英語長文問題」も堪能できる、ユニークな英語カルチャーエッセイ。
北村紗衣さんのその他の記事
boocoで読める!アルクの新刊、続々登場
語学アプリ「booco」なら、アルクのベストセラー書籍200タイトル以上が、学習し放題!
「キクタン」などアルクの人気書籍800冊以上が音声対応。「読む」に対応した書籍では、本文と音声をスマホで手軽に利用できるほか、一部の書籍では、学習定着をサポートするクイズ機能で日々の復習や力試しも可能です。さらに、Plusプランに加入すれば200冊以上の書籍が学習し放題に!
boocoの「読む」機能では、次のような使い方ができます。
① 学習したいページを見ながら音声を再生できる
② 文字サイズや画面の明るさを調整できる
③ 書籍内検索ができる
※ これらの機能には一部の書籍が対応しています。

▼「booco」の無料ダウンロードはこちらから