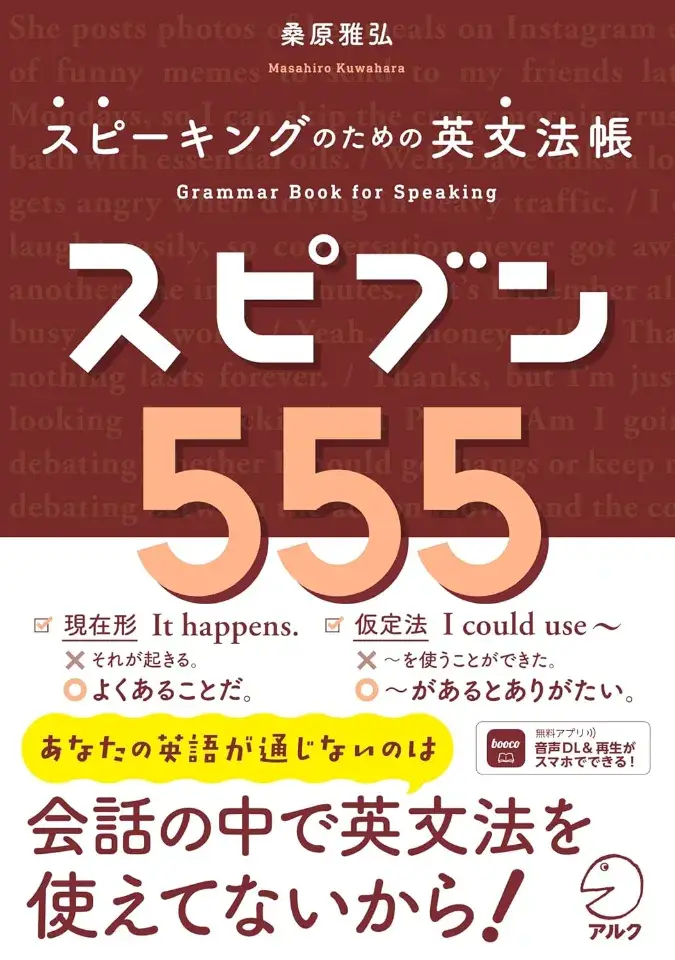多種多様な映像作品の日本語字幕版や吹き替え版を作るために不可欠な「映像翻訳者」。この連載では、映像翻訳者として活躍する3名にインタビューをし、それぞれのキャリア形成や働き方、そして映像翻訳に必要な経験やスキルついて深掘りしていきます。映像翻訳者はどんなバックグラウンドを持ち、そしてどんな働き方をしているのでしょうか?
目次
第4回:南部恭子さん(仕事編)
第4回となるこの記事では、前回に引き続き、日本映像翻訳アカデミー(JVTA)とアルクが共同運営する「映像翻訳Web講座」を受講して映像翻訳者になった、南部恭子(なんぶきょうこ)さんのインタビューをご紹介。映像翻訳者としてのデビュー、実際の仕事について伺います。
▶ 前回の記事:南部さんインタビュー前編【学習編】は こちら 。
課題は常に「実際の仕事」として取り組む
映像翻訳Web講座ではプロフェッショナルコースを修了すると、日本映像翻訳アカデミー(JVTA)が開催するトライアル(プロ化試験)を受験できるようになります。そしてトライアルに合格すると、JVTAのディレクターの指導のもとで実践的なトレーニングであるOJT(実務体験訓練)を受けてプロの映像翻訳者としてデビューとなり、JVTAの翻訳受発注部門から仕事が発注されるようになります。
JVTAのトライアルは2カ月に一度開催。南部さんは11回目に合格しました。多くの人が「合格までの期間が一番苦しかった」と言いますが、南部さんは2年間、トライアル受験にも楽しみながら取り組んでいたといいます。
「トライアルで使われる映像素材は毎回バラエティーに富んでおり、常に登場人物と同じ体験をしている気持ちで字幕を作っていました(もちろん、今もですが)。当時仕事にしていた実務翻訳に比べると映像翻訳は格段に面白かったので、受験中もまったく苦になりませんでした」
トライアルでは合格者に加え、一定の点数を獲得した「次点」も発表されます。この次点に入ると、プロの映像翻訳ディレクターから直接フィードバックを受けることができます。南部さんは、次点に入った時の課題作品やフィードバックの様子をよく覚えており、具体的に褒めてもらえたことでモチベーションが上がったと話します。
「トライアルは試験ですが、常に実際の仕事をイメージして作業し、『この字幕は公共の場に出る』という気持ちで毎回提出していました。受験後は訳例を何度も見て、改善すべきポイントを自分に叩き込んでいきました。それはプロになった今も同じで、チェック担当者や翻訳ディレクター、制作会社からのフィードバックを見て再考し、最終稿に仕上げています」
作業時間を意識してきたことが実務に役立つ
映像翻訳Web講座を修了後、2年間挑み続けたトライアルに合格。英語講師と兼業しながら映像翻訳者としてデビュー後、1年ほどでフリーランスになり、現在はリアリティ番組やドラマ、映画祭上映作品などの字幕を手掛けています。
南部さんは、トライアル受験の頃から翻訳作業にかかる時間を意識してきました。プロとして働くには翻訳作業のスピードが大切だと思ったからです。仕事の依頼を受ける際は、映像の長さ(尺)や内容と自分の作業スピードを考慮して、納期に対応できるかを見定めます。また新人時代は分野を問わず、さまざまな案件に挑戦してスキルアップを重ねました。
「時には、やや厳しいと思うスケジュールに自分を追い込むことでスピードアップしてきたように思います。もちろん質を落とさないことが条件で、『質とスピード』を上げていけば次の仕事につながると信じてきました」
ドラマや映画を観る「工夫」が未来につながった
元々、好きな映画やドラマを字幕なしでそのまま理解したいと思っていた南部さんは、字幕の世界に入る前、同じ映像を異なる視聴方法でくり返し観ていたそう。「結果的にそれが、現在の字幕づくりにも役立っているかもしれない」といいます。
「海外ドラマの同じエピソードを4回くらい観ていました。1回目は英語音声のみ、2回目は字幕あり(または吹き替え)、3回目は英語音声のみ、4回目は字幕ありと、日本語と英語を交互に観て対比させていました。英語を理解しようとする中で自然と日本語字幕にも多く触れていたことになりますね」

進化し続けるAIを「疑ってみる」理由
字幕翻訳の経験を重ねた南部さんは、最近は翻訳者が作った翻訳原稿の内容をチェックするチェッカーの仕事も引き受けています。
また映像翻訳業界では近年、機械翻訳による訳文を翻訳者がチェックし、誤訳の修正から表記の統一、内容のブラッシュアップまでを図る「ポストエディット」という仕事も増えています。そのような仕事をする際は、チェッカーの目線がより必要だと南部さんはいいます。
「機械翻訳や生成AIは確かに便利ですが、全面的に信頼せずに疑うことも忘れないようにしなければと思います。実際に、AI翻訳ツールによる訳文を支給されて歌詞対訳に取り組む案件があったのですが、『lie』という動詞の訳に関してAIが『嘘をつく』と『横たわる』の意味を取り違えていました。作業段階でそれに気づけず、チェックで直してもらったことがあります。事前に訳文が入っていると惑わされてしまうこともあるのだと実感し、注意が必要だと感じました」
AIは日々急速に進化しています。ですが、微妙なニュアンスを捉えて翻訳で表現するには、やはり人間によるチェックが必要だと南部さんは考えています。
「“好き”を仕事に」それが映像翻訳者の醍醐味
学生時代から語学の学習を続け、映像翻訳Web講座の受講をきっかけに「好きなことを仕事にする」という夢を叶えた南部さん。何よりも「楽しさ」がこの仕事の醍醐味といいます。
フリーランスとして仕事をする中で、納期によっては1日に10時間以上の作業になることも。それでも苦には感じないという南部さん。「視聴者にとって良い字幕とは何か」を追求し、仕事と向き合います。
「基本的に、視聴者は字幕を一度しか観ません。そのため分かりやすく、『文字を追っている』と感じさせず、スムーズに進み、でも見終わった後に大事なことが伝わっているような字幕を目指しています」
話数の多いドラマシリーズや映画祭上映作品では、短い納期に対応するために複数の翻訳者でチームを組んで翻訳することがあります。一つの作品を1人で任されるようになるには「質とスピード」で信頼を得ることが必要です。トライアル受験時から質とスピードにこだわってきた南部さんだからこそ、現在は1人で任される作品が増えています。
「『ドラマの1エピソードを1人で翻訳する』『ドラマシリーズを1人で翻訳する』『映画全編を1人で翻訳する』『劇場公開映画を1人で翻訳する』『翻訳仲間ができる』など、たくさんの夢が一つずつ叶っていきました」
担当作品を映画館で観ていて笑いが起こることに新鮮な驚きがあったという南部さん。東京の劇場には足を運べなかったそうですが、2024年のフィンランド映画祭で上映されたミカ・カウリスマキ監督の『頑固じいさんと愛の物語』は特にお気に入りだそうです。

(参照元:下記記事)
【参考記事】
【フィンランド映画祭に字幕で協力】ミカ・カウリスマキの人気シリーズ、メタルコメディ映画の続編など旬の話題作が一挙上映
はじめは軽い気持ちで始めた映像翻訳Web講座でしたが、最終的にこれまで学び続けた語学を活かしたフリーランスへの道に繋がりました。南部さんのように語学や映像作品が好きという方は、プロの映像翻訳者は狭き門と諦めず、一歩踏み出してみてはいかがでしょうか?
▶ 南部さんの原点や学習の工夫を振り返る前回の記事【学習編】はこちら 。
〔連載・「映像翻訳者インタビュー」〕前回までの記事
この連載では、同じく「映像翻訳Web講座」を受講して映像翻訳者になった2名へのインタビューを公開中です。ぜひこちらも併せてご覧ください。
【西飯 仁徳(にしい ひとのり)さん】
・ 〔学習編〕ホテル勤務 → 映像翻訳の道へ TOEIC300点台から始まった学習記録・キャリアチェンジ体験記
・ 〔仕事編〕プロ映像翻訳者×学び場の運営 2足のわらじを両立させる働き方の姿勢とスケジュール管理
【牧田彩野(まきたあやの)さん】
・ 〔学習編〕コロナ禍の転機と真っ赤な添削 奥深い映像翻訳の世界で弱点と向き合い、表現力を磨く
・ 〔仕事編〕:根底にある語学への「絶対あきらめない」気合い|初仕事の“半泣き経験”を越え、映画丸々一本を任された日
「映像翻訳者」への第一歩を踏み出す
映像翻訳Web講座(ベーシックコース)
◆ 英語と映像が好きなら、 プロになるチャンス!
映像翻訳Web講座は、「1000時間ヒアリングマラソン」など英語教育で実績のあるアルクと日本映像翻訳アカデミー®が共同運営するプロの英日映像翻訳者を養成するeラーニングの通信講座です。パソコンがあれば、どこにいても受講できます。最短22カ月間で、プロの映像翻訳者に。ベーシックコース(3カ月)からスタート。プラクティス(6カ月)、アドバンス(7カ月)、プロフェッショナル(6カ月)の順で修了し、トライアル(プロ登録者選抜テスト)を受験。合格すれば、JVTAの受発注部門から仕事が発注されます。
◆ 時間や場所にとらわれずに仕事ができる!
映像翻訳の仕事の魅力は、パソコンとインターネットがつながる環境があれば、時間や場所にとらわれず仕事ができることです。「子育てをしながら手の空いた時間に翻訳をする」「海外で生活しながら翻訳をする」。そんなライフスタイルも実現できます。長く活躍できることも大きな魅力。翻訳にはさまざまな人生経験を生かせることから、「年齢を重ねた方に仕事がない」ということもなく、いくつになっても能力が発揮できます。また、英日映像翻訳者の絶対数は不足しているため、活躍の場は広がり続けています。
映像翻訳Web講座のより詳しい情報やお申込み方法については、上記バナー画像もしくは コチラ をクリックしてご確認ください!