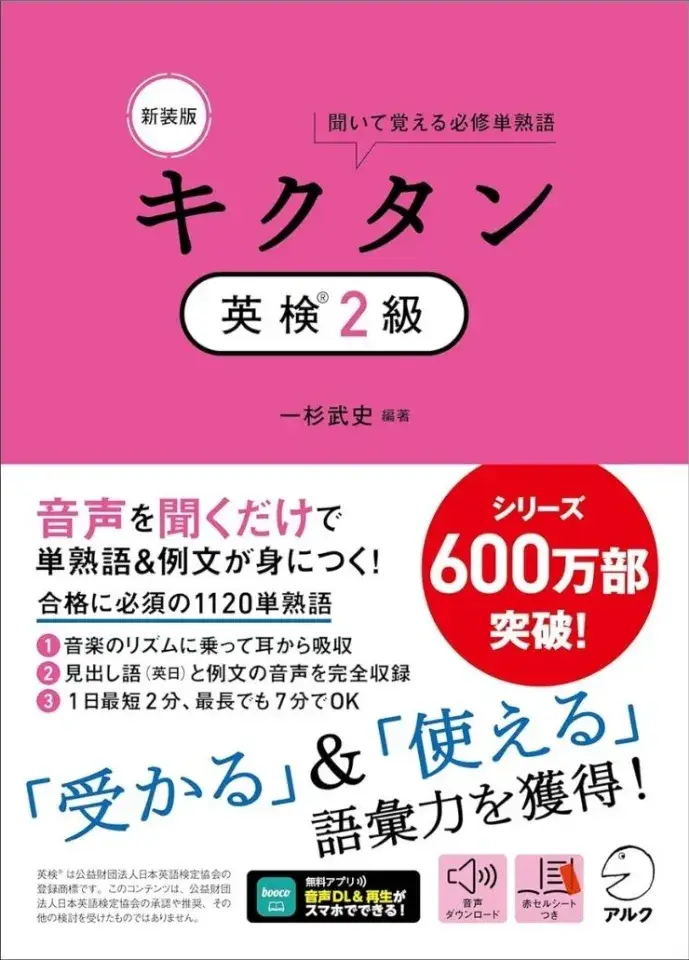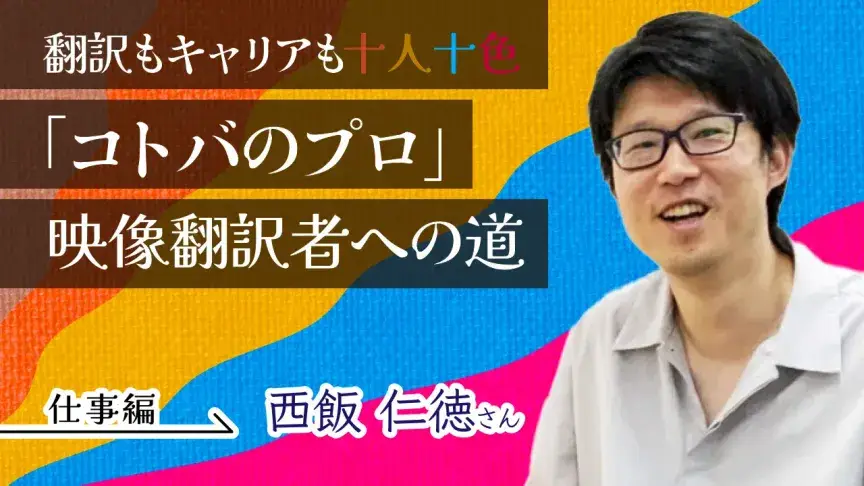
多種多様な映像作品の日本語字幕版や吹き替え版を作るために不可欠な「映像翻訳者」。この連載では、映像翻訳者として活躍する3名にインタビューをし、それぞれのキャリア形成や働き方、そして映像翻訳に必要な経験やスキルついて深掘りしていきます。映像翻訳者はどんなバックグラウンドを持ち、そしてどんな働き方をしているのでしょうか?
目次
第2回:西飯仁徳さん(仕事編)
第2回となるこの記事では、前回に引き続き、日本映像翻訳アカデミー(JVTA)とアルクが共同運営する「映像翻訳Web講座」を受講して映像翻訳者になった西飯仁徳(にしい ひとのり)さんのインタビューをご紹介。映像翻訳者としてのデビューから実際の仕事についてまでを伺います。
▶ 前回の記事:西飯さんインタビュー前編【学習編】は こちら 。
「他の人より時間がかかった」プロデビューまでの日々
映像翻訳Web講座ではプロフェッショナルコースを修了すると、日本映像翻訳アカデミー(JVTA)が開催するトライアル(プロ化試験)を受験できるようになります。そしてトライアルに合格すると、JVTAのディレクターの指導のもとで実践的なトレーニングOJT(On-the-Job Training)を受けてプロの映像翻訳者としてデビューとなり、JVTAの翻訳受発注部門から仕事が発注されるようになります。
「何回くらいで合格できますか?」という質問は多いのですが、合格のタイミングは人それぞれ。1回で合格する人もいれば、回数を重ねて合格にたどり着く人もいます。西飯さんの場合は、合格まで3年以上を要したそうです。
「具体的な受験回数は覚えていないのですが、合格するまで3年以上はかかったはずです。きっと他の人より長く時間がかかったと思います。この期間が一番つらかったです」
果敢にトライアルに挑戦するも、なかなか合格にたどり着かない日々。しかし西飯さんはめげることなく、挑戦し続けます。トライアル合格を目指して、映像翻訳の経験を少しでも多く積める機会を探しました。
「この期間、JVTAが長年字幕翻訳でサポートしている難民映画祭〔*1〕や大阪アジアン映画祭〔*2〕で字幕翻訳チームに参加し、翻訳の機会を持つようにしました。少しでも字幕に触れられる環境に自分を置くことで、なんとかくじけずに続けられたと思います」
JVTAで開催されている「ロジカルリーディング力強化コース」も受講し、翻訳に必要な英文解釈力も強化。こちらは映像翻訳Web講座と異なり、リモートでライブ配信の授業に参加する形式です。他の参加者の翻訳原稿を見ることもでき、一人で進めていたWeb講座とはまた違う学びを得ることができたと言います。
コース受講修了後も様々な方法でスキルを磨き続けた西飯さん。とうとうトライアル合格を果たし、プロの映像翻訳者としてのデビューに至ります。
〔編集部注:*1、2〕
・「 難民映画祭」
X:@unhcrrff
WEBサイト:https://www.japanforunhcr.org/how-to-help/rff
・「大阪アジアン映画祭」
X:@oaffpress
WEBサイト:https://oaff.jp/oaff2025expo/
現在は2足のわらじで活躍中。大切なのは「時間を決めること」
現在の西飯さんは、三重県で中高生向けの勉強スペースの運営と映像翻訳の仕事を並行しています。西飯さん曰く、地方は都会に比べて中高生が勉強できるカフェや図書館が少ないそう。そこで中高生が勉強の場として使えるスペースを与える事業を立ち上げ、映像翻訳者と2足のわらじで仕事をするようになりました。
「映像翻訳の仕事は、45分の映像作品を週に1~2本手掛けるようなペースで行っています。エンタメ作品だけでなく、ドキュメンタリー作品や企業動画の案件などもありますね。勉強スペース運営との両立は簡単ではありませんが、なんとかやっています」

勉強スペースの運営と翻訳を両立するため「作業時間を決める」ことを心がけていると西飯さんは言います。フリーランスは決まった就業時間がないため、時間的に自由であるものの、際限なく仕事ができてしまうという側面もあるからです。
「自分の場合は、『翻訳作業は何時に始めて何時に終える』というスケジュールを決めています。映像翻訳は納得のいく翻訳になるまでどこまでもこだわりたくなるのですが、そうなると永遠に終わらないので・・・。どこかで切り上げることも必要だと思っています」
西飯さんの日々の仕事の割合は、翻訳が8割、勉強スペース運営に関する仕事が2割とのこと。勉強スペースで中高生から質問や相談があればそちらに時間を割き、翻訳の納期が近づけば翻訳作業にかける時間が増えることもあります。バランスをとるのが難しいときもありますが、時間をしっかり管理し、どちらも手を抜くことなく取り組んでいます。
映像翻訳者になって分かった、英語力以外に必要なスキル
翻訳者 = 英語力が最重要、というイメージを持つ人は多いと思います。もちろん、英語力が高いに越したことはありません。しかし、「英語ができれば映像翻訳者として活躍できる」とは限りません。西飯さんは英語力以外で映像翻訳者に必要なスキルとして、「情報収集力」を挙げます。
映像作品は常に時代の影響を受けています。最新のドラマであれば今はやりの言葉が出てきたり、50年前に活躍したアーティストのドキュメンタリー映像であれば当時の情勢を反映した発言があったりします。映像の内容に関する「背景知識」がないと、英語力がどれだけあっても翻訳には不十分だということです。
「特に、ドキュメンタリー作品は作品の題材について深く調べることが必要です。また企業の動画を手掛けることも多いのですが、翻訳に入る前にその企業に対する予備知識を持っておくことも重要ですね。映像翻訳者は常に周りにアンテナを張り、情報を積極的に取りに行くことが大切だと思います」
情報収集については、西飯さんは周囲の人に助けてもらうこともあるそう。経営者の友人、車好きの友人、MR(Medical Representative/医薬情報担当者)の友人など幅広い人脈を生かし、翻訳に役立つ知識を得ていると言います。
字幕だけでなく吹き替えも。広がる活躍の場
「元々英語が得意で、語学力を生かした仕事を目指していた」というわけではないものの、今では映像翻訳者として様々な仕事を手掛けている西飯さん。最近では字幕翻訳だけでなく、吹き替え翻訳に携わることも増えました。吹き替え翻訳には、字幕翻訳とはまた異なるやりがいがあります。
「吹き替え作品では、翻訳された台本を基に声優さんが演技をします。アニメーションで人気の声優さんが参加されることもあり、自分の翻訳した吹き替え台本が読まれると思うと感激しますね。地方在住のため東京での吹き替え収録に立ち会うのは難しいのですが、一度オンラインで参加させていただく機会がありました。作品の一役を担っている気持ちになり、うれしかったです」

西飯さんが映像翻訳者を目指し始めた際に設定したゴールは、「映画のエンドロールの最後に名前が出る」ということ。劇場作品の字幕を手掛けるという目標にはまだたどりついていませんが、ストリーミング配信や映画祭上映の映像作品では翻訳者として名前が出ることがあります。そんな時、「夢がかなってきている」と感じると言います。
最後に、西飯さんが考える映像翻訳の面白さを聞きました。
「映像翻訳には本当に様々なジャンルの仕事があって、翻訳しながら知見を広げることができます。作品を通して新しい知識を得たり、元々知っていたものに関しても新たな視点を得たり。そういったところが面白いですね」
TOEIC300点台の大学生時代からプロの映像翻訳者になるまで。精神的につらい時期に、自分を奮い立たせるために想像していた「映像翻訳者として成功した姿」は、今の西飯さんと重なっていることでしょう。西飯さんの更なる活躍が楽しみです。
▶ 西飯さんへのインタビュー前編【学習編】はこちら から。
連載「映像翻訳者インタビュー」 | これまでの記事
この連載では、同じく「映像翻訳Web講座」を受講して映像翻訳者になった2名へのインタビューを公開中です。ぜひ併せてご覧ください。
【南部恭子(なんぶきょうこ)さん】
・ 〔学習編〕英語学習の原点はNHKのラジオ講座 とにかく翻訳が好きというモチベーションでプロデビューへ
・ 〔仕事編〕好きなことを仕事にする夢を実現 翻訳する過程もすべて楽しめるのがこの仕事の醍醐味
【牧田彩野(まきたあやの)さん】
・ 〔学習編〕コロナ禍の転機と真っ赤な添削 奥深い映像翻訳の世界で弱点と向き合い、表現力を磨く
・ 〔仕事編〕:根底にある語学への「絶対あきらめない」気合い|初仕事の“半泣き経験”を越え、映画丸々一本を任された日
「映像翻訳者」への第一歩を踏み出す
映像翻訳Web講座(ベーシックコース)
◆ 英語と映像が好きなら、 プロになるチャンス!
映像翻訳Web講座は、「1000時間ヒアリングマラソン」など英語教育で実績のあるアルクと日本映像翻訳アカデミー®が共同運営するプロの英日映像翻訳者を養成するeラーニングの通信講座です。パソコンがあれば、どこにいても受講できます。最短22カ月間で、プロの映像翻訳者に。ベーシックコース(3カ月)からスタート。プラクティス(6カ月)、アドバンス(7カ月)、プロフェッショナル(6カ月)の順で修了し、トライアル(プロ登録者選抜テスト)を受験。合格すれば、JVTAの受発注部門から仕事が発注されます。
◆ 時間や場所にとらわれずに仕事ができる!
映像翻訳の仕事の魅力は、パソコンとインターネットがつながる環境があれば、時間や場所にとらわれず仕事ができることです。「子育てをしながら手の空いた時間に翻訳をする」「海外で生活しながら翻訳をする」。そんなライフスタイルも実現できます。長く活躍できることも大きな魅力。翻訳にはさまざまな人生経験を生かせることから、「年齢を重ねた方に仕事がない」ということもなく、いくつになっても能力が発揮できます。また、英日映像翻訳者の絶対数は不足しているため、活躍の場は広がり続けています。
映像翻訳Web講座のより詳しい情報やお申込み方法については、上記バナー画像もしくは コチラ をクリックしてご確認ください!