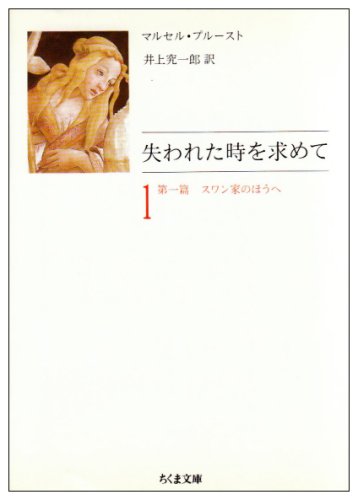連載「世界が見える 翻訳の不思議」第10回。翻訳家有好宏文さんは、最近刊行された『ポータブル・フォークナー』の新訳で、セミコロンを表す妙な空白を見つけました。それをきっかけに、日本語翻訳におけるセミコロンの表現の難しさと翻訳の奥深さについて探ります。
フォークナーの新訳に現れた妙な空白
最近、翻訳が刊行された『ポータブル・フォークナー』(河出書房)に入っている「熊」(柴田元幸訳)を読んでいたら、文章の途中に妙な空白があるのに気が付いた。
歪(いびつ)な足跡が残された、斧も入っていない森を見る前から彼の夢の中で巨体はそびえ立っていたのであり、夢の中でそれは毛むくじゃらで強大で赤い目で、悪意なくただ大きく、吠えて追いつめようとする犬たちにとってあまりに大きく、速足で追いつこうとする馬たちにとっても、男たちと男たちがそれに向けて撃ち込む銃弾にとってもあまりに大きく その活動を限定している地域そのものにとってもやはりあまりに大きかった。
最後のほうの「大きく」の後の空白である。見た瞬間にピンときた。いつも悩んでいるアレを訳したものに違いない。本棚から原著を引っ張り出してみると、空白の箇所には、やっぱりあった、あった。セミコロンである。
It loomed and towered in his dreams before he even saw the unaxed woods where it left its crooked print, shaggy, tremendous, red-eyed, not malevolent but just big, too big for the dogs which tried to bay it, for the horses which tried to ride it down, for the men and the bullets they fired into it; too big for the very country which was its constricting scope.
プルースト『失われた時を求めて』のセミコロン

セミコロンは翻訳者を悩ませる。ピリオドやコンマなら、日本語の句点(マル)や読点(テン)と似ているので、あまり困らない。ダッシュもダッシュのままでいい。引用符はかぎかっこにすれば大丈夫だ。でも、セミコロンに当たる、マルとテンの中間のような記号は、日本語にはない。
セミコロンは、文を軽く区切りたいけれど、かといって完全には切ってしまいたくないという微妙な気分のときに、ピリオドとカンマの中間のような記号としてよく使われる。でも、その微妙な気分を翻訳で再現したいと思っても、日本語にはセミコロンみたいな記号はないので、テンにすべきか、マルにすべきか、迷う。
セミコロン(正確にはフランス語のポワンヴィルギュル)をテンで訳して美しい散文を生み出したのは井上究一郎だ。プルースト『失われた時を求めて』(ちくま文庫)の冒頭近くから引用する。
それでも、三十分ほどすると、もう眠らなくてはならない時間だという考に目がさめるのであった、私はまだ手に持ったつもりでいる本を置こうとし、あかりを吹きけそうとした、ちらと眠ったあいだも、さっき読んだことが頭のなかをめぐりつづけていた、
「目がさめるのであった」「あかりを吹きけそうとした」のあとのテンはもともとセミコロン(ポワンヴィルギュル)だ。文が完全には切れずに、テンで緩やかにつながって続いていく。この文体が、まどろみの中で意識がだらだらと流れていく感じを伝えている。美しい文章だと思う。
明治時代に作られたテンとマルの中間のシロテン
冒頭に引用した、セミコロンに空白を当てるという手法は初めて見た。これがはやったら、50年後くらいに日本語句読法の一つとして文法書や教科書に載るのかな。もしかして僕たちは、日本語の歴史が変わる瞬間に立ち会っているのだろうか。
実は、セミコロンに当たる句読記号が提案されるのは今回が初めてではない。明治時代に日本語の句読記号が整理され始めた頃、テンとマルの中間の記号があったそうだ。テンの真ん中がマルのように白抜きになった記号で、シロテンとか、白ゴマ点とか、ゴマ白点とか、かわいい名前で呼ばれていた。

このシロテンは、欧文のセミコロンに当たるものが日本語にも必要だと考えた、小説家の山田美妙が提案したと言われている。山田の『武蔵野』や二葉亭四迷の『浮雲』などに使われているが、当時の印刷技術では潰れてしまうことも多く、その後定着せずにだんだん廃れていった。
このシロテンを使った翻訳は『ナボコフの文学講義』(野島秀勝訳、河出文庫)で見かけた。フロベールの『ボヴァリー夫人』を論じた章で、ナボコフがフロベールのセミコロン(ポワンヴィルギュル)の使い方を分析しているのを訳す際に、訳者は「シロテンは原文のセミコロンを表す」という但し書きをして、このシロテンを使った。セミコロンそのものが話題になっているので、こうした翻訳を選んだのだろう。
とはいっても、現代ではあまり馴染みのない記号なので、よほどの理由がないかぎり、このシロテンを使って訳すのは勇気がいる。読者のほとんどは見たことがないだろうから、普通の翻訳小説の中でシロテンが使われていたって、何かの間違いだと思われるのが関の山だろう。あるいは、まったく気付かれないかもしれない。だから、翻訳者は相変わらずセミコロンに困っている。
セミコロンがテーマの超ニッチ本

セミコロンのことをつらつら考えていたところに、『セミコロン かくも控えめであまりにもやっかいな句読点』(セシリア・ワトソン著、萩澤大輝/倉橋秀男訳、左右社)という本が最近出版された。セミコロンだけでまるまる一冊書き切った超ニッチな本だ。さすがにセミコロンだけの一冊なんて地味すぎないかと心配になったが、杞憂(きゆう)だった。セミコロンの解釈一つで、ボストンで酒が売れなくなったり、被告が死刑になったりと、こんなに痛快な歴史があったとは。細かい話ってどうしてこうもユーモラスになるんでしょうね。
著者のワトソンは、文章規則集『シカゴ・マニュアル』を幼少期から暗唱していたほどの筋金入りの規則大好き人間だったが、大学生に作文を教える教師になって壁にぶち当たったそうだ。いわく、規則をいくら説明しても、学生たちがインパクトのある言葉を使ったり、愛をかき立てるメールを書いたり、笑いを取れるツイートをする助けにはならない。それで、規則の暗唱から、個性ある文章をたくさん読んで解明する方向にシフトしていった。
作家たちの個性的なセミコロンづかいを解説した「セミコロンの達人たち」の章が勉強になる。マーク・トウェイン、ハーマン・メルヴィル、ヘンリー・ジェイムズ、レイモンド・チャンドラー、レベッカ・ソルニット、アーヴィン・ウェルシュ、そしてキング牧師といった「達人」たちの用例を、著者ワトソンに導かれてたどるうちに、文法書の規則だけでは説明し切れないセミコロンの姿が浮かび上がってくる。彼らは、規則の枠を広げる、規則なんて知らないよとうそぶく、あるいは規則を逆手に取る。そこにあるのは作家の声だ。
「ピリオドでも良かったのに、どうしてここでセミコロンを使ったんだろう」ある時は、文を段落の、段落を章の、章を本全体の一部として位置づけて観察し、こう考える。この文は周りとどう関わり合っているのだろう。(フィクションであれば)人物像をどう作り上げているだろうか。(ノンフィクションなら)考えや感情をどう提示しているだろうか。またある時は、書き手の全体的な文体や声やテーマについて「このセミコロンはどう貢献しているんだろう」のように考える。本書には文脈から切り離されて宙に浮いた例文は出てこない。
もっとも、この『セミコロン』を読んだからといって、翻訳者の悩みがたちどころに解消するわけではない。これからも、このやっかいな記号に出会うたびに悩むだろう。でも、セミコロンで本を一冊書いてしまうようなスゴイ人だって、いちいち考えているのだ。そう思うと、安心して悩むことができる。セミコロンは作家の声に耳を澄ませるチャンスだ。
文学カテゴリー記事一覧
boocoで読める!アルクの新刊、続々登場
語学アプリ「booco」なら、アルクのベストセラー書籍200タイトル以上が、学習し放題!
「キクタン」などアルクの人気書籍800冊以上が音声対応。「読む」に対応した書籍では、本文と音声をスマホで手軽に利用できるほか、一部の書籍では、学習定着をサポートするクイズ機能で日々の復習や力試しも可能です。さらに、Plusプランに加入すれば200冊以上の書籍が学習し放題に!
boocoの「読む」機能では、次のような使い方ができます。
① 学習したいページを見ながら音声を再生できる
② 文字サイズや画面の明るさを調整できる
③ 書籍内検索ができる
※ これらの機能には一部の書籍が対応しています。

▼「booco」の無料ダウンロードはこちらから