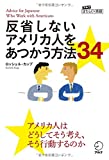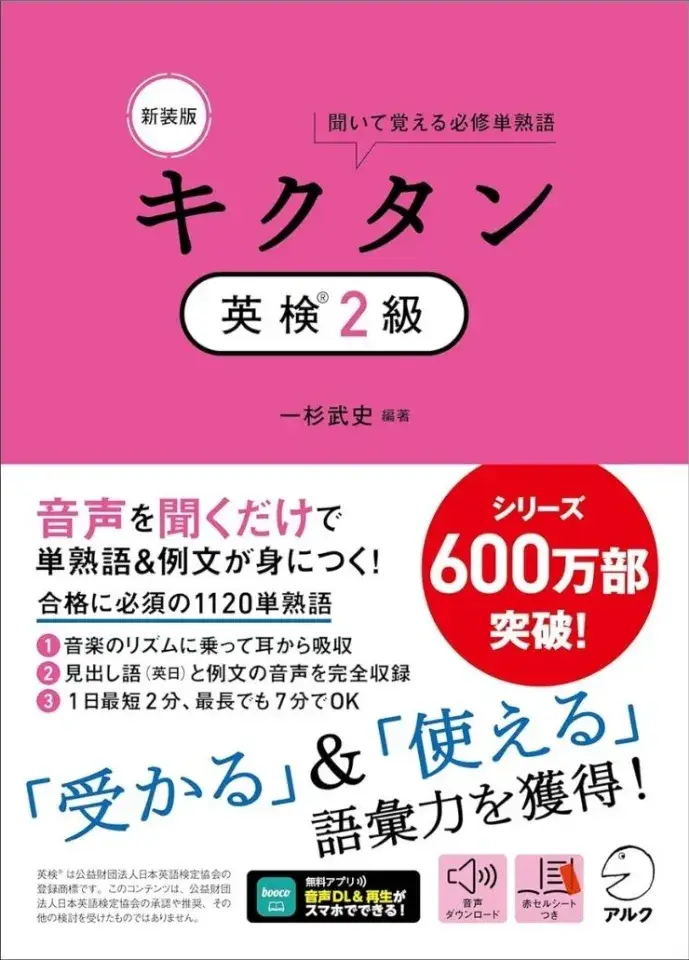世界を相手にビジネスを行うためには、英語力だけでなく、多様な文化を受け入れるためのグローバルマインドセット、つまり視野の広いもののとらえ方が必要となります。本コラムでは、経営コンサルタントのロッシェル・カップさんにグローバルマインドセット獲得のヒントを教えていただきます。
会議中に鉛筆をボキッ!何があった?

日本の広告会社の東京本社で、あるスペイン人従業員が働いていました。
普段は穏やかな性格の人で、日本人の 同僚 の皆とも仲良くやっていたのですが、ある日、会議の場で突然、鉛筆を折ったのです。声を上げもしなかったし、興奮したり感情を爆発させたりすることもありませんでした。しかし、鉛筆を折るという行動は、日本人の目から見るとあまりにも激しい振る舞いなので、その会議に参加していた日本人の多くは不快感を覚えてしまいました。
もしこのようなことがあなたの職場で起きたとすれば、どのように対応をすればよいでしょうか。
「豊かな感情表現」をよしとする文化もある
日本では、会社など公の場にいる場合には自分の感情を抑え、周りの人と摩擦が起きないように自分の言動を控え目にする文化があります。そのため、多くの日本人は上記の選択肢の中で【a】を選びます。しかし、相手が外国人である場合、同じ尺度で測ることは間違いかもしれません。
実は、在日外国人からよく聞く苦情に「突然、職場の日本人が自分と話さなくなった。 原因 がいったい何なのか、まったく見当がつきません」ということがあります。
文化によって、自分の感情をどのように言動で表わすかについては大きな違いがあります。 下記のチャートの左側に位置するほど、声の調子、顔の表情、体の動き、言葉数で、自分の感情を他人に伝えようとする 傾向 があります 。その人の様子を見ると、どんな感情を抱いているかは明らかです。
一方、 この比較チャートで右側の方に位置するほど、自分の感情を他の人に見せない 傾向 があります 。そういう文化に属する人々は、自分の感情を自制することが良いと思っていますから、言動は控え目にします。

これらの異なった 傾向 を持っているタイプの人々同士が交流すると、誤解が起こりやすくなります。感情を表に出す人から見れば、そうしない人たちは冷たく思えるし、何を考えているか分からないので近づきにくいと感じます。一方、感情を控え目にする人たちにとっては、感情表現が豊かな人は、彼らの持つ雰囲気が激しくて圧倒されるように感じるので、一緒にいると居心地が悪く思えるのです。
このような違いが、上に挙げた会議での 事例 の背景にあったのではないかと考えられます。表で見られるように、スペインは典型的な感情表現の豊かな国です。会議中に鉛筆を折るという行動は、感情をあまり表に出さない日本にとってはとても目立つ奇妙な振る舞いに思われるかもしれませんが、実はそのスペイン人にとっては、そんなに大した意味がなかったのかもしれません。この場合は【c】に当たります。
そうであるとはいえ、鉛筆を折るという行動に至ったのは何かのストレスが 原因 かもしれない ので、私が選びたいのは【b】です。その人と話を交わすと、何か大切な発見があるかもしれません。
しかし、そのような対話の機会を設けるときには、鉛筆の事件にこだわり過ぎないで、一般的に、 その従業員は今の仕事に満足しているのか、何かのストレスを抱いていないかなどについて、幅広い会話をすればよい と思います。実は日本の職場では、上司は部下に対してそのような会話を十分に行わない 傾向 がありますから、 心配 を招くような行動がなくても、定期的にそのような会話をする方が望ましいでしょう。
固定観念を捨て、もっと笑顔で接しよう!

一般的に感情を表に出すのにあまり慣れていない日本人に推薦したいことは、感情を大げさなかたちで表現する人と接触するときには、 相手の感情表現にあまり大げさな反応を示さないで、相手の文化を考えながら前後の文脈の中で捉えるように努力した方がよい ということです。自分の感情を表に出すことに慣れていなくても、相手にとってはそれが普通の行動であることを理解する必要があります。なお、 「感情を表に出すのは良くない」とか「感情をそのまま示すのは子どもだけ」などのような固定観念を 捨てる ことも望ましいと思います。
なお、相手が自分より感情表現豊かな文化圏の人であれば、少しでも自分の感情を素直に表現して見せることができれば、心を通じ合う橋渡しとして役立ちます。特に多くの他の文化と比べた場合、日本人はあまり笑顔で人と接することをしないので、感情表現を大切にする文化の人から見れば、自分に親しみを感じてくれていないように映ります。
簡単なことですが、笑顔をもっと頻繁に見せて接することは、円滑な人間関係を築く上でとても効果的な方法です。
こちらもおすすめ!
gotcha.alc.co.jpロッシェル・カップさんの本

- 作者: ロッシェルカップ,大野和基
- 出版社/メーカー: 集英社インターナショナル
- 発売日: 2017/08/07
- メディア: 新書
![]() 反省しないアメリカ人をあつかう方法34 (アルク はたらく×英語シリーズ)
反省しないアメリカ人をあつかう方法34 (アルク はたらく×英語シリーズ)- 作者: ロッシェル・カップ
- 出版社/メーカー: アルク
- 発売日: 2015/12/24
- メディア: 単行本
![]() 日本企業がシリコンバレーのスピードを身につける方法
日本企業がシリコンバレーのスピードを身につける方法- 作者: ロッシェル・カップ,到津守男,スティーブ・マギー
- 出版社/メーカー: クロスメディア・パブリッシング(インプレス)
- 発売日: 2017/07/18
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
![]() 日本企業の社員は、なぜこんなにもモチベーションが低いのか?
日本企業の社員は、なぜこんなにもモチベーションが低いのか?- 作者: ロッシェル・カップ
- 出版社/メーカー: クロスメディア・パブリッシング(インプレス)
- 発売日: 2015/01/30
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (2件) を見る
編集:GOTCHA!編集部![]()
執筆:ロッシェル・カップ
ジャパン・インターカルチュラル・コンサルティング社 社長。
異文化コミュニケーションと人事管理を専門とする経営コンサルタントとして、日本の多国籍企業の海外進出とグローバル人材育成を支援している。イェール大学歴史学部卒業、シガゴ大学経営学院卒業。日本語が堪能で、『 反省しないアメリカ人をあつかう方法34 』(アルク)、 『英語の品格』 (集英社) をはじめ、著書は多数。朝日新聞等にコラムも連載している。【1000時間ヒアリングマラソン】 ネイティブの生英語を聞き取る実践トレーニング!
![]()
大人気通信講座が、アプリで復活!
1982年に通信講座が開講されて以来、約120万人が利用した「ヒアリングマラソン」。
「外国人と自由に話せるようになりたい」「仕事で困ることなく英語を使いたい」「資格を取って留学したい」など、これまで受講生のさまざまな夢を支えてきました。アプリ版「1000時間ヒアリングマラソン」は、日常、ビジネス、フリートーク、時事英語、物語などの多彩なジャンルのコンテンツを収録し、さらに豊富なアウトプット練習や学習時間の計測などの機能を盛り込み、よりパワーアップして復活しました。
「本物の英語力」を目指す人に贈る、最強のリスニング練習
学校では習わない生きた英語
実際にネイティブスピーカーと話すときや海外映画を見るとき、教科書の英語と「生の英語」のギャップに驚いた経験はありませんか? 「1000時間ヒアリングマラソン」には、オリジナルドラマやラジオ番組、各国の英語話者のリアルな会話など、学校では触れる機会の少ない本場の英語を届けるコーナーが多数用意されています。
こだわりの学習トレーニング
音声を聞いてすぐにスクリプトを確認する、一般的なリスニング教材とは異なり、英文や日本語訳をあえて後半で確認する構成にすることで、英語を文字ではなく音から理解できるようにしています。英文の書き取りやシャドーイングなど、各トレーニングを一つずつこなすことで、最初は聞き取りが難しかった英文も深く理解できるようになります。
あらゆる角度から耳を鍛える豊富なコンテンツ
なぜ英語が聞き取れないのか? には理由があります。全15種類のシリーズは、文法や音の規則、ニュース英語など、それぞれ異なるテーマでリスニング力強化にアプローチしており、自分の弱点を知るきっかけになります。月に一度、TOEIC 形式のリスニング問題を解いたり、書き取りのコンテストに参加したりすることもできるため、成長を定期的に確認することも可能です。
「1000時間ヒアリングマラソン」は、現在7日間の無料トライアルを実施中です。さあ、あなたも一緒にランナーになりませんか?