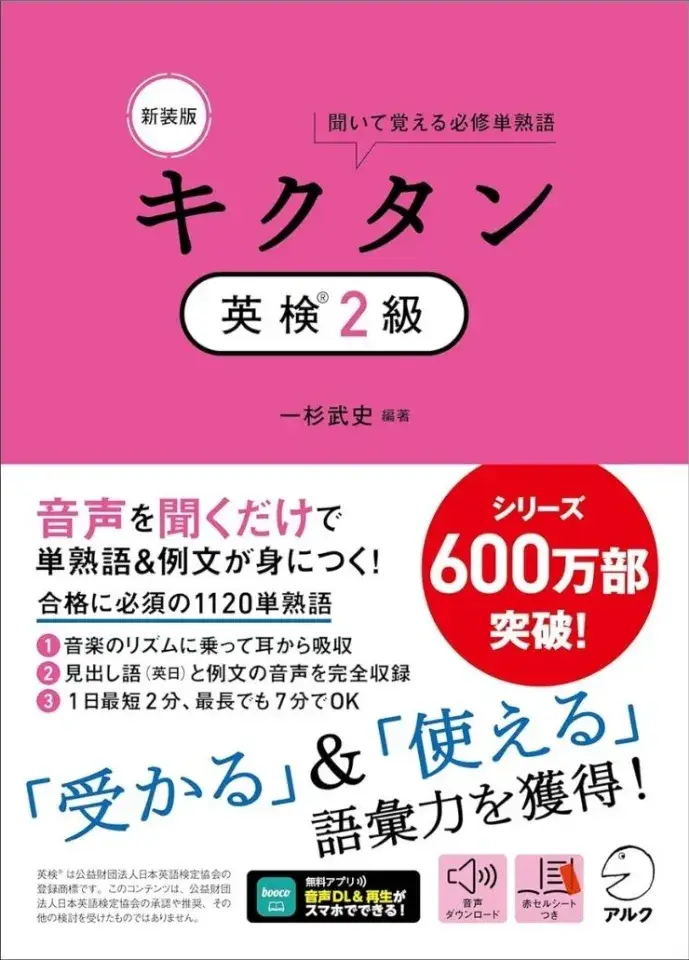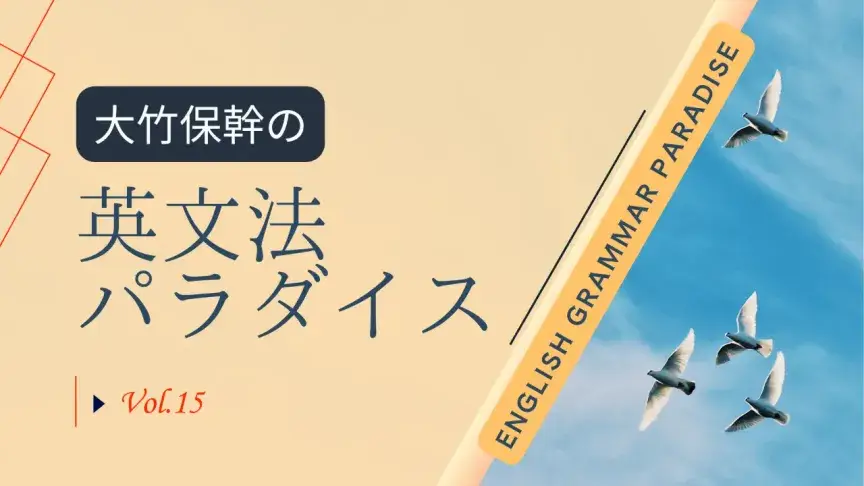
現役高校英語教師・大竹保幹さんの連載はいよいよ最終回。英文法の「苦手」「分からない」を解消し、英語のいろいろな面を楽しめる「英語愛好家」を目指して、今日もクイズに挑戦しましょう!
パラダイス行き切符を手に入れる問題
英文法パラダイスを目指してから1年以上が経ちました。皆さんとは、動詞中心の時制に始まり実にたくさんの文法を巡って来たわけですが、英文法とは仲良くなれましたか?
さて、今回でこの連載「英文法パラダイス」は最終回を迎えます。最後に扱う文法は一体何でしょうか。問題を解きながら「これは何の知識を問われているのだろう」と、よく考えてみてください。
難しさを感じずに自然と解けたなら、あなたは英語上級者・・・というより立派な英語愛好家です。英語愛を問う間違い探しに挑戦してみましょう。
問題
次の (1) ~ (5) の英文について、正しいかどうかを判断してください。
・正しい:〇
・間違っている:×
・ちょっと怪しい:△
(1)
My family are all coming for dinner this weekend.
(2)
I realised I had to be careful as I walked across this colorful floor. The sign says, 'Caution: Wet Floor'.
(3)
You should throw the rubbish into that trash can.
(4)
The weather’s awful but she don’t care. She’s out there dancing in the rain.
(5)
A photo surfaced of the missing hiker.
今回のテーマは「いろいろな英語」です。これはいろいろな文法項目という意味ではなく、各地域で使われていたり、学校ではあまり習わなかったりする英語ということです。意外でしたか?
「そんなことよりも『正しい』英語を!」と思った方は要注意です。というのも、今や英語は世界中に広がり、その姿を少しずつ変えて来てきていますし、そのどれもがそれを使う人々にとっての「正しい」英語だからです。
少なくとも、代表的なものとして挙げられる「アメリカ英語」と「イギリス英語」には語彙だけでなく文法の違いなどもありますし、そのアメリカ英語、イギリス英語の中にだって地域ごとに方言があります。一概に「これが正しい」と言うのは思っている以上に難しいのです。
もちろん、英語学習者の私たちは教科書的な正解を求めそれを手本とするべきですが、そうでない形の英語があって、それを使っている世界があることも知らなくてはいけません。むしろ、知っているからこそ楽しめる世界があると言ってもいいでしょう。
最終回らしい、マニアックな英文法の世界を覗いてみましょう!
解答と解説

(1)
【答え:〇】
My family are all coming for dinner this weekend.
うちの家族は今週末の夕食会に来ますよ。
さすがに今の時代、This is a pen.(これはペンです。)から英語学習が始まるなんてことはありませんが、それでもbe動詞の使い分けは多くの学習者にとっては最初に習う文法です。
主語が一つのものを表す単数なのか、それとも二つ以上を表す複数なのかによって、対応するbe動詞の形はisやareに変化します。ある名詞が複数なのかどうかは、基本的には名詞の語尾に-sがあるかどうかで判断できますから、使い分け自体はそこまで難しくはありません。
もちろん、they(彼ら、彼女ら)やpeople(人々)のように、単語の見た目ではなく意味そのものが複数を表すこともあるので注意が必要ですが、それでもbe動詞の使い分けで悩む学習者はそこまでいませんよね。
しかし、今回の英文ではどうでしょうか?
❖ アメリカ英語とイギリス英語の違い
皆さんは (1) の文を見たとき、すぐに正誤の判断ができましたか?もし自信を持って「○」と答えられたなら、英語のバリエーションの一つである「地域方言」にも目が向いている証拠です。
細かく分類するとキリがありませんが、英語には大きく分けて「アメリカ英語」と「イギリス英語」の2種類があります。学校で習う英語は基本的にはアメリカ英語ですので、イギリスの人が話す英語を聞くと「少し発音が違うな」と思うはずです。
でも違うのは発音だけではありません。文法だって少し違うのです。
The government was planning to raise the consumption tax.
政府は消費税を引き上げる計画をしていた。
The government were planning to raise the consumption tax.
政府は消費税を引き上げる計画をしていた。
二つの例文はどちらも同じことを言っていますが、be動詞の形が異なります。私たちにとって馴染みのあるのは上の方で、be動詞が主語であるthe government(政府)に合わせて単数形であるwasになっています。これはアメリカ英語では当然の形です。
一方で下の方は動詞がwereなのでthe governmentを複数として扱っていることがわかります。実はイギリス英語ではgovernment、team(チーム)、family(家族)などには「個々のメンバーが集まってできている」というイメージがあり、複数扱いをするのです。people(人々)も見た目では-sがありませんが、人が何人も集まっているという意味から複数扱いをしますから、これと同じ理屈だと考えると分かりやすいですね。
少しトリビア的な話になりますが、国名であるthe United States(アメリカ合衆国)ははるか昔はThe United States are... と複数扱いをされていたそうです。それが南北戦争をきっかけにしてThe United States is... と単数で扱われるようになったとか。一つの国として結束されたぞという意識が語法を変えている面白い例です。
(2)
【答え:△】
I realised I had to be careful as I walked across this colorful floor. The sign says, ‘Caution: Wet Floor’.
このカラフルな床を通るときには気を付けないといけないことがわかった。張り紙に「注意:床が濡れています」と書かれていたからだ。
この英文に「○」と言えない理由、それはつづりの統一感のなさです。ご存じの方も多いように、アメリカ英語とイギリス英語ではつづりが異なる語があり、どちらを使っても正解ではあるのですが、やはりどちらかに統一した方が英語としてはきれいだからです。
少し極端な例えかもしれませんが、日本語を書いていて一部の漢字が旧字体になっていたり、「パソコン」のようにカタカナで書くべき語を「ぱそこん」と書かれていたらちょっと違和感がありますよね。
❖ もう一つの違い、分かった?
では、今回はどこをどのように直せば良いのでしょう。ひとまず教科書的にアメリカ英語にすることにしましょう。
I realized I had to be careful as I walked across this colorful floor. The sign said, "Caution: Wet Floor."
realisedをrealizeに直すということについては多くの人が気づくのかもしれませんが、意外な盲点として引用符の違いやピリオドの位置が挙げられます。アメリカ英語ではセリフなどの引用には「"(ダブルクオーテーションマーク)」を使うのが一般的ですし、ピリオドは基本的にはいつもその引用符の内側に入れます。
言われてみると当たり前のことなのですが、指摘できるかというと結構難しいポイントですね。では、今度はイギリス英語に統一することにします。
I realised I had to be careful as I walked across this colourful floor. The sign said, 'Caution: Wet Floor'.
realisedというつづりを活かしてイギリス風にするならばcolorfulはcolourfulと書くことになります。しかし、やはりここでも注目してほしいのは引用符の使い方です。絶対ではありませんが、イギリス英語では引用には「 '(シングルクオーテーションマーク)」を使うのが基本です。また、張り紙自体に「Caution: Wet Floor」のようにピリオドが使用されていないのであれば、文末のピリオドは引用符の外側に出すことになります。
引用符の使い方の違い、知っていましたか?
❖ クイズに挑戦!
最後にちょっとだけ、英米つづりクイズです。次の単語を全てイギリス風の綴りに直してみましょう。
[1] favorite(お気に入りの)
[2] program(番組)
[3] jail(刑務所、拘置所)
↓
↓
↓
正解は、[1] favourite、[2] programme、[3] gaol でした。全部当てられましたか?
(3) に関してはイギリスでも公文書以外ではjailを使うことが多いようですが、gaolなんてあまりにも不思議な見た目で面白いのでぜひとも覚えておきたいつづりです。
そう、綴りの違いは面白いのです。めんどくさいではなく、面白い。こういう気持ちが大切です。
(3)
【答え:△】
You should throw the rubbish into that trash can.
↓
You should throw the rubbish into that dustbin.
ゴミはあのゴミ箱に捨てるべきですよ。
若者への注意でしょうか。ゴミはゴミ箱へということを伝えています。rubbishは「ゴミ、くず、がらくた」でtrash canは「ゴミ箱」ですから、英文は意味的にも文法的にもまったく問題ありません。
しかし、すでに (1) と (2) の解説を読んでいる方はお気づきかと思いますが、ここでもアメリカ英語とイギリス英語がごちゃ混ぜに使われているため、どちらかに統一した方が良いのです。
❖ 同じ意味なのに単語が全然違う
英語は話される地域によって、同じ意味を表すものでも使用する単語が異なることがあります。
| アメリカ英語 | イギリス英語 | 単語の意味 |
|---|---|---|
| apartment | flat | アパート |
| can | tin | 缶 |
| fall | autumn | 秋 |
| elevator | lift | エレベーター |
| gas | petrol | ガソリン |
ここに挙げたのはほんの一部ですが、やはり私たちに馴染み深いのは左側に書かれているアメリカ英語の方でしょう。英語を学び始めたころ季節の中で「秋」だけ2種類の言い方があると習い、「どういうときに使い分けるのだろう」とものすごく疑問に思いましたが、使われる地域の違いなのでした。
(3) の英文には次の語が統一感なく使われていました。くれぐれもごちゃ混ぜにならないようにしましょう。
| アメリカ英語 | イギリス英語 | 単語の意味 |
|---|---|---|
| trash | rubbish | ゴミ |
| trash can | dustbin | ゴミ箱 |
みなさんがどちらの語を好んで使うかは自由です。
❖ first floorは何階のこと?
ただし、中には注意が必要な言い回しもあり、知らないと現地で困ってしまうことがあります。
first floor
さて、これは何階のことでしょうか?
「1階!」と威勢よく答えた方、アメリカなら正解です。しかし、イギリスではなんと「2階」を意味するのです。イギリス英語で1階は ground floor(地上階)と言い、エレベーターでも「G」という記号が使われています。イギリス旅行中、デパートで「バッグ類はfifth floorだよ」と言われてとっさに「あぁ、6階か」と思えるかどうかが大事なのです。
ところで食べ物の話ですが、chipsという語もアメリカとイギリスではポテトの形状が異なります。アメリカではいわゆるポテトチップスを、イギリスではフライドポテトを意味します。なるほど、だからイギリス料理のfish and chipsのポテトはあの形をしているのですね。
では、解答を再確認しておきましょう。
解答(再掲)
【答え:△】
You should throw the rubbish into that trash can.
↓
You should throw the rubbish into that dustbin.
ゴミはあのゴミ箱に捨てるべきですよ。
(4)
【答え:△】
The weather’s awful but she don’t care. She’s out there dancing in the rain.
↓
The weather’s awful but she doesn’t care. She’s out there dancing in the rain.
天気は最悪だが、彼女は気にしていない。雨の中、外で踊ってるよ。
最終回にして簡単な問題でした。sheという主語に対してdon’tを使うなんて、英語の初学者がよくやる間違いです。いわゆる「三単現の s 」というやつで、当然doはdoesに変化させなくてはいけません。――学校で習う「正しい文法」では。
そう、学校の授業でこの英文を添削するのであれば私も英語教師として迷わず「×」にします。でも実際にはこういう英語が地域方言として使われているということは知っておいてほしいのです。
❖ 「三単現の s 」を使わない人たちがいる
三単現の s を使用しない英語のバリエーションとして黒人英語やシンガポールの英語などがあります。イギリスの方言の一つである「イースト・アングリア英語」などもそうです。
だからこれらの英語を話す人たちは、本来she goesと言うべきところをshe goと言ったりします。
ビートルズが好きな人なら『Ticket to Ride』という歌の中に、三単現の s が使われていない箇所があるのをすでに知っているはずです。
She’s got a ticket to ride
But she don’t care
彼女は(別れの)切符を手にした
でも彼女は(僕のことなんか)気にしてないのさ
❖ 英語の多様性を楽しめるという贅沢
この歌の細かい解釈などは置いておきますが、ここでdon’tを使うことで彼女への想いが口語感たっぷりに語られていることがわかります。大事なのは、こういう英語を聞いたとき、または小説のセリフの中で見たときに「あっ、間違えてるな」とか「教養がないな」などと思わないことです。
日本語の方言で考えてみるといいかもしれません。「好きやねん」と言われてみなさんは何を思うでしょうか。私は素直に嬉しいなと思います。「『好きです』と言うべきだろ」とは誰も思いませんよね。
もちろん、作文など書き言葉として方言が使われていると違和感がありますから、そのときは「『ですます調』にすべきだ」と感じるかもしれません。でも、日本語としては間違っていない。この考え方が大切です。
英語好きの皆さんのことですから、インド映画やスコットランドが舞台の映画などを観ることもあるかもしれません。そんなとき、特徴として分かりやすい発音に目が行きがちですが、文法にも一定の法則があって、そこに気付けたとき英語の多様性をより強く感じられるはずです。
ある意味、聞いて気づけるくらい英文法を身につけた上級者向けのお楽しみ要素とも言えますね。とても高級な英語の楽しみ方です。それを踏まえて、解答をもう一度見ておきましょう。
【答え:△】
The weather’s awful but she don’t care. She’s out there dancing in the rain.
↓
The weather’s awful but she doesn’t care. She’s out there dancing in the rain.
天気は最悪だが、彼女は気にしていない。雨の中、外で踊ってるよ。
(5)
【答え:〇】
A photo surfaced of the missing hiker.
行方不明の旅行者が映った写真が出てきた。
「この英文を日本語に訳しなさい」と言われたらちょっとドキッとする人もいるかもしれません。photoは「写真」、surfaceは「表面」?いや、ここでは-edがついているから動詞の「現れる」か・・・というところまでは少なくとも辞書があれば大丈夫でしょう。
問題はof以降です。このofは文中でどんな役割をしているか自信を持って答えられますか?「surface of ~」なんて熟語はおそらくありません。となるとof以下は一体何なのでしょうか?
英語の特徴として、「重い要素」を後ろへ置くというものがあります。itを使った形式主語が一番わかりやすい例でしょう。
To believe that Naoto will come on time is absurd.
↓
It is absurd to believe that Naoto will come on time.
ナオトが時間通りに来ると信じているなんてばかげているよ。
❖ 分かりやすさ・読みやすさのための工夫
不定詞などで主語がずいぶんと長くなるときは、例文のように仮に置いたItを主語にして不定詞以下を文末に置くようにしますよね。そうすることで主語と述部の関係がわかりやすくなるというわけです。
もちろん、重い要素が後ろへ置かれるのは不定詞のときだけではありません。
Kaishu introduced one of the most influential samurais from Kagoshima to Ryoma.
海舟は鹿児島出身の最も影響力のある侍の一人を龍馬に紹介した。
Kaishu introduced to Ryoma one of the most influential samurais from Kagoshima.
海舟は龍馬に鹿児島出身の最も影響力のある侍の一人を紹介した。
通常であればintroduce A to B(AをBに紹介する)という語順を取るのですが、Aの要素が重いときにはintroduce to B Aという語順に変わることがあります。5文型の考え方的には正しくないかもしれませんが、このように文の要素を移動させて読みやすくする工夫も英語にはあるのです。
実は (5) の英文では、これとまったく同じというわけではないものの、似たような移動が行われているのです。
A photo of the missing hiker surfaced.
↓
A photo surfaced of the missing hiker.
行方不明の旅行者が映った写真が出てきた。
なんと、元々はa photoにくっついていたof the missing hiker(行方不明の旅行者の)が後ろへ移動していたのでした。このような動きを「外置」といいます。主語と動詞がより近づくことで読みやすくなるいう効果もあるのですが、相手に特に伝えたい内容を文末に持っていくという英語の情報構造とも深く関係があるようです。
この外置を意識して訳すと「写真が出てきたんだけど、実は『行方不明の旅行者が映ったやつ』だったんだよ」という感じでしょうか。どんな写真なのかという情報を印象付けています。
こういう少し特殊な文体の英文は慣れるまでは難しさを感じますが、主に書き言葉で使われるものです。日本語と比べると英語の語順はがっちりと決まっていることが多いのですが、こういう例を見ると案外柔軟であることが分かります。英語も人間のことばですから、決して杓子定規なものではないのです。
まとめ
英語を使う上で知らなくてはならない「標準」や「正しい形」を知っているからこそ、今回扱ったような「標準的でないもの」や「例外」に気付き、楽しむことができる。この連載を通じて英文法のさまざまな姿を見てきた皆さんには、もうそれができます。
分厚い参考書を一冊終えた程度で英文法の学習を終えた、などと言ってはいけません。文法や語法は非常に多様で、ものすごく奥深い世界なのです。これからも同じ英語愛好家として、ともに英文法を楽しみましょう。
大竹保幹さんの本
『子どもに聞かれて困らない 英文法のキソ』では、「仮定法」をはじめとする、子どもが抱きそうな疑問・質問に対して、ある程度答えられるように英文法の基礎を学ぶことができます。英語を学ぶ面白さに触れられる雑学的な小話も随所にあり、楽しみながら英文法を復習できます。
boocoで読める!アルクの新刊、続々登場
語学アプリ「booco」なら、アルクのベストセラー書籍200タイトル以上が、学習し放題!
「キクタン」などアルクの人気書籍800冊以上が音声対応。「読む」に対応した書籍では、本文と音声をスマホで手軽に利用できるほか、一部の書籍では、学習定着をサポートするクイズ機能で日々の復習や力試しも可能です。さらに、Plusプランに加入すれば200冊以上の書籍が学習し放題に!
boocoの「読む」機能では、次のような使い方ができます。
① 学習したいページを見ながら音声を再生できる
② 文字サイズや画面の明るさを調整できる
③ 書籍内検索ができる
※ これらの機能には一部の書籍が対応しています。

▼「booco」の無料ダウンロードはこちらから