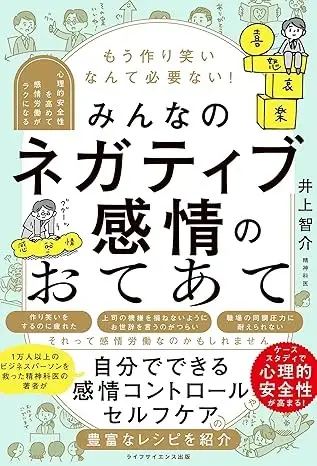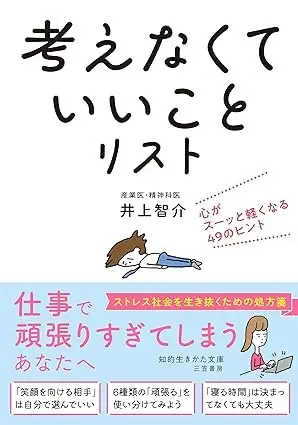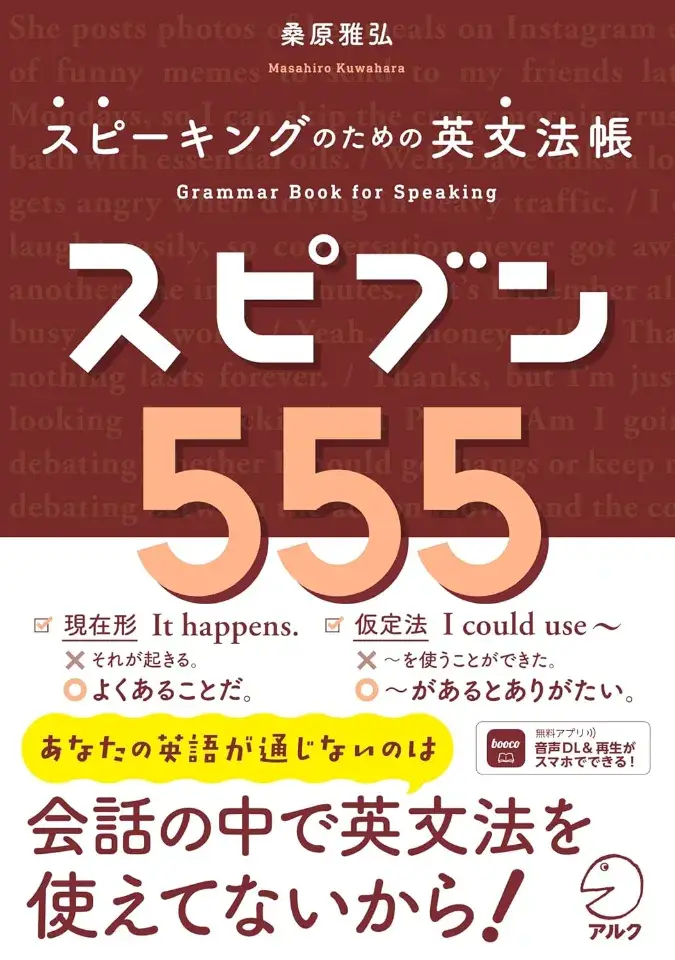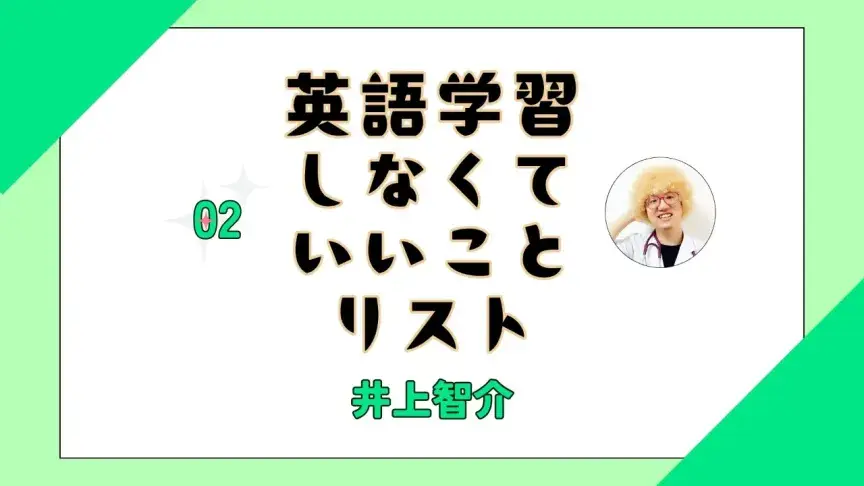
「継続は力なり」とは言うものの、英語の勉強って三日坊主になりがち・・・ですよね?実はモチベーションの維持が一番難しいのかもしれません。そこで、“イングリッシュ無重力”の経験者である医師・井上智介さんに、心が軽くなるアドバイスをしていただきましょう!ところでイングリッシュ無重力って、何?
「英語の勉強続かない」問題
お久しぶりです。危うく一回で打ち切りに・・・はならず、無事に連載第2回に入りました。精神科医で産業医の井上智介です。
暑い日が続きますが夏バテしていませんか?英語への熱い気持ちはバテていませんか?私はギリです。
さて、「英語学習 しなくていいことリスト」初回は読んでいただけたでしょうか。「英会話が苦手で・・・」という情けない話や、いろいろな勉強法に手を出すものの、どうしても継続できない話などに触れました。
いやね、私のパターンって、「やるぞ!」と始めるんだけど、数カ月くらい経つと知らぬ間に止めている。そして、しばらくして「よし、もう一回頑張るか!!」と参考書を開くと、「あれ・・・?このページ、前にもやったよな」ってなる。既視感に何回も襲われるんです。
でも、これって私だけじゃないですよね?こういうことが続くと、「意志が弱いなあ」って自分を責めちゃうんですよね。さらに悲しいのが、そんな風に自分を責める割に、次の日から気持ちを切り替えてガリガリと勉強する!なんてことは一切ない。人間って、そんな急には変わらんもんです。
「英語ができなくても死なない」から
ただ私、思うんですよ。「やらない」には「やらない」なりの理由があるんじゃないかと。いわゆるモチベーションってやつ。つまり、目的意識です。
自己分析をしてみると、英語の勉強が続かない最大の原因はズバリ、そこにある。「なぜ英語をやるのか」が完全にぼやけている。ふと思い立ち、「よし!今日から英語やるぞ!」と始めることは多々あります。それで最初は勢いで突っ走れるけど、その状態はなかなか続かない。
じゃあ、なぜ続かないのか?―― 結局、「英語ができなくても別に死ぬわけじゃないしな~」と心の奥で思っているからです。ハングリー精神が足りない。だから今日も「まあいっか」で終わって、明日もまた「まあいっか」でずるずると時間だけが過ぎていく。そして、気づけば参考書も行方不明に・・・。

もうね、明日からすごいから。めちゃくちゃやるから。
いや、もちろん心のどこかでは思ってますよ。「英語、ペラペラになったらカッコええなあ!」って。最近の大阪なんて、万博の影響もあってか、見かける外国人の数もめっちゃ増えているんです。街を歩くといろいろな言語が飛び交っていて、「英会話ができたら世界も広がるやろうな」とひしひし肌で感じます。
高いモチベはなくていい
その一方で、AIがかなり優秀になってきている現実もありますよね。だから英語ができなくても「なんとかなるかなあ・・・」どころか、「なんとでもなるわな!」と、できないことに超前向きになっちゃう。そうなると、自分の怠けグセを肯定し始める。やらない言い訳を正当化していっちゃう。デジタルテクノロジーの進化に、勉強のモチベーションを奪われてしまう。
・・・そろそろ、「おい井上、苦手の理由を語る割に悲壮感がないな」と思われたかもしれません。はい、確かにそうです。そこは否定いたしません。というのも、こうした自己理解・自己分析の結果、達した境地があるんです。
そもそもが無理ゲー、そして減点方式
それは、モチベーションを上げようとするなんて無理ゲーだな、ってこと。そもそも、苦手意識のあることに向き合っているのに、やる気まで上げるなんて無理でしょ?だから、いっそ開き直ることにしたわけです。「モチベーションなんていらん!」と。そう考えると楽です。

そもそも、勉強する・しないの前提がモチベーション、という構造が甘かった。そんなことでは、YouTubeとかで「朝4時に起きて勉強してまーす!」みたいな高い志&高いモチベを維持して勉強する人を見るたび、「ああ、俺なんて・・・」と感じて心がへし折られるだけ。
この流れは、いわば「自分に対する減点方式」なんですよ。ダメな所を見つけては自分を責め、どんどん自分を減点していく。そりゃしんどくなるし、勉強なんて続くわけがありません。
「モチベ0(ゼロ)からの加点方式」でいい
だから私は、思い切って発想を変えました。「モチベーションゼロ」がスタートラインです。
それで勉強できるの?と思われたかもしれませんね。でも・・・あなたも会社に行くとき、正直、同じじゃありません?「今日はマジで行きたくない」朝でも、なんやかんやで結局出社していますよね。モチベなんて関係ないですよね。「とりあえず会社に到着したし、今日はこれだけでOKにする」って日もありますよね。
英語学習も同様の扱いにしたんです。モチベゼロから始めて、「とにかくちょっとでも触れたらOK!」ということに。
つまり、加点方式です。例えば、英単語を1個だけ覚えた、英語の文章を1文だけ読んだ、語学学習アプリを開いた、そのどれもが加点要素。「レベルが低いな」と言ってくる人もいるかもしれません。でも、そんなん好きに言わしときましょ!「低い所でめっちゃ頑張ってまーす!」って、堂々と胸を張りましょ。それが、私自身も含めて立派な「自分なりの生存戦略」です。
永遠のゼロでなければいい
モチベゼロからスタートするメリットは、「必要以上に自分を傷付けない」という点にあります。限られた人生の中で、「自分はダメ」なんて思う時間は少ない方がいいんでね。
ただしここで1つ、当たり前のことを言わせていただきます。それは・・・何もしないと加点されません!ず~っとゼロです!永遠のゼロです。さらにヤバいことに、ゼロの状態というのは心地よく、そのまま何もせずあっという間に時間だけが過ぎていくことも。
ぶっちゃけこれ、私のいつものパターン。まさにイングリッシュ無重力状態。このゾーンに入ると、当然ながら成長もゼロです。

なので、英語を勉強するモチベはゼロでいいんだけど、無重力状態からの脱出は必要。つまり、何でもいいから加点要素に触れ続けること。加点要素が何なのかは、人それぞれ異なります。単語帳を開く、オンライン英会話をする、アプリで発音練習など、何でもOKです。
付け加えるとすれば、「加点要素までのアクセスの良さ」が超重要だと個人的には考えています。というのもね、ほら、「1日たった5分続けるだけ!」みたいなうたい文句のアプリとか本とか、見たことありません?あれこそ、「その5分ができんのやがな!!」というジレンマを生むんですよね。アプリを立ち上げるまでが、本を開くまでが、そらもう腰がかなり重いのよ。
勉強する環境、洗練させなくていい
だからこそ私は、「いかに加点要素までのアクセスを良くするか」をめちゃくちゃ意識しています。というわけで、私が実際にやっている工夫を紹介させていただきますね。
【机の上、開けっぱなし作戦】
はい、まずはその名もそのまま、「机の上、開けっぱなし作戦」です。英語の勉強において、机は片付けない!「英語の本は閉じたら終わり。閉じてしまったら次に開くのは来週。本棚にしまったら半年後になるぞ!」、そう自分に言い聞かせています。
本を開きっぱなしにしておけば、勉強を再開するときも「ここからやな」とスムーズに始められる。勉強する机が1つしかない場合や、他の作業でも使う机の場合は、「開けっぱなし専用エリア」を決めておきましょう。机の端っことかね。「ここだけは英語の本を開けっぱなしにしておくスペース」みたいな感じです。
【トイレ英語】
そして、もう1つが「トイレ英語」。これは超古典的な方法です。覚えたい単語を紙に書き、家のトイレに貼っておくだけ。これがまた効くんですわ。
――はい、聞こえました。「トイレじゃなくて部屋の壁に貼るのはどうよ?」という声が。これね、私も最初やってみたんです。でも・・・カレンダーと一緒で、いつの間にか完全に壁と同化して全く見なくなります!もはや、貼ってあることすら忘れます!
それに対しトイレだと、用を足す間は手持ち無沙汰になるじゃないですか。小さい方でも、10秒くらいは。その間はやることもないので、チラ見してしまうわけです。で、何回も目にしていると、いつの間にか頭に残っている → 同じ単語・文章だといつか飽きる → 別の単語に変えようと思える。そんないいサイクルを回せるようになります。
ちなみに私のケースだと、一度に貼る単語数は3~5個がちょうど良かったと感じました。10個くらい書いて貼った時期もありましたが、“覚えなければ”という義務感がしんどくて、トイレでお腹だけじゃなく、頭まで痛くなってくるという・・・。
「続かない」で悩まなくていい
結局、私のようにモチベーションゼロの場合、大切なのは何をするかじゃないんです。「英語に触れている時間をいかにして作り出すか」「その頻度をどうやって増やすか」という所からなんです。
こういう小さな小さな工夫が、英語の勉強との距離を縮めてくれる。そして、「もういいか・・・」と諦めて投げ出す前にとどまることができ、「・・・まあ、やろっかな」と立ち上がりやすくなるんです。長期的に考えれば、それがゆくゆくは「習慣」となっていく。
もちろん、EJを読んでいる方は私よりもはるかに英語ができる人ばかりでしょう。それでも、たまに「勉強が続かん」「なんかモチベ上がらん!」と悩んだときに、「モチベなんてゼロでもよくね?」と考えられるなら、少し気持ちが楽になると思いません?
私はそんなに意志が強くないし、そもそもバカでかい夢も持っていない。それでも、自分の高いプライドを傷つけないように、コンプレックスと向き合っていく。誰のペースでもない自分の歩幅で進んでちょっとずつ加点できたら、それで充分。
まだまだの道のりは長いけれど、少しずつ、少しずつ進んでいきますよ!