
「世界が見える 翻訳の不思議」第12回。今回は翻訳家の有好宏文さんが、ユードラ・ウェルティの作品を中心に、アメリカ南部に特有のストーリーテリングの魅力を紹介します。「おしゃべりは耳で書く」とは一体どういうことでしょうか。
アメリカ南部に伝わるストーリーテリングの伝統
『アラバマ物語』(旧訳、原題To Kill a Mockingbird)、改め『ものまね鳥を殺すのは』(新訳)の著者ハーパー・リーは、アラバマを含むアメリカ南部のことを、「ストーリーテラーたちの世界」と呼んだ。リーによれば、かつて劇場も舞踏場も映画館もなかったころ、田舎町に住む南部人たちは、互いに小話を披露し合うのを唯一の楽しみにしていたそうだ。
暑い南部のことだから、人々は家の前の風通しのいいフロント・ポーチに腰掛けて、うそとも本当ともつかない話に興じていたのだろう。今でこそ、ちょっと大きい街まで行けば映画館はあるし、というか、もはやみんな自宅でNetflixを見ているけれど、それでもまだストーリーテリングの伝統は健在で、毎年夏になると各地でストーリーテリング・フェスティバル、つまり、小話披露会が開かれ、街のおしゃべり自慢たちが自信作を引っ提げて舞台に上がる。

南部テネシー州のアパラチア山麓のジョーンズボロという人口6000人弱の街は、「ストーリーテリングの都」を名乗り、国際ストーリーテリング・センターなる施設を運営しているし、イースト・テネシー州立大学に至ってはストーリーテリング専攻の修士号まで出している。
考えてみれば、南部作家マーク・トウェインを一躍有名にした短編小説「ジム・スマイリーの跳び蛙」も、語り手がどこかで聞きかじった物語をとうとうと語るスタイルの与太話だし、かの『ハックルベリー・フィンの冒険』だって、ミシシッピ川をイカダで下るという大筋よりも、途中にどんどん繰り出される小話や、生き生きとした語り口に真骨頂がある。
今年の7月には、テレビ局のPBSが『Southern Storytellers』というドキュメンタリーを放送していた。現代アメリカ南部の作家、ミュージシャン、映画制作者たちが、いかに南部の複雑な歴史と伝統の中でストーリーを作り上げているかを記録した番組である。そうそうたる顔ぶれが、自分の声で創作の秘密を語っていて、見応えがあった。やはり、南部では今でもストーリーテリングが大事なんだな、と納得した。
ユードラ・ウェルティの奇想天外な物語
このドキュメンタリーの中で、何人かの作家やミュージシャンが、敬愛するストーリーテラーとして、ユードラ・ウェルティの名前を挙げていた。
ウェルティは故郷の南部ミシシッピ州の土地と人間を描き続けた作家で、『デルタの結婚式』や『ポンダー家の心』が日本語に翻訳されている(残念ながら、ほとんどが絶版状態だが)。『大泥棒と結婚すれば』を訳した青山南はウェルティを「おしゃべりの巨匠」と呼んだが、確かに、南部人のおしゃべりを書かせたらウェルティに並ぶ者はちょっといない。現代のストーリーテラーたちが好んでウェルティを読むのもうなずける。
なかでも、短編「わたしが郵便局に住んでいるわけ(Why I Live at the P.O.)」と「石化人間(Petrified Man)」はおしゃべりの傑作で、アメリカでは数々のアンソロジーに収められている。だが、このおしゃべりの雰囲気を訳すのが至難の業だからだろう、どちらもまだ日本語には翻訳されていない。同じく南部女性作家だと、フラナリー・オコナーの全短編やカーソン・マッカラーズの短編集は、ちくま文庫に入ってよく読まれていることだし、筑摩書房さん、ぜひ次はウェルティ短編集なんていかがでしょうか。
「わたしが郵便局に住んでいるわけ」は、語り手の女性が、タイトルのとおり、郵便局に住んでいるわけを読者に向かってべらべらとまくしたてる話である。語り手いわく、妹には恋人を奪われ、ひげを何十年も伸ばしている父親にはひげを切れと言ったと激怒され、女物の着物姿でケチャップをがぶ飲みする叔父には火のついた爆竹を寝室に投げ込まれる。家族全員にそうやって迫害されるので家を出て、郵便局に住んでいるのだと彼女は語る。
エキセントリックな家族たちの悪行があまりにとうとうと語られるものだから、なんてひどい人たちなんだと圧倒される。説得されかける。でも、彼女の話をよく聞けば、この語り手もどうやらただ者ではない。例えば、家を出るときに持って来た物のリストが、なんだか変だ。昔みんなで母親にプレゼントしたミシンから、自分がお金を出した分として、モーターだけ外して持って来たというし、応急手当ての方法が書かれたカレンダー、温度計、ウクレレ、スイカの皮のシロップ漬け、青い鳥が描かれた壁掛けの花瓶、これらもみんな持って来て、郵便局の窓辺に外から見えるように並べているのだという。
うそとも本当ともつかない奇想天外な話をべらべらと語る、南部ストーリーテリングの王道を行く作品である。
「石化人間」では、田舎町の美容院で、美容師のリオータと客の2人の女性が街のゴシップに興じている。客にシャンプーをしながら、コテコテの南部なまりで下品な話題をしゃべりまくるリオータが強烈なキャラクターで、小説家のキャサリン・アン・ポーターはこれを「俗悪さの臨床研究として第一級」と褒めたたえた。客の女が妊娠しているという話から、リオータが、結合双生児の遺体のホルマリン漬けを近所のフリーク・ショーに見に行くように勧めるあたりなど、読んでいてちょっと恐ろしくなった。
この短編を読んでいると、隣の椅子で自分も頭を洗われながら、彼女たちの話を聞いているような気がしてくる。話の脈絡はよくわからないが、とにかくおしゃべりがおしゃべりを呼び、どんどん下品な方向に流れて行く。読み終えても、美容師リオータの声がまだ聞こえる。
おしゃべりは耳で書く
ウェルティのすごいところは、奇想天外な話をしながら、ちゃんと人間を描いているところである。下手をすると現実味のない人物造形に陥りそうな話なのに、人物がみんな生きている。ミシシッピの小さな街の郵便局や美容院に本当にいそうである。
どうしてそんなことができたのか。その創作の秘密をウェルティは語っている。
「物語を書き始めるずっと前から、わたしは物語に耳を澄ませていました。物語をただ聞くんじゃなくて、もっと感覚を研ぎ澄ませて、物語に耳を澄ませるんです」。
「おしゃべりの巨匠」は、おしゃべりをゼロから創作したわけではなかったのだ。ミシシッピのストーリーテラーたちの話に耳を澄ませ、それを書き留めてきたのである。きっと彼女たちは本当にいるのだ。彼女が登場人物たちを愛していたことは作品を読めばすぐに分かるが、それはきっと、そんなミシシッピの人たちを愛していたからなのだろう。
台所で焼いた原稿がどう復活したのか
つい先日、ミシシッピ州ジャクソンにある、ウェルティが生前暮らしていた家に出かけた。案内係の女性が台所を見せてくれたときに、電気コンロを指さしながら、かつてここには、まきストーブがあったのだと教えてくれた。「Petrified Man」の原稿がボツになって送り返されて来たときに、落胆したウェルティは原稿をそのストーブで焼いたのだという。
ところが、その後、気が変わった編集者が、やっぱり雑誌に掲載したいと手紙を寄こした。しかし、原稿はもう焼いてしまった後である。しばらく返信せずにいたら、何度も催促の手紙が届く。それでとうとう、ウェルティは記憶をもとに原稿をもう一度書いて、送ったそうだ。そういうわけで、現在読むことのできる「Petrified Man」は、この書き直された方のバージョンである。
ウェルティの家の台所で、案内係の女性に、幻の「Petrified Man」を読んでみたかったかと聞かれた。でも、さほど読みたいとは思わなかった。二つのバージョンがあまり違う気がしないからだ。きっとウェルティは、ほとんど同じ原稿をさらっと書いてしまったのではないか。原稿を焼いた程度で、あのリオータのおしゃべりが消えてしまうはずはない。
家に帰ってから、ウェルティの伝記やインタビュー集をめくってみたら、ビンゴ。あるインタビューで、「一字一句まで全く同じ原稿を再現できたんですか」と聞かれて答えている。「たぶんね。簡単でしたよ。また燃やしたって、また一から書き直せます。こういうのは、音楽を聴くみたいなものなんです。一度聴いた曲は歌えるでしょう」。なるほど、耳のいい作家というのは、こういうものなのかと感心した。
でも、ひとしりきり感心してから、ふと思った。ウェルティは本当に原稿を焼いたのだろうか? 何しろ、南部のほら話に揉まれて育った小説家である。もしかしたら、ほら話かもしれない。あるいは、ことの真偽なんてどうでもいいのかもしれない。
本文写真:Francesca Tosolini from Unsplash
文学カテゴリー記事一覧
boocoで読める!アルクの新刊、続々登場
語学アプリ「booco」なら、アルクのベストセラー書籍200タイトル以上が、学習し放題!
「キクタン」などアルクの人気書籍800冊以上が音声対応。「読む」に対応した書籍では、本文と音声をスマホで手軽に利用できるほか、一部の書籍では、学習定着をサポートするクイズ機能で日々の復習や力試しも可能です。さらに、Plusプランに加入すれば200冊以上の書籍が学習し放題に!
boocoの「読む」機能では、次のような使い方ができます。
① 学習したいページを見ながら音声を再生できる
② 文字サイズや画面の明るさを調整できる
③ 書籍内検索ができる
※ これらの機能には一部の書籍が対応しています。

▼「booco」の無料ダウンロードはこちらから

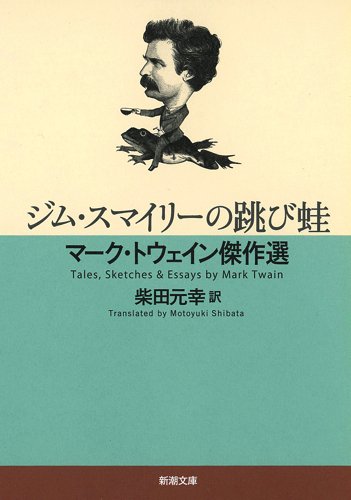










![『スピーキングのための英文法帳 スピブン555』[音声DL付]](https://image-ej.alc.co.jp/images/GamGSrTWRko6iAR2V9kR.webp)
