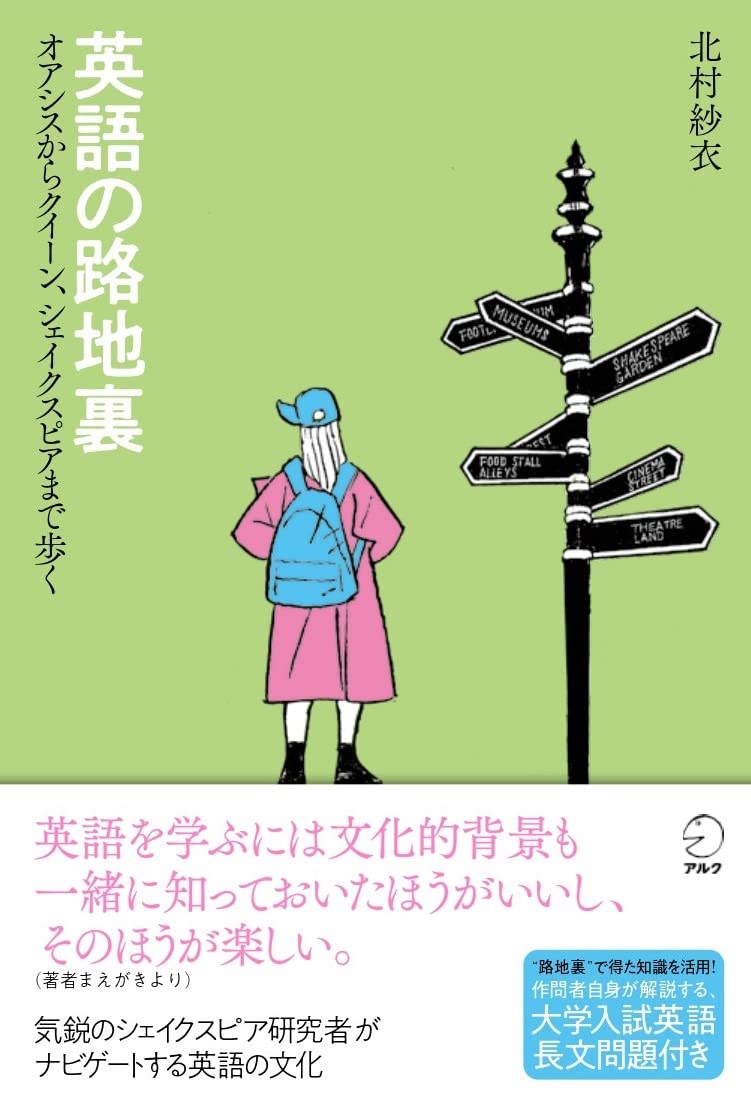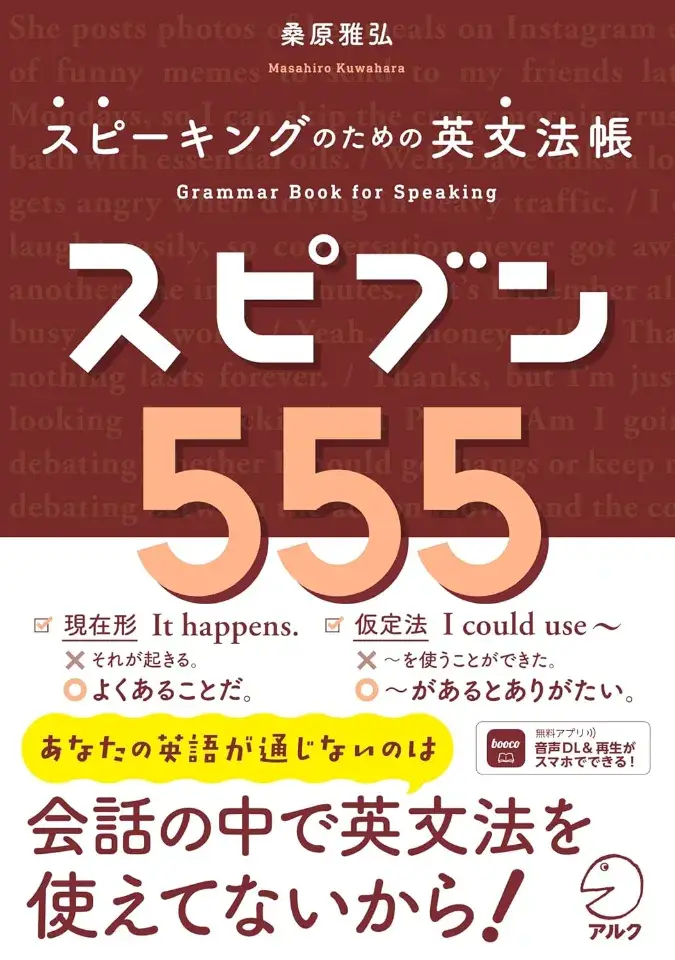「大学教育に文学は不要」「英文学を学んでも英語ができるようにならない」という声を聞くことがあります。こういった見方について、シェイクスピア研究者で大学准教授にして、自称「不真面目な批評家」であり、著書『お砂糖とスパイスと爆発的な何か』が好評の北村紗衣さんに、2回にわたって(至って真面目に!)検証していただきます。第1回のテーマは「大学で英文学を学ぶのは無駄で役に立たないのか?」です。
大学の英語教育に文学は不要か?
私は大学でシェイクスピアと英語を教えています。本務校である武蔵大学では専門教育のゼミのクラスで、非常勤先の慶應義塾大学では文学部の英語のクラスで、1学期かけてシェイクスピアを読んでいます。1年は2学期から成るので、シェイクスピアを読まない学期は、もっと時代が新しい英語の戯曲を読むことにしています。
そんな教員なので、「文学は『不要』か?」という問いに対しては大きな声で「いいえ、まさか!」と答えるほかないのですが、この記事では、なぜ私が大学教育で文学が必要だと考えるかを説明していきたいと思います。
まともで立派な研究者であれば、ここで、人文学の価値とか、学問を役に立つ、役に立たないで分けることの問題点などを指摘するところですが、私はあまり立派なシェイクスピア研究者ではないので、そういうことはしません。正攻法で人文学の価値を論じている方々はとても正しいと思いますが、私はもう少しえげつない方向性で、なぜ 大学教育、特に英語教育に文学が必要 なのかを 指摘したいと思います。
シェイクスピアがやり玉に挙げられる理由
シェイクスピアは昨今、英語教育をはじめとする大学教育を語るときに一番、不要だとして攻撃されている作家(※1)です。
シェイクスピアが攻撃される理由としては、まず批判者がそれ以外に大学で教えられている作家を知らないから、ということが挙げられるでしょう。シェイクスピアが大学の英文学の授業で取り上げられる機会は以前よりも減っており、イギリス・アメリカ以外の地域で書かれたものをはじめとして、 多様な作品が教えられる ようになっています。
しかしながら、このような議論で、ハリー・ポッター・シリーズを描いたJ・K・ローリングとか、著作『侍女の物語』がテレビドラマ化されて大ヒットしたカナダの作家マーガレット・アトウッドとか、アメリカ黒人文学を代表する作家で、最近、著作『ビール・ストリートの恋人たち』が映画化されたジェイムズ・ボールドウィンなどが出てくることはまずありません。たぶん、このような作家が大学で頻繁に教えられていることも知らないし、ひょっとするとそのような 定番作家の名前もコンテンツ力も知らない人々が、大学教育を批判 している可能性があります。
もう一つの理由として、批判をする人たちの頭の中では、シェイクスピアが古くさい権威の象徴、名前はよく知られているが面白くないものの代表になっているということがあります。シェイクスピアの名前を出すことで、人々が「そうだそうだ、そんなつまらない遺物を大学で教えるな」と思ってくれるだろう、と予想しているのでしょう。しかし、これは大きな間違いです。
売り切れ続出のシェイクスピア劇の公演
既に一度、 別の記事 で書いたことがあるのですが、 シェイクスピアは今なおコンテンツとして極めて大きなビジネス上のポテンシャルを持っている 作家です。シェイクスピアを無用の長物として攻撃している方々はご存じないことでしょうが、人気俳優が舞台でシェイクスピア劇に出演すると、イギリスでも日本でもチケットがすぐ売り切れます。
今年の5月に渋谷のシアターコクーンで岡田将生と黒木華が『 ハムレット 』に出演したときはチケットの入手がかなり困難でしたし、昨年の夏に堂本光一と井上芳雄のダブル主演でシェイクスピアの『二人の貴公子』翻案ミュージカルである『 ナイツ・テイル-騎士物語- 』が上演されたときは、すごい速さで席が売り切れました。女性アイドルもシェイクスピアに進出しており、SKE48が今年の4月に『 ハムレット 』を上演しています。
古典が俳優やクリエイターを引き付ける理由
このようにチケットがすぐ売れてしまうのは俳優がスターだからですが、スターはシェイクスピアをやることにいつも興味があります。というのも、 シェイクスピア劇は役者の魅力を最大限に引き出してくれるよくできた台本 だからです。しかも 著作権が切れている ので、使用料や遺族の意向を気にする必要がなく、クリエイターの采配で 翻案し放題、変更し放題 です。いくら台本を変えても、シェイクスピアは怒りません。
このように高いコンテンツ力を持っているのは、もちろんシェイクスピアだけではありません。英文学に限らず、現在の大学の外国語文学の授業で教えられている作家の作品には、世界中で読まれ、舞台化、映像化されているようなものが多数あります。特に古典については、今読んでも面白くて、 現代のクリエイターを触発し続けているような作品が頻繁に授業で取り上げられています 。
文学は実は「もうかる」
私が学生に シェイクスピアなどの文学を教えるのは、コンテンツとして潜在力のあるものに触れることが、良いクリエイターと良い観客を育て、文化産業の経済的な隆盛につながると考えている からです。
身も蓋(ふた)もないことを言うと、私は、シェイクスピアは使い方さえ考えればかなりもうかると思っています。私自身がシェイクスピアでお金を稼いでいるので、これは比較的、自信を持って言えます。
シェイクスピアを大学で教えることを批判している人たちは、シェイクスピアを使ってどうやってお金をもうけられるか知りません。経営ではニッチな市場の開発が重視されることがあるようですが、私は、 文学を学んだ人たちがもうけられるような市場を作る つもりで大学教育をしています。
さて、そこで出てくるのが、「でも、それ(文学)を英語教育でやる必要はあるのか?」という問いだと思います。これについては、2部作になっているこの記事の、次回でお話ししたいと思います。
▼第2回はこちら↓
北村紗衣さんの新刊
注目のシェイクスピア研究者、北村紗衣が、海外文学や洋画、洋楽を、路地裏を散歩するように気軽に読み解きながら、楽しくてちょっと役立つ英語の世界へとご案内。英語圏の質の高いカルチャーに触れながら、高い英語運用能力を得る上で重要な文化的背景が自然と身に付きます。“路地裏”を抜けた後は、“広場”にて著者自身が作問し解説する「大学入試英語長文問題」も堪能できる、ユニークな英語カルチャーエッセイ。
編集:ENGLISH JOURNAL編集部
(※1) https://bunshun.jp/articles/-/12038
【1000時間ヒアリングマラソン】 ネイティブの生英語を聞き取る実践トレーニング!

大人気通信講座が、アプリで復活!
1982年に通信講座が開講されて以来、約120万人が利用した「ヒアリングマラソン」。
「外国人と自由に話せるようになりたい」「仕事で困ることなく英語を使いたい」「資格を取って留学したい」など、これまで受講生のさまざまな夢を支えてきました。
アプリ版「1000時間ヒアリングマラソン」は、日常、ビジネス、フリートーク、時事英語、物語などの多彩なジャンルのコンテンツを収録し、さらに豊富なアウトプット練習や学習時間の計測などの機能を盛り込み、よりパワーアップして復活しました。
「本物の英語力」を目指す人に贈る、最強のリスニング練習
学校では習わない生きた英語
実際にネイティブスピーカーと話すときや海外映画を見るとき、教科書の英語と「生の英語」のギャップに驚いた経験はありませんか? 「1000時間ヒアリングマラソン」には、オリジナルドラマやラジオ番組、各国の英語話者のリアルな会話など、学校では触れる機会の少ない本場の英語を届けるコーナーが多数用意されています。
こだわりの学習トレーニング
音声を聞いてすぐにスクリプトを確認する、一般的なリスニング教材とは異なり、英文や日本語訳をあえて後半で確認する構成にすることで、英語を文字ではなく音から理解できるようにしています。英文の書き取りやシャドーイングなど、各トレーニングを一つずつこなすことで、最初は聞き取りが難しかった英文も深く理解できるようになります。
あらゆる角度から耳を鍛える豊富なコンテンツ
なぜ英語が聞き取れないのか? には理由があります。全15種類のシリーズは、文法や音の規則、ニュース英語など、それぞれ異なるテーマでリスニング力強化にアプローチしており、自分の弱点を知るきっかけになります。月に一度、TOEIC 形式のリスニング問題を解いたり、書き取りのコンテストに参加したりすることもできるため、成長を定期的に確認することも可能です。
「1000時間ヒアリングマラソン」は、現在7日間の無料トライアルを実施中です。さあ、あなたも一緒にランナーになりませんか?