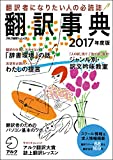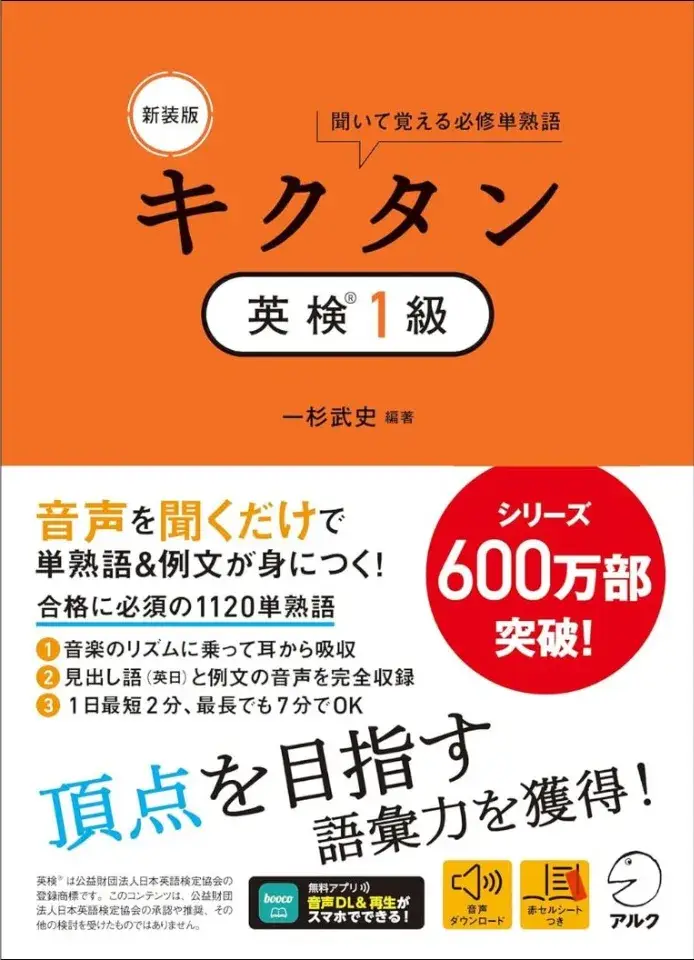翻訳者ってどんな仕事?
語学力を生かせるあこがれの職業。でも、それだけで食べていくのは難しい・・・。これが、多くの人が翻訳者という職業に対して抱くイメージではないでしょうか。確かに、出版不況に加え、Google 翻訳などの自動翻訳の進化により、翻訳業界をめぐる状況にはなかなか 厳しい ものがあります。
そんな中、「ヒト、モノ、カネ、情報が国境を越えて激しく動くこのグローバル化した世界で、 言語というボーダーを超える必要性、つまり翻訳の必要性はますます高まるに違いない 」と語るのが 『翻訳というおしごと』 の著者、実川元子さんです。
本書の対象となるのは、「翻訳者を目指す人」と「もっと活躍したいと願う現役翻訳者」ですが、それ以外の職業の人にも役立ちそうな内容がいっぱい。早速、見ていきましょう。
専門スキルを持ち、客観的に評価し、磨き続ける
とにかく毎日、英語学習
翻訳者にとっての専門スキルといえば、もちろん「翻訳力」。なかでも語学力が重要な要素であることは間違いありません。多くの場合は英語力と言えるでしょう。
そのため、翻訳者になってからも、日々「翻訳力を向上させるための勉強」として、仕事以外で英語に触れることは欠かせません。もともと高い英語力があったとしても、日常的に「今」の英語に触れる必要があるからです。そのためどの翻訳者も、英字新聞や雑誌、ネットのニュースなどを活用して勉強を続けています。
実川さん自身は、1980年代にはニューヨークタイムズ紙の日曜版とヴィレッジヴォイス誌を定期購読。船便を使うので費用がかさみ、年間20万円ほどかかっていたとか。 今でも毎朝、インターネットでニューヨークタイムズ紙とル・モンド紙に目を通し、興味を惹かれた記事はプリントアウトして熟読。翻訳してファイリングしているそうです。
ベテラン翻訳者が続ける「翻訳筋トレ」
金融分野の翻訳で第一人者といわれる鈴木立哉さん。
鈴木さんが、仕事を始める前に必ず実践しているのが「翻訳筋トレ」です。これは「興味を持った英文を音読したり書き写したりした上で、自分で和訳し、さらにほかの翻訳者の訳と比較する」というもの。
翻訳者としてのキャリアが長くなると、どうしても自分の「癖」が出てきてしまいます。自分の訳と他の翻訳者の訳を比較することで、自分の癖に気づき直すことができるのです。
専門的なスキルを持ち、それを客観的に評価し、なおかつ常に磨き続ける。ベテランといわれるキャリアがあるからこそ、自分の仕事の結果を客観視する習慣が必要なのですね。これはどんな仕事をする上でも、大切なことではないでしょうか。
健康、空間、時間を管理する
水泳教室で得た体力アップ以上の効果
実川さんが翻訳者になって10年ほどたったころ。
仕事は順調だったものの、土日も関係なく座りっぱなしで仕事をする毎日に体が悲鳴を上げました。 翻訳者の職業病ともいえる腰痛、さらに偏頭痛や歯痛、顎関節症にも悩まされるようになったのです。
「体を動かさなくては」と水泳教室に通うことにしたものの、レッスンについていけず体力の低下を実感。還暦を過ぎたおばさまたちにも遅れを取るレベルでした。
それでも「運動するしかない」と続けるうちに体調は 改善 。水泳教室に通う時間を捻出するため、スケジュール管理もうまくなってきたとか。水泳教室と自主練の前日は禁酒にしたことで、半年で6キロ減というダイエット効果もありました。
「定期的な運動を自分に課したことで、生活リズムが変わり、働き方が変わり、仕事とプライベートのバランスが変わった」 と実川さん。
忙しさを言い訳に体を動かすことを避けがちな現代人にとって、示唆に富む言葉です。
空間管理が時間管理にもつながった
医療翻訳を専門とする森口理恵さんの仕事場には、なんと椅子も書棚もないそうです。
部屋の隅に胸下までの高さのL字型ボードを設置、その上には4枚のディスプレイが。足元には昇降運動用の踏み台が置かれ、立ったまま仕事ができるようになっているのです。座らないから腰に負担がなく、仕事をしながら踏み台昇降の運動もできて一石二鳥!
そんな森口さんも、以前はリビングに長机を置き資料を広げて仕事をしていたとか。
しかしあるとき、思い切って紙の資料をPDF化し、本などの紙類を大量に処分しました。部屋が片付き、パソコンで資料を検索できるようになったことで、仕事が劇的に 効率化 されたのです。「 部屋がすっきりすると、頭の中もすっきりして、家事や仕事も効率よく片づけることができます。 それがクライアントからの信頼感を生み、自分の自信にもなる」とも森口さん。
これも、翻訳者だけでなく、働くすべての人に役立つ箴言と言えそうです。
プロとしての矜持を持つ
自分自身の意識を変える
翻訳者は下請け業者、あるいはサービス業という見方は少なからずあります。そこから脱却して、クライアントや編集者と対等な立場になるにはどうすればよいのでしょう?
実川さんが考えたのは、翻訳の実力をたくわえることに加え、翻訳者が自分自身の意識を変えること。
自分自身が個人事業主であり、専門職であるという意識を持てば、クライアントに対してギャラや納期について交渉し、どうしても受けられない仕事はきちんと理由を言って断る勇気も沸いてくる。また、クライアントから仕事が来るのをただ待っているのではなく、自らが請け負える仕事について、あるいは仕事のよりよい進め方などを、クライアントに提案してみることもできるだろう。クライアントを「上司」や「会社」と言い換えれば、組織に 所属 して働く人にも通じる言葉です。※本書p185より引用
翻訳者にも、働く私たちにも未来はある!
ちょっと話がそれますが、現在、政府は「雇用 契約 によらない新しい働き方」を検討する段階に入っています。
第1回「雇用関係によらない働き方」に関する研究会を開催しました(METI/経済産業省)
今後は 、翻訳者以外にもさまざまな職業で、組織に 所属 しないで働く人が増えるかもしれません。そうでなくとも、「組織に 所属 していれば安泰」といった考え方は過去のものになりつつあります。会社員でも突然、未経験の業種や職種で働くことになったり、就労形態の変更を余儀なくされたり、育児や介護のためにキャリアプランを変更することもあるでしょう。そんなとき、本書で取り上げている「食べていける翻訳者」の働き方は、ひとつの指針になるのではないでしょうか。
- 専門スキル(自分の強み)を持ち、客観的に評価し、磨き続ける
- 健康、空間、時間を管理する
- プロ(職業人)としての矜持を持つ

- 作者: 島崎秀定
- 出版社/メーカー: アルク
- 発売日: 2016/01/19
- メディア: Kindle版
![]() 翻訳事典2017年度版 (アルク地球人ムック)
翻訳事典2017年度版 (アルク地球人ムック)- 出版社/メーカー: アルク
- 発売日: 2016/01/28
- メディア: ムック
- この商品を含むブログを見る

構成・文:GOTCHA!編集部
GOTCHA(ガチャ、g?t??)は、I GOT YOUから生まれた英語の日常表現。「わかっ た!」「やったぜ!」という意味です。英語や仕事、勉強など、さまざまなテー マで、あなたの毎日に「わかった!」をお届けします。
boocoで読める!アルクの新刊、続々登場
語学アプリ「booco」なら、アルクのベストセラー書籍200タイトル以上が、学習し放題!
「キクタン」などアルクの人気書籍800冊以上が音声対応。「読む」に対応した書籍では、本文と音声をスマホで手軽に利用できるほか、一部の書籍では、学習定着をサポートするクイズ機能で日々の復習や力試しも可能です。さらに、Plusプランに加入すれば200冊以上の書籍が学習し放題に!
boocoの「読む」機能では、次のような使い方ができます。
① 学習したいページを見ながら音声を再生できる
② 文字サイズや画面の明るさを調整できる
③ 書籍内検索ができる
※ これらの機能には一部の書籍が対応しています。

▼「booco」の無料ダウンロードはこちらから