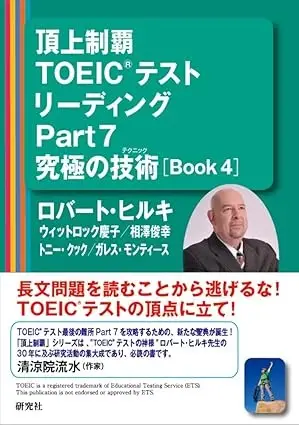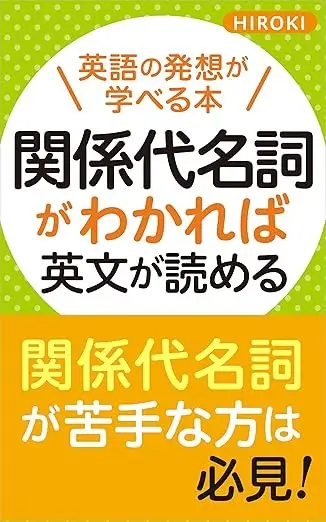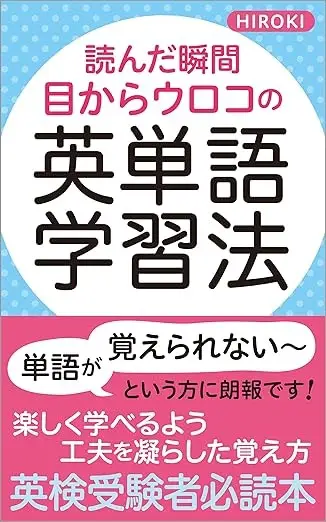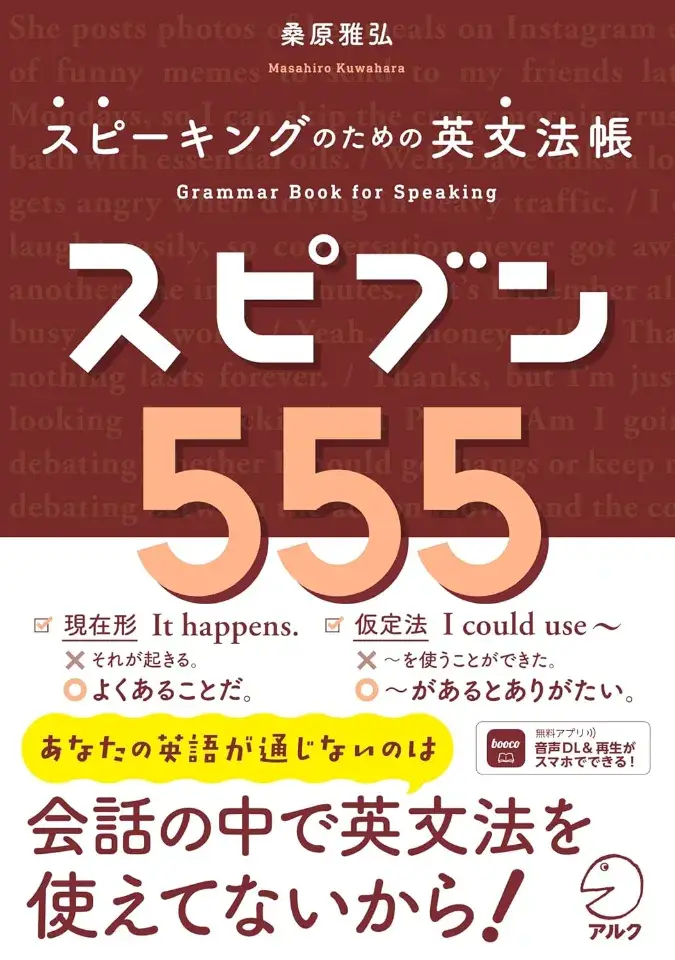TOEICはビジネスシーンに対応したテストです。それぞれの出題意図を知ると、問題への取り組み方が分かります。この記事では、現在600点レベルで、700~800点を目指す人に向けて、解答のスピードと正確さを上げるテクニックをお伝えします(600点は、問題の半分は自信をもって正解できるレベル、800点はまだ20問くらい解ききれない状態です)。テスト全体に対する心構えから、即効性のあるテクニックまで、ぜひ覚えて使ってください。
目次
TOEIC試験全体で使えるテクニック

まず、全体に共通するものを紹介します。
TOEICは早食い競争である
TOEICは、制限時間内にどれだけ多くの問題を処理できるかが問われる、早食い競争のような試験です。早食い競争で料理の味をじっくり味わわないのと同じように、TOEICでも一問一問をじっくり解く時間はありません。全ての問題の配点は同じなので、難しいと感じたら、すぐに次の問題へ進みましょう。そうすることで、時間切れになって、正解できたはずの問題を解けずに終わるのを防げます。
気持ちの上で圧倒されない
楽観的に考えてください。もしこれが全部日本語で書かれた試験であれば、満点とはいわないまでも、間違いなく9割はいくはずです。「同じ人間の言葉でそんなに難しいことを言っているわけではない」とポジティブに考えて、テストに臨みましょう。
リーディングセクションは順番通りに解く
Part 5から順に解いていくことで、徐々に文の長さに慣れ、長文問題への抵抗感が減ります。後ろから解くとマークミスの原因にもなるため、順番通りに解くのがおすすめです。
難しい顔をして解かない
ニコニコしながら解くと、脳が「これは簡単だ」と錯覚し、問題が解きやすくなりますといわれます。心の中でIt is so easy.(楽勝)と言いながら解くのも効果的です。
TOEIC Part 1の解き方のコツ

Part 1~4はリスニングの問題です。Part 1は音声を聞いて、問題用紙にある写真を正しく描写しているものを選びます。
Part 1は「ウォーリーをさがせ!」
聞こえてきたフレーズに対応する人物や動作を、写真の中から素早く見つけ出しましょう。絵本の「ウォーリーをさがせ!」のように、音声と写真を照らし合わせる感覚です。
最後の選択肢を聞くまでに「保険」をキープする
選択肢を聞きながら、正解に近いと思ったものを「保険」として選んでおきましょう。もし最後の選択肢まで聞いて、どれも正解と思えない場合、前の選択肢を思い出せなくて困る恐れがあります。「保険」の選択肢をキープするのは、リスク回避のために有効な方法です。
鉛筆の位置を使って選択肢を追う音声を聞きながら、選択肢に合わせて、鉛筆の先を時計回りに(A)→(B)→(C)→(D)と動かしていきます。良さそうだと思った選択肢のところに鉛筆を置き、最後の選択肢まで聞いて確信が持てたらすぐマークしましょう(イラスト参照)。こうすることで、正解の選択肢を忘れなくなります。

抽象的な表現に備える
写真に写っているものが、そのものずばりの単語で表現されるとは限りません。例えば「車」が写っていても、car(車)ではなく、vehicle(乗り物)のような、総称や抽象的な語を使って表現されることがよくあります。TOEICでは、このような言い換えが多いことを意識しておきましょう。
Part 1対策がビジネスに有効な理由
Part 1では、オフィスの写真やビジネスの場面の写真が出題されるため、対策をすることで、ビジネス関連の語彙が身に付きます。
TOEIC Part 2の解き方のコツ

Part 2は質問・発言を聞いて、それに対する適切な応答を選択肢から選ぶ問題です。
Part 2は「百人一首競技」のようなもの
上の句が読まれたらすぐに反応する百人一首のように、最初の語に特に注意を払い、素早く答えを選ぶ必要があります。
3つ目の選択肢が来る前に保険マークをつける
Part 1と同じく、最後の選択肢の音声が流れる前に、これまでの2つの選択肢のうちどちらかを、保険として、正解の候補にしておくことが重要です。そうしないと、3つ目の選択肢が違うと判断した場合に、適当にマークすることになります。
質問を脳内でリピートする選択肢が読まれる直前に、質問文を毎回頭の中で繰り返しましょう。選択肢の音声を聞いているうちに、質問を忘れてしまわないようにするためです。
Part 2は「流しそうめん」ではなく「回転ずし」!
流しそうめんは、いつ来るか分からないのでタイミングをつかみにくいですが、回転ずしは一定の間隔で次々と流れてくるので、リズムをつかみやすいですよね。
TOEIC Part 2もそれと同じで、一定のリズムで出題されるので、「リズムに乗ること」がとても大切です。音声が流れている間は一時的に息を止めると、より集中しやすくなります。呼吸とリズムを意識することで、Part 2の正答率がグッと上がります。
Part 2はなぜビジネスで大切か
商談で相手の最初の質問を聞き逃さないことは、とても重要です。英語では特に冒頭の言葉に意味が凝縮されているため、意識して聞く必要があります。電話での商談では、相手の顔が見えませんから、音声だけで相手の意図を瞬時に理解する力が必要です。
TOEIC Part 3の解き方のコツ

Part 3は会話を聞いて、内容に関する設問に答える問題です。
Part 3は「天気予報を聞く感覚」で解く
全国の天気予報を聞くときには、全ての情報を聞き取るのではなく、自分に関係のある地域だけに注意を向けます。それと同様に、Part 3の会話でも重要な情報だけを聞き取ることが大切です。
設問の「疑問詞+動詞+目的語」の構造を意識する
設問がWhat does the woman remind the man to do?なら、what remind the man?と重要部分だけを頭に入れましょう。日本語で「何 リマインドする 男性に?」のように簡略化しても効果的です。
一方、What information does the man say she needs?では、what info she needs?に注目しましょう。the man sayの部分からは、会話で誰が解答のヒントを言うかが分かります。
副詞の位置は日英で違うことに注意
What is he going to do next Thursday?という設問の場合、会話ではnext Thursdayを聞き取ることが重要です。日本語では「次の木曜に~」と、時を表す言葉が文頭に来ることが多いため、その後の部分を聞き逃すことはあまりありません。しかし英語では、I am going to ~ next Thursday.と、時間を表す副詞が文末に置かれることが多いため、その前にある肝心な情報(動作や予定など)を聞き逃してしまいがちです。そうならないように、会話全体を聞く必要があります。
TOEICでは、こうした英語特有の語順の違いに慣れることが、正答へのカギになります!
スリーフィンガーメソッドを活用する
3問ある設問の答えを、問題用紙の選択肢で「中指→人差し指→親指」の順に押さえます。ギターでコードを押さえるようなイメージで、3つのアルファベットを記憶してから、一気にマークシートを塗りましょう。
Part 3がビジネスで大切な理由
ビジネスでは、突然の商談でも会話の内容についていけるような、柔軟な対応力が求められます。商談の場面などで、当事者ではなく第三者として会話を聞くケースも少なくありません。Part 3では、そうした状況を想定しながら、「どのように話が展開していくか」「何が重要なポイントか」を把握する力と理解力を鍛えることができます。
TOEIC Part 4の解き方のコツ

Part 4は1人の話(トーク)を聞いて、内容に関する設問に答える問題です。
副詞節の位置が変わる「変化球」に注意
例えば、設問がWhen do you create a file?(いつファイルを作成しますか)だった場合、create a fileがヒントになります。音声でYou create a file before you start a project.(プロジェクトを始める前にファイルを作成します)と流れれば、聞き取りやすく、正解も選びやすいですよね。
しかし、もしBefore you start a project, create a file.のように、create a fileが後から流れると、前の副詞節(Before you start a project)を聞き逃してしまうことがあります。英語では、副詞節の位置が前後に入れ替わることがよくあるので、どちらのパターンでも意味を正しく捉えられるように、文全体を聞き取れるようにしましょう。
Part 4は「その場にいるつもり」で聞くトークが行われている現場にいるイメージで、自分の居場所を瞬時に切り替えて、内容に没入しましょう。
「Xにしようかと思ったけど、やっぱりYにする」パターンに注意
トークでは「Xにする」と言いつつ、最後で「やっぱりYにする」という展開があります。私はこれを「なんちゃって型」と呼んでいます。早とちりせず、トークを最後までしっかり聞くことが大切です。
Part 4がビジネスで大切な理由
留守電メッセージやアナウンスを正確に聞き取る力はビジネスでも必要です。
TOEIC Part 5の解き方のコツ

Part 5~7はリーディングの問題です。Part 5は短文の空所に入る、適切な語を選ぶ問題です。
Part 5は「金魚すくい」
Part 5は、まるで「金魚すくい」のようなものです。金魚をすぐにすくわないと網が破れてしまうように、テンポよくどんどん答えていかないと、時間が足りなくなってしまいます。

トンネル攻略のように、両側から攻める
トンネルを貫通するには、左右両側から掘り進めますよね。Part 5も同じで、文法と意味の両面からアプローチする必要があります。
そのうち、まずは文法(文のカタチ)で解くようにしてください。例えば、「この位置には目的語しか入らないから、-lyで終わる副詞は除外する」といった具合に、文法で絞り込むことで、スピーディーに解答できるでしょう。
5秒悩んだら、それ以上は悩まず「棚上げ」!
Part 5で5秒以上悩む問題があったら、それ以上考え込まず、いったん直感で最も正しいと思う選択肢を選びましょう。そして、解答用紙のその問題の番号に印をつけておくのがポイントです(問題用紙には書き込みができないため)。その後、Part 7を解き終えてからその問題に戻ると、ヒントが見つかることがあります。実は、Part 7に似たような文法表現や言い回しが出てくることがよくあるのです。
大きな声では言えませんが、本試験では、Part 5で問われていた表現が、Part 7の本文中にそのまま登場したという事例もあります。それを参考に、迷っていた問題を再確認して、正答できることもあるのです。
似て非なるtoの使い方に注意!
toが出てきたときに、つい「不定詞のto=後ろに動詞の原形が来る!」と決めつけていませんか?実は「to」には前置詞としての使い方もあり、その場合は後ろに名詞(または動名詞)が続きます。
例:
- obstacle to -ing(〜するための障害)
- key to -ing(〜するための鍵)
- commit oneself to -ing(〜することに全力を注ぐ)
toの後についつい動詞の原形を入れてしまいそうになるので、注意しましょう。
似た単語は「用法」で覚える!
単語は意味だけを暗記するのではなく、文の中でどう使われるか(=用法)も覚えましょう。
insure (~を保証する)/ ensure(~を確実にする) / assure(人に~を保証する)の違い
insure:直後に目的語が続く
例:I have to insure my car before I drive it.(車を運転する前に保険をかけなければなりません)
ensure:直後に「that節」が続く
例:Please ensure that everything is ready. (全ての準備が整っているか確認してください)
assure:「人+that節」の形で使う
例:I assure you that everything is fine.(きっと全部大丈夫ですよ)
こういった単語は、意味を覚えるだけでは不十分です。insure that~、ensure that~、assure you that ~のように、発音しながら、後ろに何が来るかを覚えるとよいでしょう。
Part 5がビジネスで大切な理由
顧客に応対する時に、意味が伝わるかだけでなく、正確な文法、場にふさわしい単語を使えているかが重要で、これらは商談の成否に影響を与えます。文を正しく理解できるということは、自分でも正しく文を運用できるということです。
TOEIC Part 6の解き方のコツ

Part 6はパッセージ(長文)の空所に入る、適切な語句を選ぶ問題です。
文挿入問題は「代数の問題」と同じ感覚で解こう!
Part 6の文挿入問題は、数学の代数問題に似ていると考えると、解きやすくなります。例えば、代数の方程式では、解を求めた後にxに代入して式が正しく成り立つかを確認しますよね。これは「解の吟味」と呼ばれます。文挿入問題も同様に、選んだ文を実際に空所に入れてみて、文章の流れや意味が自然に通るかをチェックする必要があります。
選んだ選択肢が間違っている場合、以下のような理由で文章が不自然になります:
- 時制のズレ
- 代名詞の不一致
- 内容や論理の矛盾
逆に、正しい選択肢は、“ぴったり当てはまる数式の解”のように、スムーズに文脈にフィットするのです。
「高速輪島塗メソッド」で読む
輪島塗は下地を何度も塗って仕上げるのが特徴で、「高速輪島塗メソッド」とはPart 6の長文全体を二度読んで解答する方法です。
Part 6の文挿入問題は、パッセージ全体の流れをつかんだ上で、選択肢を空所に当てはめなくてはいけません。パッセージを丁寧に一度読むのではなく、輪島塗のように高速で全体を読んでから、問題を解きながらもう一度長文を読んで解いていく方が、間違いが減ります。
Part 6がビジネスで大切な理由
それほど長くないビジネスメールの言いたいことを理解できるかが問われる問題です。ちょうど漢字や敬語を間違えると、ビジネスにはふさわしくないと思われるように、ビジネスパーソンは接続詞や単語の理解したり、文の流れを把握したりできる必要があります。
TOEIC Part 7の解き方のコツ

Part 7は文書(長文)を読んで、内容に関する設問に答える問題です。
設問の動詞から、解きやすい問題かどうかを見極める!
TOEICのPart 7では、設問文に使われている動詞に注目することで、「すぐに解ける問題」か「時間がかかる問題」かを見分けられることがあります。
すぐに解ける問題
設問に以下のような動詞が使われている場合:
- indicate(~を示す)
- mention(~と述べる)
- state(~と述べる)
この場合は、「文書に明確に書かれている情報」が問われているので、比較的情報を見つけやすく、短時間で解けます。
時間がかかる問題
設問に以下のような表現が使われている場合:
- imply(~を暗示する)
- suggest(~を示唆する)
- infer(~を推測する)
- most likely(最も可能性が高い)
この場合は、文書に答えが明確に書かれていません。 解答には、少し飛躍した理解や推測が必要になるため、時間がかかる傾向があります。
こうした問題は、いったん飛ばして、時間が余ったときに戻って解くという戦略も有効です。設問の動詞を見て、効率よく時間配分をすることで、スコアアップにつながります。
「名探偵コナン」になる
犯人(問題作成者)は答えがすぐ分からないように巧みに工作しています。むしろ違う結論を出してくれる(間違える)ことを願っています。ミスリードされないように、文章の意味が分かるだけで満足しないようにしましょう。
「人間ChatGPT」になる! 自分を「Google化」する
できるだけ最速で答えを見つけ出す力を身につけたいなら、「自分はChatGPTのように即座に答えを出すんだ」とか「自分の頭がGoogleの検索エンジンのようになっている」と考えることで、思考のスピードを上げるよう「意識」できます。
つまり、自分を「人間ChatGPT」や「思考版Google」と考えることで、時間短縮と効率アップにつながります。
「悪魔の証明」を試みない!
「悪魔の証明」とは、何かが存在しないのを証明することですが、その証明は困難とされます。Part 7には、選択肢を長文と照らし合わせて解く問題があります。例えば、「このメールの目的は何か?」という設問はこのタイプです。このタイプでは、選択肢一つ一つが「パッセージに書かれていないこと」を確認する作業をやってはいけません。長文にズバリ書かれている選択肢をまず探す「ズバリ法」で解くのが鉄則です。「ないことを証明する」のではなく、「あることを確認する」意識で取り組みましょう。どうしても迷った場合は、いったん飛ばして、時間が余ったときに見直すようにすれば、時間の浪費を防ぐことができます。
「当事者リーディング」を心掛ける
手紙やメールが出題された場合、自分に宛てられたものだと思えば、内容に集中しやすくなります。さらに、選択肢と本文を何度も往復する必要はなくなります。
数字を記憶する
数字を短期記憶できるようにしておくと、本文と選択肢を何度も確認する必要がなくなります。ちなみに私は1から100までを、自分がすぐ記憶しやすいようなイメージにしていますが、自分なりに作っておくと意外と本番で役立つはずです。
例えば、
- 1 ロウソク(数字の形から)
- 2 白鳥(数字の形から)
- 3 ツリー(木)(threeとtreeを掛けています)
- 4 ヨット (数字の形から)
- 5 五本指
パッセージに出てくる数字を自分がピンとくるイメージで覚えておくと、パッセージと選択肢をいちいち照合する必要がなくなり、時間の大幅な節約になります。ちなみに、5を「碁(囲碁)」として覚えるなど、自分にとって印象に残りやすいイメージを使えばOKです。こうした「仕込み」は、情報に対する感度や、記憶の定着力を高め、解答スピードを確実に上げてくれます。私自身、この方法を使うようになってから、本文と選択肢を見返す回数が劇的に減りました。
最初の一文ざっと読み
長い手紙やメール文では、各段落の最初の一文をざっと読んで、全体の趣旨を理解するとよいでしょう。英語では、段落の最初の文に、最も言いたいことが書かれているので、最初の文だけを読んでいくと、どんな展開になるのか知ることができます。ちょうど遊園地に入ったらまず、全体の地図を見てどこに何があるかチェックしながら乗り物に乗るのと同じです。まずは全体をふかんする意識を持ちましょう。
慣れない名前の処理の仕方
最近のTOEICでは、VikramやRekhaのように、日本人にはなじみのない名前が出てくることがよくあります。発音のしにくい名前は覚えにくいものです。そういう名前が出てきたら、それぞれVさん、Rさんのように短縮して覚えるとよいでしょう。
難化傾向のTOEICへの対処法
Part 7では文書にはっきりと書いてない選択肢が正解になる問題があり、それに時間を使い過ぎてしまう人が多いです。こういった「間違ってはいない」という選択肢が正解になることも覚えておきましょう。逆に言うと、誤答の選択肢は必ずズレているか、書いていないかのどちらかです。
「To」と「From」の位置に注意! 送信者・受信者を正確に見極めよう
TOEICのメール問題では、最初に「誰が誰に送ったメールか」を把握することがとても重要です。そのためには、まず「To(宛先)」と「From(差出人)」の位置を確認しましょう。例えば、Yahooメールなどでは「From」が上、「To」が下に表示されるのが一般的で、チラッと見ただけで「上の人が下の人に送っている」と判断できます。しかし、TOEICの問題では、「To」と「From」の位置が統一されていないため、毎回どちらが送信者なのかを丁寧に確認する必要があります。
確認すべきポイント:
- 「From」のメールアドレスや名前を確認して、誰が送ったのかを特定する
- メール本文の最後の署名(サイン)を見て、「From」と同じ人物かどうかを照合する
- 「To」のアドレスが、本文冒頭の呼びかけ(Dear ○○,)に対応しているかをチェックする
この確認作業をしっかり行うことで、この人がこの人に、こういう目的でメールを書いているという、やりとりの全体像がつかめます。つまり、誰が誰に何を伝えようとしているのかという、問題の核心が見えやすくなるのです。
Part 7がビジネスで大切な理由
ビジネスでは大量の情報の中から、必要な情報を正確に読み取り、処理する力が問われます。例えば、社内外から大量のメールや報告書が送られてきても、圧倒されることなく、的確に内容を把握し、要点をつかむ必要があります。また、ビジネスでは「言い換え」や「意図をくみ取る力」が求められます。相手の発言や文章を言い換えて「つまり、こういうことですよね?」と確認したり、「あなたの意図はこうだと理解しています」と示したりする場面が多くあります。
Part 7では、そうした言い換え表現の理解力や、意図を読み取る力を試されるため、実践的な読解力を身につける、良いトレーニングとなります。
TOEICのテクニックを磨く! おすすめ教材
スコアアップのためのおすすめ教材を紹介します。
「Santaアルク」
TOEIC対策アプリ 。12問の診断テストでスコアの予測ができます。AIがユーザーに合った問題をお勧めしてくれる機能も。通勤・通学のスキマ時間にTOEIC対策ができて便利です。
『TOEIC L&Rテスト 直前の技術』(ロバートヒルキ)
各Partを攻略する技術が盛り込まれています。
『頂上制覇 TOEICテスト リーディングPart 7 究極の技術』
特にTOEIC研究家「あ~るさん」が書いた特別付録「Part 7これを確実に獲れ!」は大変参考になりました。メールのCCが解答の根拠になる、割引の種類が解答の根拠になるなど、TOEICならではの受験テクニックを学ぶことができます。
以下は拙著です。長文が読みにくいのは、もしかしたら関係代名詞がよく分かっていないからかもしれません。または単語の意味がしっかりつかめていないのかもしれません。
「関係代名詞がわかれば英文が読める」 Kindle版(Hiroki)
「読んだ瞬間 目からウロコの英単語学習法: 日本人のための英単語記憶法」 Kindle版(Hiroki)
まとめ
TOEICは各パートでビジネスに必要なスキルが問われる優れたテストです。その意図を理解すればテストの重要性が見えてきます。基本的な攻略テクニックを学んだ後は、大量の英文に触れることがスコア向上の鍵です。英文を読む量を増やすことで、設問の先読み力が身に付き、リスニング力も向上します。技術(how)から量(how much)へと、学習の軸を移すことが重要です。本番が一番読む日にならないよう、週に2日以上、同等以上に英文を読む習慣をつけましょう。
【Santaアルク】3分で英語力診断!
AIが弱点・伸びしろ・TOEICスコアを予測
- Santaアルクを使って学習しているユーザーは世界で1000万人以上!
- 20時間の学習で平均195点のスコアアップ実績
- AIがユーザーのTOEICスコア・弱点・伸びしろを診断し、個別最適化されたカリキュラムを提供