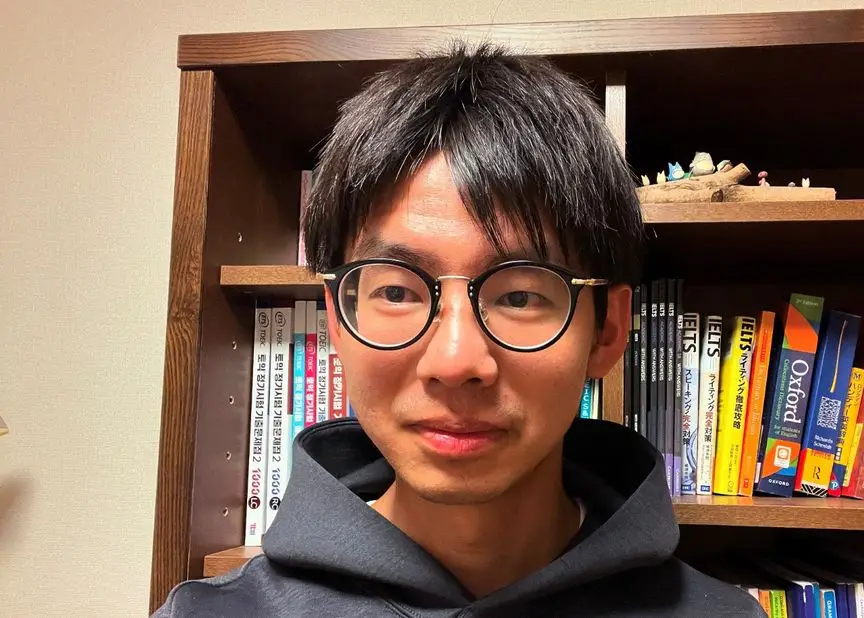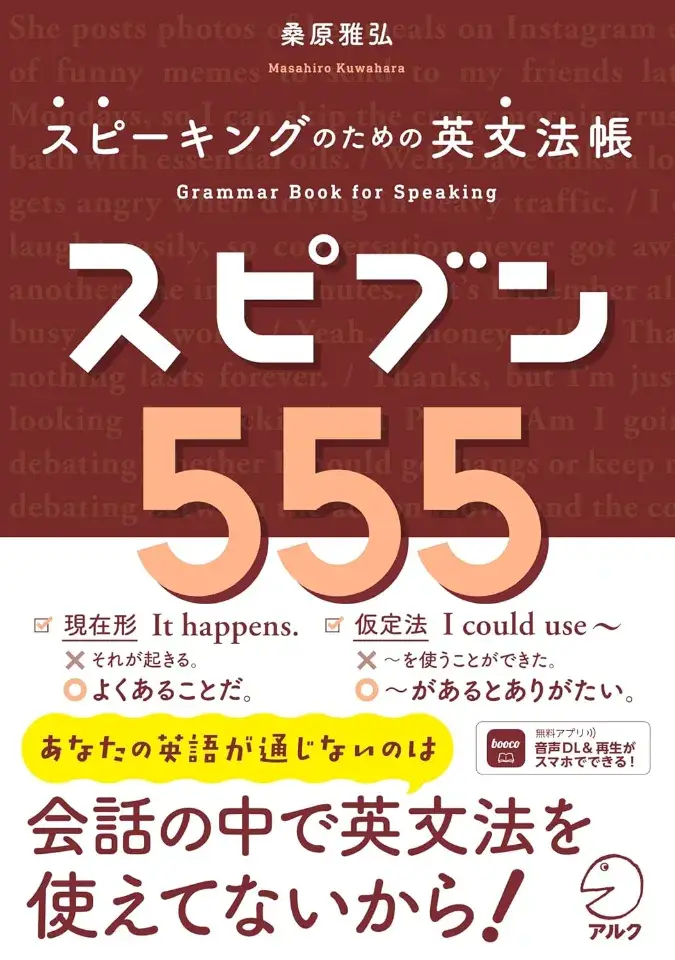TOEIC 990点・英検1級・国連英検特A級・ケンブリッジ英検CPEの資格を持ち、英語講師として活動する「とげまる」さん。今でも毎日欠かさず数時間の英語学習を続けるという英語への向き合い方や、「英語上級者」となるまでの具体的な勉強法に迫ります。日本人の多くが目指すものの、到達するのはかなり難しい「TOEIC満点=990点」という高い山の頂上。とげまるさんは一体どうやってたどり着いたのでしょうか。
目次
TOEIC満点への“英語の登山ルート”
皆さん、こんにちは。とげまるです。
今回からは3回にわたって、私がどのようにしてTOEIC L&Rテスト990点取得を取得したかについてお話しします。TOEIC満点は、私が初めてのぼった「英語の山」です。登山になぞらえて、どのように準備を整え、どんなルートを選び、どんな困難を乗り越えて頂上にたどり着いたのかを、順を追ってご紹介していきます。
【装備1:目標と動機】「どこを目指すのか」「なぜ、それをしたいのか」を明確に
よく言われることですが、目標と動機は何より重要です。「自分は何を目指すのか」「なぜ、それをしたいのか」を突き詰めて考え、挫折しそうになったらそこに立ち返る。私がここまで英語を続けてこられたのも、目標と動機があったからです。
前回お話しした通り、私が英語学習に真剣に取り組み始めたのは2015年3月、大学2年生の終わりのことです。大学で英文科を選ぶくらいなので、英語はもちろん嫌いではなかったのですが、当時はまったく勉強していませんでした。
理由の1つは、大学受験で燃え尽きてしまったこと。福岡の高校から祖父の出身校である東京の大学に行こうと決めたのは高校3年になってからで、受験勉強のスタートがかなり遅かったのですが、(後述する方法で)英語で大幅に巻き返して合格することができました。ところがそれで満足してしまい、それ以上英語を学ぼうという気が起きなかったのです。
理由のもう1つは、大学1年生のときにいじめに遭い、不登校になったこと。大学の英文科は女子学生が圧倒的に多かったので、田舎の男子校育ちだった私は、都会の女子だらけの教室でどう振る舞っていいか分からず、つい挙動不審になってしまうことがありました。居場所を作ろうと入ったミュージカルのサークルでも「コミュ障」などとからかわれて孤立するように。生活環境が大きく変わったストレスも加わって、完全に引きこもるようになりました。
人生を変えてくれた一筋の光
授業にも出ず、単位はギリギリ。進級も危ういということが、大学から送られた履修状況報告で親に知られてしまったのです。とても心配され、大学のキャンパス・ソーシャルワーカーに相談をするように言われました。学費を出してくれている親への申し訳なさもあり、大学2年次には頑張って朝から晩まで授業を受け、言われた通り、大学のカウンセリングルームに通うようになりました。
ある日、お世話になっていたソーシャルワーカーの先生の手伝いで、短い英文を訳す機会がありました(その先生が受け持っていた他の学生の課題だったと思います)。
そして、その訳を見た先生が、「君は英語ができるんだね。TOEICを受けてみれば?自信につながると思うよ」と言ってくださったのです。先生は何気なく口にしただけかもしれませんが、私にとっては一筋の光のような言葉でした。
それなら、英語をもっと真剣にやってみよう。英語を極めて、周囲に何を言われても負けない自分になろう。そう思いました。
当時の英語力は英検2級、TOEIC(IPテスト)405点で、お世辞にも「英語ができる」というレベルではありません。そこで、まずは英検準1級と、英検準1級レベルに相当するTOEIC700点を目標にしました。
正直に言うと、クラスに英検準1級保持者がいなかったので、「合格して周りに差を付けたい」という気持ちもありました。今ではもちろん「勉強は誰かと競うためにするものではない」と分かっていますが、元来負けず嫌いな私の最初の素直な動機は、「見返したい」という強い思いでした。
【装備2:少数精鋭の教材】数ではなく、相性と使い方が重要
TOEIC700点を目指すにあたり、私が使った参考書は以下の3冊のみです。
1.『新TOEIC TEST 出る順で学ぶボキャブラリー990』
通称「出るボ」ですね。基礎的な語句が網羅されていています。大学生協で中身を見て、自分はこのレベルから積み上げるべきだと直感して購入しました。そして、それが大正解でした。
著者の神崎正哉先生のブログを読み、先生がTOEICの試験日に放送していたネットラジオも愛聴するようになりました。TOEICに関する知識が得られたと同時に、著名な先生方が英語について生き生きと話しているのを聞いて、「自分もこんなふうになりたい」とあこがれを持ちました(それが今の仕事につながっています)。
2.『TOEIC L & R TEST 出る単特急 金のフレーズ』
定番中の定番、「金フレ」。これは英文科のクラスメートが使っていたのを見て購入しました。良いと言われているものには理由があるので、一度は手に取って自分に合うかを確かめてみるのがいいと思います。
3.『TOEIC 公式問題集』
公式問題集は試験形式になじむためにも必須――とはいえ、大学生には高額だったので、当時の最新刊を1冊だけ購入。次々と新しいものが出ますが、取り組み方を工夫すれば1冊で十分だと思います。(※編集部注:上記のリンクには、2025年4月末時点で最新の公式問題集を掲載しています。当時のとげまるさんが実際に購入したものとは異なりますのでご了承ください)
【ルート選び】達人の「学習法」を自分に合うようにアレンジする
勉強に当たってはやみくもに自己流で進むのではなく、先に山を踏破した達人の「ルート」、すなわち勉強法を大いに参考にしました。
1.高校の同級生の「リスニング上達法」
お手本の1人は高校時代の友人です。彼は予備校の全国模試で英語の偏差値75をたたき出す猛者。その勉強法は主に、リスニング試験の問題文をディクテーション(書き起こし)するというものです。
彼は、センター試験(現:大学入学共通テスト)のリスニング試験の音声を0.8倍速でディクテーションしてから、等倍 → 1.2倍速 → 1.5倍速と速度を上げてリスニングする練習をしていました。
当時の私にはディクテーションは少し難しかったので、彼の練習法をシャドーイング(音声を聞き、少し遅れて発音をすること)にアレンジして行いました。それで英語の点数がぐっと伸びて大学に合格することができたのです。
そうして、TOEICでもこれを応用し、以下のやり方で進めました。
- 公式問題集のリスニング問題(主にPart 3、4)を普通に解き、解説を読む
- 遅めのスピードで音声を再生し、5回シャドーイングする
- 等倍のスピードで音声を再生し、スクリプトを見ずに聞き取る
- 1.2倍のスピードで音声を再生し、スクリプトを見ずに聞き取る
- 1.5倍のスピードで音声を再生し、スクリプトを見ずに聞き取る
- 等倍のスピードで音声を再生し、5回シャドーイングする
また、リーディング対策でも同様に音読を取り入れました。ただ聞く・読むのではなく能動的に口を動かすことが、自分には合っていたのだと思います。
2.ATSUさんの「単語暗記法」
もう1人のお手本がYouTuberのATSUさんです。ATSUさんの動画は大学のクラスメートの間で評判になっていました。特に内容がとても腑に落ちて、自分の学習に取り入れたのがこの動画です。
ATSUさんの方法をシンプルに言うと、「一度で覚えようとせず、最初はスピード重視で全体像をざっくりつかんでから、何度も周回して覚えていく」というもの。
そこで私は、上述の「出るボ」を使い、次のように学習を進めました。
- 1日で覚える単語を100個と決める
- 紙に単語と日本語訳を5回ずつ書き、声に出しながら覚える
- 寝る前にその日やった単語のリストを見直し、日本語訳を赤シートで隠して瞬時に言えるかどうかを確認する
- 言えなかった単語はもう一度書いて覚え直し、次の日の朝に改めて確認する
この方法で進めると、「出るボ」(掲載語数:990語)は10日で1周できるので、受験日までひたすら繰り返しました。
「金フレ」も並行して、同じ方法で進めました。「金フレ」は、600点レベル、730点レベル、860点レベル、990点レベルとスコアごとのレベルに分かれています。私はこの時700点を目指していたので、730点レベルまでを完璧にすることを目標として1日50語ずつ進めました。

(※Amazonの「金フレ」販売ページで紹介されている
目次画像を、編集部で抜粋して掲載)
3. ATSUさんの「学習ルーティン」
私はXの投稿でほぼ毎日、1日の始めに「学習宣言」をし、1日の終わりに「学習時間の報告」をしています。

挙げた計画を実際に実行できたかどうかを、「学習時間の
報告」(右)の中で○×を付けて伝えています。これまでの
学習時間や時間配分などが一目で分かる画像付き。
フォロワーの方に「こんなに長時間どうして勉強できるの?」とよく聞かれますが、これもATSUさんのブログを参考にして確立した習慣です。ATSUさんは動画にもしてくださっていました。
ATSUさんは、英語力向上には勉強の質もさることながら「絶対量」も不可欠で、長時間自然に勉強できる体制を整えることが大事だ、と主張されています。特に「計画を立てること」の効果は絶大で、1日の学習内容やスケジュールを具体的に計画することで、集中力を維持しながら長く学習を続けることができるようになりました。
休憩+移動というルーティンを体に定着させる
また、4時間ごとに休憩を取る、場所を変えるというTipsも私には有効で、適度に休みを挟みながら、「朝は図書館で単語、昼は学食でリスニング、夜はマック(スタバは高かった!)でリーディング」といったように、移動しながら勉強していました。実は今でも家で勉強するのは苦手で、朝と晩にカフェで勉強しているんです(最近のお気に入りはミスド)。
一度習慣化してしまえば苦にはならず、むしろやらないと気持ち悪くなります。社会人の方が12時間を確保するのはかなり難しいことだと思うのですが、1時間でも30分でも、「今日はこれをやる」と計画し、決めた時間は必ずそれに取り組むというルーティンを、まずは1週間でいいので続けてみてください。きっと変わるはずです。
こうした学習を続けて、2015年9月に初めてTOEIC公開テストを受験しました。650点くらいを予想していたところ、結果は730点。いきなり目標の700点を超えられたことはとてもうれしかったです。ただ、その1カ月後の英検準1級一次試験は、合格点に4点足りず不合格に・・・。力を入れていたので、かなりショックでした。
次回は、その英検準1級へのリベンジと、TOEIC730点から990点を取得するまでの道のりについてお話ししたいと思います。