
時代を経て読み継がれる文学の名作には、「今」を生きるためのヒントやテーマが潜んでいます。この連載「現代的な視点で読み解く アクチュアルな英語文学」では、英文学と医学史がご専門の上智大学教授である小川公代さんが、主に18世紀以降のイギリス文学から今日的な課題を探ります。第5回で取り上げるのは、 コロナ禍以降に注目されている、メアリー・シェリーの小説『最後の人間』 です。作者の 自伝的要素と、帝国主義時代の人種差別に対する「罪悪感」、そして感染症の関係 はどんなものなのでしょうか?
コロナ禍で注目されるシェリーの『最後の人間』
新型コロナウイルス感染症のパンデミックが始まってから、メアリー・シェリー(Mary Shelley、1797-1851年)の『最後の人間』(原題:The Last Man、1826年) *1 が感染症文学の一つとして特集などでしばしば取り上げられている。
ダニエル・デフォーの『ペストの記憶』やブラーム・ストーカーの『吸血鬼ドラキュラ』といった多くの感染症文学は、感染症というものを善悪二元論で捉えれば差別やナショナリズムに帰着する 可能性 をはらみ、逆に社会共通の困難として捉えれば連帯が促されることを示唆している。
シェリーの『最後の人間』も、アルベール・カミュの『ペスト』と並んで、疫病と人々の連帯を語る上で重要な作品の一つに数えられるだろう。興味深いのは、奴隷制廃止運動が盛んになっていたシェリーの時代には、疫病と奴隷制、あるいは人種差別に対するヨーロッパ人の罪悪感は深く結び付いていたということだ。
疫病がまん延する世界での「連帯」を描く未来小説
2073年のイギリスを舞台として始まる『最後の人間』は、主人公のライオネル・ヴァーニーという語り手が地球上の最後の一人になるというアポカリプス(黙示録)的物語である。
ライオネルは落ちぶれた貴族階級の孤児として育つ。無法主義的であったが、貴族のエイドリアンやレイモンド卿と知り合い、さまざまなことを学んでいく。そんな折、トルコで戦争が勃発し、にわかに疫病がはやり始める。
エイドリアンは、王政から共和制に移行する社会で、彼自身は王室の末裔(まつえい)である にもかかわらず 、共和制を支持する自由主義者として描かれている。ライオネルは、疫病の感染が広がる大陸をエイドリアンらと旅する過程で、彼との対話を通じて次第に「愛」や「連帯」の大切さについて考えるようになる。
ライオネルやエイドリアンらがパンデミックを生き延びようとする姿とともに、人々が疫病だけでなく戦争や教権主義といった災いに苦しめられる世界が描かれている。また、フランス革命の大義でもあった宗教が力を振るう教権主義への抵抗というテーマが物語に組み込まれている。パリでメソディストの集団が宗教の名の下に多くの女性を監禁している場面に遭遇したエイドリアンは、ライオネルとともに彼女らを救おうとする。
黒人との接触で感染する主人公
次々と人々が疫病に感染する中、ライオネルは物語の最後の方まで感染の 影響 を受けない。そのライオネルがとうとう感染するとき、その きっかけ となるのが黒人との接触である。
これは、ポストコロニアル研究の見地から『最後の人間』のテクスト 分析 が行われる場合は必ず取り上げられる場面である。衣服を半分しか着ていない「黒人」(negro)(暗に「奴隷」という意味も示す)がライオネルを抱擁することについて、アン・メローは、この場面は黒人の身体を拒否する文化に終わりを告げる、「共感」の象徴的な場面であると論じている(Mellor, p. 193)。
抱擁を「共感」の象徴と考えるメローとは異なり、ピーター・メルヴィルは、抱擁する事実は認めながらも、その直後にライオネルが黒人から自身の身体を引き離す場面があり、それを拒絶のジェスチャーであると解釈している(Melville, p. 835)。つまりメルヴィルは、この描写は黒人や他者に対する「分断」を示していると言う。
このように、『最後の人間』が人種差別的なのか、そうではないのか、メアリー・シェリー研究者の間で論争が繰り広げられてきた。しかし、シェリーの作品で言うと『フランケンシュタイン』以外の小説があまり読まれていないこともあって、この感染症文学における差別の問題はそれほど知られていない。
それでは、実際シェリーは、ライオネルと黒人との抱擁をどのように描きたかったのだろうか。
シェリーの「罪悪感」が投影された自伝的要素
共和制を支持し、圧政を批判する自由主義者として描かれるエイドリアンは明らかに、メアリーの夫であった詩人パーシー・B・シェリーが理想化された姿であり、かなり伝記色の強い小説であることがわかる。
このことから、主人公ライオネルもおそらくシェリー自身であると推測できる。自分だけが生き残ってしまったというライオネルの罪悪感は小説のあちこちから見て取れるが、これは実は、シェリー自身の罪悪感とも結び付く。
例えば、シェリーは自身が生んだ一人目の娘に「クララ」、三人目の娘に「クララ・エヴリーナ」という名前を付けていたが、二人とも1歳未満で亡くなっている。この小説の最後にも「クララ」という名前の子どもが登場し、まるで自身の娘たちの喪に服すかのようにその「クララ」という名の子どもの死を再現している。なぜクララは亡くなってしまったのか、なぜ自分は生き残ったのかという悲痛な思いがこの小説を貫いている。
それでは、シェリーはなぜライオネルの感染源として黒人を登場させたのだろうか。
奴隷への人種差別に対する「罪悪感」
感染症と帝国主義時代の「罪悪感」(guilt)の関係についてはすでに重要な研究がある。
デビー・リーによれば、1790年代にはすでに奴隷廃止運動が盛り上がりを見せ、植民地では黒人奴隷たちの反乱が勃発していた。イングランド人たちがようやくアフリカの奴隷を道徳感情の対象となるにふさわしい人間として見なすようになったこの大きな感情の変化を、リーは「モラルの逆転」と呼んだ。それによって、突如として人々の中に罪の意識が生まれたのだ。例えば、「黄熱」(yellow fever)という当時流行していた病に「黒吐病」(black vomit)という異名が付けられたように、ロマン主義詩人や作家たちはすでに、この感染症をヨーロッパ人による奴隷貿易の罪の代償として背負わされたものと考えていた(Lee, p. 684)。
「モラルの逆転」が起こった時代とは、 すなわち ヨーロッパの白人たちから見て「他者」であった奴隷を巡る言説が変容した時代である。
その象徴的な詩が、同時代詩人サミュエル・テイラー・コールリッジによって書かれていた、「老水夫の歌」である。老水夫が航海中にアホウ鳥を打ち落とすと、突如として気象に変化が起き、風が吹かなくなる。老水夫の罪の意識とあがないが象徴的に表されるのが「十字架の代わりに、アホウ鳥がわしの首につるされた」(コールリッジ、p. 284、ll. 141-142)という場面だ。その後、船員全員の死がもたらされても、その死と老水夫による鳥の殺害との間に因果関係があるの かどうか 、最後まで宙づりのままである。ハリー・ホワイトは、コールリッジが老水夫の苦しみや罪の意識を詩に表したのは、コールリッジ自身が抱えていた不安感、あるいは罪の意識にも何かしらの 原因 があると思っていたからだと論じている(White, p. 816)。それはリーによれば、ヨーロッパ人の帝国主義的な暴力であるというのだ。
シェリーが『フランケンシュタイン』にも「老水夫の歌」を引用していることを踏まえれば、彼女が奴隷への共感を同じ文脈に挿入していたことは至極当然のことだろう。また、コールリッジはシェリーの父ウィリアム・ゴドウィンの古くからの友人で、彼女がまだ幼かった頃にたびたび家を訪ねてきていた。そして、コールリッジが「老水夫の歌」をそらんじるのを聞きたいばかりに、彼女は就寝時間になってもソファーの影に隠れていたというエピソードもある。
病原体発見以前の感染症の捉え方
シェリーが生きたロマン主義時代は、感染症研究の開祖ロベルト・コッホが、細菌が病原体であると発見する(1882年)以前である。つまり、19世紀前半頃までの医学の実践においては、感染症が臭気や発散物の吸収によってうつるという説が支配的で、例えば次のような言葉からも、疫病の感染経路が「空気」であるという考え方が主流であったことがわかるだろう。
マラリア(malaria):「悪い空気・悪魔の空気(bad air)」が語源。
ミアズマの時代には、疫病がまだまだ「呪い」、あるいは罪悪感のしるしとして捉えられる時代だったが、シェリー自身もそういう考え方から逃れられていない。
大切な人を奪った感染症への感情
コールリッジがアホウ鳥に罪悪感を象徴させたように、シェリーもまた、生き残ってしまったライオネルの姿に自分を重ね合わせた。なぜこれほどの罪悪感が小説に刻まれることになったのか。また、それはなぜ感染症の物語として表されたのだろうか。
シェリーは実子「クララ」のほかに、実母を感染症で失っている。母親のメアリー・ウルストンクラフトは、シェリーを産んで10日後に産褥(さんじょく)熱で亡くなった。シェリーはしばしば母親の墓地を訪れ、そこで読書をしたりした。自分を出産していなければ、死ななかったであろう生命に思いをはせていたのだろう。実は、クララも感染症(赤痢)で亡くなっている。
シェリーの大切な人の命を次々と奪っていった病はいずれも 原因 が不可視である。彼女にとって、感染症は脳裏を離れない類いの病であっただろう。
シェリー夫妻がスイスを訪れた際に滞在したのはバイロン卿のディオダティ荘であった。この場所で幽霊談義を語り合った詩人のバイロン卿もギリシャ独立戦争に参加して、36歳で熱病にかかって亡くなっている。『最後の人間』においては、ライオネル(メアリ・シェリー)とエイドリアン(パーシー・シェリー)の友人であるレイモンド卿のモデルは明らかにバイロン卿である。
感染症文学『最後の人間』に「救い」はあるか?
それでは、この小説には「救い」はないのだろうか。筆者はあると考えている。
黒人から感染したライオネルの病状は、一度は悪化するが、妻イドリス(エイドリアンの妹)の手厚い看護のおかげで、奇跡的に助かる。そしてこの場面に描かれるのは、「分断」ではなく、感染者を差別しない「連帯」によって危機を乗り越えようとする反差別主義の態度である。三日三晩イドリスは片時もライオネルのそばから離れなかった。しかし、その代償として、看護をしている最中に感染し、亡くなってしまう。
生き残ったライオネルは以前にも増して生命力がみなぎっており、「私の生命の歯車やバネが、また再び生の運動が開始され、体のしなやかさを取り戻した」(Shelley, p. 343、日本語訳は筆者による)という言葉からもわかるように、ある意味で、 『フランケンシュタイン』 のクリーチャーの蘇生のようにも表現されている。ヴィクター・フランケンシュタインが「科学」の力で生み出した被造物の物語が、数年後に手掛けた『最後の人間』という作品では、「愛」の力で蘇生させたライオネルが生き残る物語になっている。その点で、生命の誕生の物語の再話とも解釈できる。
あまりに伝記的なこの作品が読者に「シェリー家の悲劇」であると意識されないように、舞台をはるかかなた未来に移したのではないだろうか。メアリー・シェリーは、パーシー・シェリーやバイロン卿らと語り合った理想の未来を、『最後の人間』というフィクションに託したかったの かもしれない 。
カミュの『ペスト』で主人公の医師リウーが新聞記者ランベールと対話する場面は、ライオネルとエイドリアンの信頼関係を彷彿(ほうふつ)とさせる(カミュが『最後の人間』を読んだの かどうか は不明だが)。ランベールは隔離されているオランの町から、「恋人が待っているから」と逃げようとする。だが、最終的にリウーと対話を重ねることで、自分さえよければいいという考えを捨て、町に踏みとどまり、リウーたちと連帯していく。
シェリーの『最後の人間』でも、困難に直面する人たちを助けるエイドリアンがライオネルやイドリスに 影響 を及ぼすことで、ライオネルが最後まで生き延びることができたとも言える。黒人とライオネルの抱擁はやはり「共感」の象徴ではないだろうか。
デフォーの『ペストの記憶』にも、蛮勇を奮って、感染した人を療養所に搬送したり、死者を墓場に運んだりしたジョン・ヘイワードという人物が登場する。1817年に『ペストの記憶』を読んだシェリーは、この作品からインスピレーションを得たのかもれない。
「連帯」というテーマを強く押し出したシェリーの感染症文学は、今のコロナ禍のなかで生き延びようとする私たちにその大切さを教えてくれる。
次回は2021年3月5日に公開予定です。
文学を通じて英語力を強化したい人におススメの参考書はこちら!

参考文献
■S・T・コールリッジ「老水夫の歌」、『S.T.コールリッジ 詩歌集(全)』野上憲男訳(大阪教育図書、2013年)
■ブラーム・ストーカー『吸血鬼 ドラキュラ』菊地秀行訳(講談社文庫、2014年)
■ダニエル・デフォー『ペストの記憶』武田将明訳(研究社、2017年)

- 作者: Shelley, Mary Wollstonecraft
- 発売日: 2008/10/15
- メディア: ペーパーバック
■Anne Mellor, “Frankenstein, Racial Science, and the ‘Yellow Peril ,’” Romantic Science: The Literary Forms of Natural History (Albany: State University of New York Press, 2003)
■Peter Melville, “The Problem of Immunity in The Last Man,” SEL Studies in English Literature 1500-1900, Vol. 47, No . 4 (Johns Hopkins University Press, Autumn, 2007)
■Harry White, “Coleridge’s Uncertain Agony ,” SEL Studies in English Literature 1500-1900, Vol. 49, No . 4 (Johns Hopkins University Press, Autumn, 2009)
こちらもおすすめ
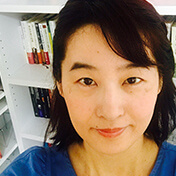
小川公代(おがわ きみよ) 上智大学外国語学部教授。英国ケンブリッジ大学卒業(政治社会学専攻)。英国グラスゴー大学博士号取得(英文学専攻)。専門は、イギリスを中心とする近代小説。共(編)著に『 幻想と怪奇の英文学IV 』(春風社、2020年)、『 Johnson in Japan 』(Bucknell University Press, 2020)、『 文学とアダプテーション――ヨーロッパの文化的変容 』(春風社、2017年)、『 ジェイン・オースティン研究の今 』(彩流社、2017年)、『 文学理論をひらく 』(北樹出版、2014年)、『 イギリス文学入門 』(三修社、2014年)など。
https://sites.google.com/view/ogawa-kimiyo
boocoで読める!アルクの新刊、続々登場
語学アプリ「booco」なら、アルクのベストセラー書籍200タイトル以上が、学習し放題!
「キクタン」などアルクの人気書籍800冊以上が音声対応。「読む」に対応した書籍では、本文と音声をスマホで手軽に利用できるほか、一部の書籍では、学習定着をサポートするクイズ機能で日々の復習や力試しも可能です。さらに、Plusプランに加入すれば200冊以上の書籍が学習し放題に!
boocoの「読む」機能では、次のような使い方ができます。
① 学習したいページを見ながら音声を再生できる
② 文字サイズや画面の明るさを調整できる
③ 書籍内検索ができる
※ これらの機能には一部の書籍が対応しています。

▼「booco」の無料ダウンロードはこちらから


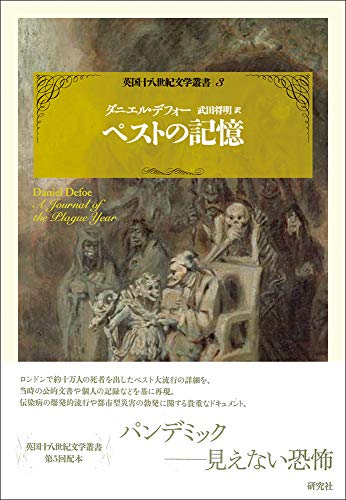




![『スピーキングのための英文法帳 スピブン555』[音声DL付]](https://image-ej.alc.co.jp/images/GamGSrTWRko6iAR2V9kR.webp)
