
時代を経て読み継がれる文学の名作には、「今」を生きるためのヒントやテーマが潜んでいます。この連載「現代的な視点で読み解く アクチュアルな英語文学」では、英文学と医学史がご専門の上智大学教授である小川公代さんが、主に18世紀以降のイギリス文学から今日的な課題を探ります。第4回は、 オスカー・ワイルドの『ドリアン・グレイの肖像』にみられる同性愛的描写や登場人物のモデルとされる人物、ワイルドのシェイクスピアへの関心 についてです。
シェイクスピアの銅像の除幕式
1888年10月10日にストラトフォード・アポン・エイヴォンで、ある銅像の除幕式が行われた。その式典に、銅像の制作者ロナルド・ガウアー(Lord Ronald Gower、1845-1916年)とともに姿を現したのがオスカー・ワイルド(Oscar Wilde、1854-1900年)であったことはあまり知られていない。しかも、この2人には興味深い共通点があった。
ストラトフォードは、シェイクスピアの生家があることで世界的に有名な町だが、ワイルドとガウアーは、この街を流れるエイヴォン川沿いにある公園、バンクロフト・ガーデンに建つシェイクスピアの銅像の除幕式に出席し、スピーチをしている。中心で見下ろすような位置に設置されたのがシェイクスピア自身の銅像で、その周りをシェイクスピアが生み出した4人のキャラクター、ハムレット、フォルスタッフ、ハル王子、マクベス夫人の像が囲んでいる(これらの像は、哲学、喜劇、歴史、悲劇をそれぞれ表している)。


1888年のワイルドは34歳。のちにワイルドが名声を勝ち得る理由にもなる『真面目が肝心』や『ウィンダミア卿夫人の扇』といった戯曲はまだ一切書かれていない時期である。ワイルドは、1887年に雑誌『婦人世界』(The Woman’s World)の編集者に抜擢され、評論家としても頭角を表し始めてはいたが、どちらかといえば絵画やインテリアデザインの目利きとして知られていた。また1888年には、「幸福な王子」(原題:The Happy Prince)などの童話も刊行されている。一方、ガウアーは当時すでに43歳。芸術家として円熟さを増し、ライフワークとしてのシェイクスピアの銅像を完成させたところであった。
とはいえ、いずれ演劇の世界で才能を開花させ、美と芸術に情熱を注ぎ込んでゆくワイルドは、ガウアーとよく似ている。そればかりか、2人には19世紀のイギリス社会では公言できなかった秘密――つまり同性愛者だった――という共通点もあった。
オスカー・ワイルド事件
ワイルドとガウアーの運命を大きく分けたのが、この除幕式から7年後、つまり1895年の「オスカー・ワイルド事件」である。ワイルドが「著しいわいせつ行為」の有罪判決を受けてしまう事件だ。
驚くべきことに、ガウアーは政治家や芸術家として活躍するだけでなく、19世紀イギリスのLGBTQの歴史において中心的な人物であった にもかかわらず 、幾度ものスキャンダルをはねのけて、法的な制裁を受けずに済んでいた。英文学者のジョセフ・ブリストーによれば、ガウアーは同性愛者として知られていたが、富と社会的地位をうまく利用しながら、ワイルドが引き起こしてしまったような事態を回避し、晩年には若い恋人のフランク・ハード(Frank Hird、1873-1937年)を養子にするという法的 手続き を経て同居までしている *1 。
ワイルドはといえば、裁判沙汰に巻き込まれ、最終的には犯罪刑法改正条例第11条の罪で、2年間の過酷な重労働を伴う投獄に処せられた。 そもそも の発端は、彼の恋人であったアルフレッド・ダグラス卿(Lord Alfred Douglas、1870-1945年)の父親クイーンズベリー侯爵が息子とワイルドの関係に気付き、「男色者らしきオスカー・ワイルドへ」と書いたカードを、彼の行きつけのクラブに残したことだった。ワイルドは、ダグラス卿にたきつけられて父親のクイーンズベリー侯爵を名誉毀損(きそん)で訴えたのだが、それがあだとなり、彼自身が同性愛行為の罪で告発されてしまったのだ *2 。
男女二元論が「普通/ノーマル」と考える「ヘテロノーマティヴ」という価値観が行き渡る社会では、性の「逸脱」と考えられる行為への社会的制裁がより大きい。ワイルドが逮捕された背景には、1885年の刑法改正法後に男同士の「親密な」関係が国家の徹底的な監視下に置かれ、同性愛者の権利が著しく損なわれていた歴史的状況があった。イギリスで男性間の同性愛行為が合法化される1967年までは、同性愛の男性は差別の対象となるだけでなく法的な処罰を受けたため、異性愛者でない人々は自身の性的指向をひた隠しにする必要があった。

『ドリアン・グレイの肖像』のヘンリー卿のモデル
ワイルドの同性愛が発覚する以前にも、彼の同性愛的 傾向 は作品にすでに色濃く表れていた。例えば、『ドリアン・グレイの肖像』(原題:The Picture of Dorian Gray、1890年)には、同性愛を示唆するとみなされた言葉が使われていた。しかし、先述したとおり、19世紀における性規範の縛りはあまりに厳しかった。アメリカの月刊誌『リピンコッツ・マンスリー・マガジン』のエージェントであったジョセフ・マーシャル・ストッダートが編集した1890年版は同性愛を示唆する言葉は排除せずそのまま掲載していたが、1891年版では削除されている *3 。例えば、主人公ドリアンの美しさに魅せられた男性画家バジルは彼を毎日「崇拝する」( worship )と、友人で快楽主義者のヘンリー・ウォットン卿に語っているが、その会話は1891年には検閲対象となっている。
興味深いのは、シェイクスピアの彫像を制作したガウアーこそ、実はワイルドの『ドリアン・グレイの肖像』に登場するヘンリー・ウォットン卿のモデルとなった人物であったということだ。ガウアーと面識のあるブルームズベリー・グループのロジャー・フライ(Roger Fry、1866-1934年)によれば、彼には小説に登場するヘンリー卿をほうふつとさせる点がいくつもあった。例えば、フライはガウアーのことを「堕落によってゆがめられていない完璧なまでの貴族的な顔」が特徴的で、「完璧なまでに礼儀正しく、くつろいだ印象の愛想のよい人物、 ただし 少し無関心過ぎ」なところもあり、「ギリシャの彫刻についてよく語っていた」と友人に宛てた手紙につづっている *4 。
ワイルドとガウアーの関係
ワイルドとガウアーの接点はシェイクスピアの銅像の除幕式よりずっと前の1876年までさかのぼる。ワイルドが弱冠22歳だった頃、35歳のガウアーはワイルドの友人を介して彼に出会っていた。女性の肖像画で有名になった画家フランク・マイルズ(Frank Miles、1852-91年)はワイルドのオックスフォード大学時代の友人で、しかもアパートの同居人でもあった。マイルズに会いに訪ねてきたガウアーはワイルドとも話をしており、そのことを日記につづっている。そのときのガウアーの印象では、ワイルドは陽気な青年だったが、髪は長く、ローマ・カトリック教の話には辟易(へきえき)したという *5 。
1888年の除幕式でスピーチをしたワイルドは、ガウアーのように芸術家として名声を得てはおらず、どちらかといえば批評家としての評判しかなかった。年齢的にも社会的地位においても、明らかにワイルドが劣っており、当人がいくらか気後れしたとしてもおかしくない。
しかし、その関係性も1890年代には逆転する。ワイルドは『ドリアン・グレイの肖像』の耽美(たんび)的かつ退廃的な内容と機知に富んだ文体によって、英国の文壇にセンセーションを巻き起こした。また、パリで出版された『サロメ』(原題:Salome、1893年)が話題を呼び、1894年に出版された英訳版にはオーブリー・ビアズリーの挿画が使用され、さらに注目を集めた。その頃、『ドリアン・グレイの肖像』のヘンリー卿のモデルとなったガウアーは恋人のフランク・ハードとともに静かな生活を送るようになっていた。
ワイルドは、近代社会に最初に公然と現れた同性愛アーティストであり、今では性的マイノリティーの象徴的存在でもある。しかし、19世紀のイギリス社会はセクシュアリティーにあまりに厳格で、とりわけ同性愛嫌悪(homophobia)がひどかった。
ワイルドが敬愛したシェイクスピア
ワイルドは、童話や戯曲を書いたことは広く知られているが、実はシェイクスピアへの関心が強かったことはそれほど知られていない。ましてや、シェイクスピアの同性愛をテーマにした小説を書いていたことは研究者の間でもそれほど議論されてはいない。
彼の短編「W・H氏の肖像」は、シェイクスピアの元で演じたことのあるウィリー・ヒューズ(W・H)という少年俳優の物語である。少年でありながら女性の役を演じられる両性具有的な存在であるため「子どもと大人」や「男性と女性」を、俳優なので「現実と虚構」を、また時間を超越する存在として「過去と現在」を越境する登場人物である *6 。
男女二元論という性規範から逸脱することを許さないイギリス社会は同性愛者であったワイルドを弾劾した。その法廷の場で、ワイルドが言及した名前がシェイクスピアだったことはおそらく偶然ではないだろう。
ワイルドは、ヘテロノーマティヴな規範から逸脱するようなクィアな愛を弾劾されるべき愛としては認めず、来るべき新文化の曙光(しょこう)を暗示するものとして「名付け得ぬ愛」と表現した。次の引用は、ワイルドの法廷でダグラス卿への愛について弁明するスピーチである。
それ[男性同士の愛]は、深淵でスピリチュアルにつながり合う愛にして、純粋かつ完全。シェイクスピアにしろミケランジェロにしろ、偉大な芸術作品の決め手となったのはこの愛であり、作品の隅々にまでそれは浸透しています。しかし、今世紀ではそれはまったく理解されていません。だから、「名付け得ぬ愛」と表現されているのです *7 。おそらくこのスピーチでワイルドが想起していたのは、小説「W・H氏の肖像」で描き出したシェイクスピアの美しい若者への愛だったのだろう。そして、除幕式という華やかな場で、同性愛者としても認知されていたガウアーとともにシェイクスピアをたたえた記憶も呼び起こされたの かもしれない 。このワイルドの法廷でのスピーチは今でも人々に語り継がれるほど伝説的な逸話となった。ガウアーがシェイクスピアの形をとどめる視覚芸術の名手であったとしたなら、ワイルドは言葉の芸術を極めた芸術家だと言えるだろう。
※ワイルドのスピーチの 分析 については、『群像』2021年2月号(講談社)掲載の筆者による短期集中連作「ケアの倫理とエンパワメント」の第2回「オスカー・ワイルドの越境するケア」を参照している。
次回は2021年2月4日に公開予定です。お楽しみに。
参考文献
■Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray, 1847, ed. Robert Mighall (Penguin Classics, 2003)

- 作者: Wilde, Oscar
- 発売日: 2006/08/03
- メディア: Kindle版

- 作者:
![]() *1 :Joseph Bristow, “Oscar Wilde, Ronald Gower, and the Shakespeare Monument,” Etudes anglaises, Vol,69, Issue 1 (2016), p.21.
*1 :Joseph Bristow, “Oscar Wilde, Ronald Gower, and the Shakespeare Monument,” Etudes anglaises, Vol,69, Issue 1 (2016), p.21.*2 : https://victoriancommons.wordpress.com/2020/02/19/lord-ronald-gower-1845-1916-the-life-of-a-queer-mp-at-the-time-of-the-second-reform-act/
*3 : https://www.themorgan.org/collection/oscar-wilde/the-picture-of-dorian-gray/19
*4 :Roger Fry, Letters. Ed. Dnys Sutton, Vol. 1 (London: Chatto and Windus, 1972), p. 18.
*5 :Bristow, p.14.
*6 :大橋洋一「解説」『ゲイ短編小説集』(大橋洋一監訳、平凡社、2014年)、p. 364。
*7 :H. Montgomery Hyde, The Trials of Oscar Wilde (New York: Dover Publications, 1962), p. 201.
![]()
小川公代(おがわ きみよ) 上智大学外国語学部教授。英国ケンブリッジ大学卒業(政治社会学専攻)。英国グラスゴー大学博士号取得(英文学専攻)。専門は、イギリスを中心とする近代小説。共(編)著に『 幻想と怪奇の英文学IV 』(春風社、2020年)、『 Johnson in Japan 』(Bucknell University Press, 2020)、『 文学とアダプテーション――ヨーロッパの文化的変容 』(春風社、2017年)、『 ジェイン・オースティン研究の今 』(彩流社、2017年)、『 文学理論をひらく 』(北樹出版、2014年)、『 イギリス文学入門 』(三修社、2014年)など。
https://sites.google.com/view/ogawa-kimiyoboocoで読める!アルクの新刊、続々登場
語学アプリ「booco」なら、アルクのベストセラー書籍200タイトル以上が、学習し放題!
「キクタン」などアルクの人気書籍800冊以上が音声対応。「読む」に対応した書籍では、本文と音声をスマホで手軽に利用できるほか、一部の書籍では、学習定着をサポートするクイズ機能で日々の復習や力試しも可能です。さらに、Plusプランに加入すれば200冊以上の書籍が学習し放題に!
boocoの「読む」機能では、次のような使い方ができます。
① 学習したいページを見ながら音声を再生できる
② 文字サイズや画面の明るさを調整できる
③ 書籍内検索ができる
※ これらの機能には一部の書籍が対応しています。![]()
▼「booco」の無料ダウンロードはこちらから





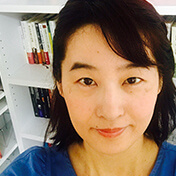





![『スピーキングのための英文法帳 スピブン555』[音声DL付]](https://image-ej.alc.co.jp/images/GamGSrTWRko6iAR2V9kR.webp)
