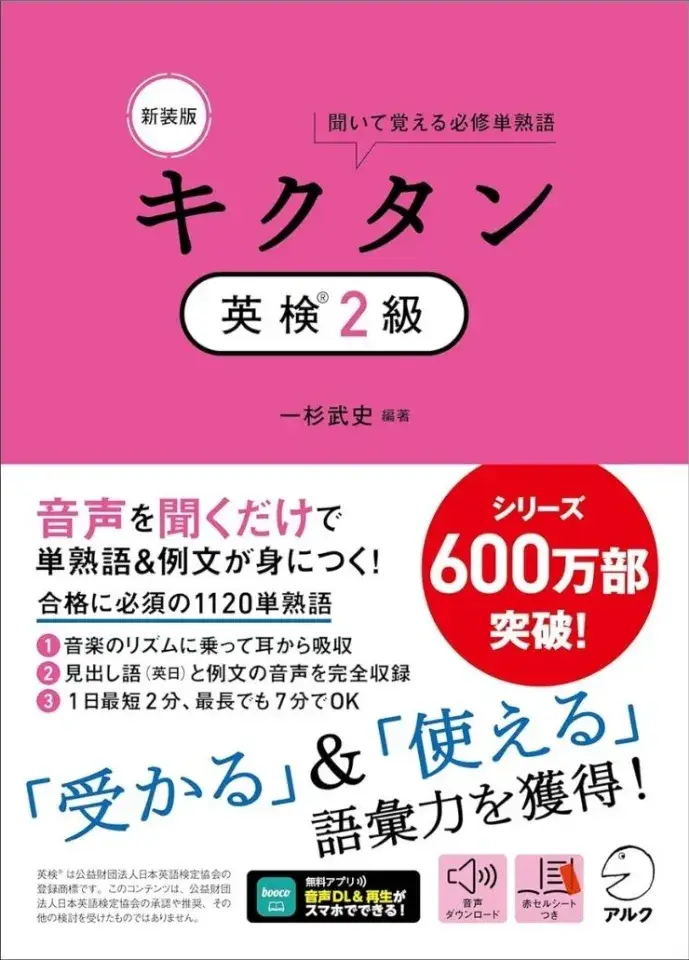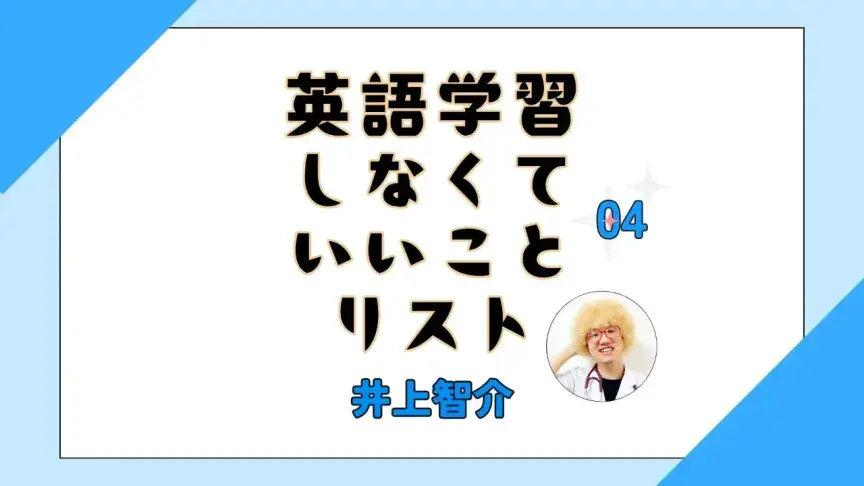
英語の勉強は、まず文法から?それとも会話から?シャドーイングとかディクテーションは?―― 情報だらけだからこそ、勉強法の“正解探し”は本当に難しい!精神科医の井上智介さんは、そうした「正解探しに振り回される」ことに気を付けて、と発信しています。
情報の波におぼれる時代
はい、どーも!もう第4回ですよ。この連載は全6回なので、折り返し地点を回った所です。いや〜早いですね!前回は、「コソ勉」についてお話ししましたね。今日もコソコソENGLISH JOURNALを読んでくれていますか?
さて、今回は英会話の勉強方法について語らせてください。そもそも、英会話がペラペラになるまでの方法って、ありそうで、なさそうで……あるんでしょうね、多分。実際にできる人がいるわけですからね。
でも、大人になってから「よし、英会話の勉強をしよう」と思って始めてみたら、ビックリしませんでした?シャドーイングとかオーバーラッピングとかディクテーションとかチャンクとか、受験英語ではあまり聞かない手法のオンパレード。さらに、勉強すればするほど「結局どの勉強法がいいんや!?」「どこから勉強したらいいねん!?」という迷路にはまり込みませんでした?
いい意味でも悪い意味でも、今は情報があふれ過ぎている時代です。「発音できない音は聞き取れません。だから発音から勉強しましょう」と言われることもあれば、「読めない英文は聞き取れません。なのでリーディングから勉強すべきです」という説もあります。しまいには「英会話に英文法は必要ありません!」とあおるキャッチコピーのそばに、「まずは中学レベルの英文法から始めよう!」と励ます本やYouTube動画があったり。もう真逆やん……。こんな風に、眉唾レベルも含め、さまざまな情報に触れることになりますよね。
「正解」通りにいかなくていい
その結果どうなるかというと、どんどん勉強法の迷子になる。それで今なお迷子センターにいるのが私です。え?「私も迷子センターにいる」って?やあやあ、仲間ですね!
そして、ここで朗報です……と言いたいところですが、そう単純にはいきません。
さて、あなたは「第二言語習得論」という言葉を聞いたことはあるでしょうか。あっ、「なんかすごそう」ってワクワクしてきました?これは私たち迷子を導く魔法の地図かもしれない、と……。
第二言語習得論をざっくり説明すると、「母語以外の言語を身につけるプロセスを、研究と理論で分かりやすく説明しようとする学問」です。

「その方法で勉強すれば間違いないんやな!」と思って猫ちゃんと同じ顔をした人もいることでしょう。―― そう、最初は「これで迷子から抜け出せるかも!」と思うんです。でも、そこで私みたいなひねくれ者の心がむくっと顔を出す。「うわ、出たよ」と。
第二言語習得論は世界中で研究されているアカデミックな分野で、エビデンスに基づいた学習法もたくさんあります。それなのになぜしっくり来ないのか……。
それは、自由が奪われた気がするから。理論や学習法が世の中で広がっていくと、「これこそが正解です」と主張されているようで、言い方を変えれば「これ以外は全て間違った方法です」とまで言われているような圧迫感を覚えてしまう。
健康の話でもよくあるじゃないですか。医者から「健康の秘訣を教えます」と言われて、それが「食事・運動・睡眠です!」だったとき、「分かっとるわ!!!」って心の中でツッコむやつ。あれと重なる部分もあります。
もちろん、正しい理論があるのはいいこと。勉強の道しるべとなり、迷子センターにいる我々に進むべき方向を示してくれるようなもの。でもね、自分の性格やペースに合わないと続かないんです。そもそも、勉強で一番大事なのは「続けること」ですよね。
勉強の「正解」は十人十色
第二言語習得論をベースにした学習方法がばっちりハマったのなら最高です。でも現実でそういうことは少なくて、むしろ、試してみたものの「いや、なんか違うな……」となることも少なくありません。そして、この「なんか違う」という感覚がめちゃくちゃ大事。その感覚を無視して、常に歯を食いしばって鬼の形相で勉強したとしても、果たして効果があるのでしょうか。
それに、第二言語習得論がまだ存在しない時代にもペラペラになれた人はいるでしょうし、全然違う方法で英会話の力を上達させた人もたくさんいるはず。だから、これが唯一の正解だと思い込まない方がいいと感じています。
そもそも、英語界隈ってのは新しいメソッドとか教材とか、次から次へと出てくるじゃないですか。しかも、ちょっとうさんくさいやつもかなり混ざっとる!(笑)でもそれらも、全部が全部ダメと決め付けるのではなく、自分に合えば取り入れたっていいんじゃないでしょうか。
第二言語習得論はアカデミックな響きだし、“これぞ正解”感もある。でも、それに振り回され過ぎるのはちょっと怖いなと思います。
最短・最速ばかりがいいとは限らない
旅行の話にたとえて一緒に考えてみましょう。大阪から東京へ行くとした場合、「一番早い移動手段は?」と聞かれたら、きっと大抵の人は「飛行機!」と答えるでしょう。
でも、「早い=正解」でしょうか。人によっては、それが一番心地いい方法とは限りません。「飛行機が怖い人」とか、「特有の圧迫感がダメな人」とかもいますよね。第二言語習得論は、この「飛行機」っぽい雰囲気だと感じます。
旅行の場合、新幹線や夜行バスのような選択肢を回答しようもんなら、「はい、情弱乙!」なんて空気に直面することも。「それは効率悪い方法です!」みたいに否定されると、「いや、“味”があるやん!」と反論したくなりませんか?
「学び続ける」原動力を生むもの
これは私の“超”偏見なんですが、夜行バスで長距離移動する人って、絶対インスタに「今から○○に向かいます!」写真をアップしてるでしょ?あれがポイント。飛行機の移動では味わえない、「どこか非日常の環境の中でワクワクしてる自分」が好きなわけです。そういう自分だけの日々をしっかり楽しんでいる、それって最高じゃないですか。
第二言語習得理論には、「遊び」や「寄り道」といった楽しさから遠ざかっていく、そんな側面もある気がします。そりゃね、目的が「東京に最速で着くこと」なら、飛行機が正解なのも分かりますよ。だけど、人生はそんな単純ではないですから。到着するまでのプロセスが楽しかったり、寄り道にこそ特別なエピソードが生まれたりするものです。
「これこそが正解」と声を大にして言われても、「いや、自分は夜行バスの雰囲気が好きやねん!」と思っていい。好きな方法やペースで「英語の勉強の旅」を楽しんでいいんです。

夜行バスは、目的地に着く頃には体バキバキになるし、隣の人のいびきがすごいなんて可能性もあります。でも、そういうのは全部ネタになるし、思い出にもなるでしょ?そして、「全然寝られなかったけど東京に着きました!」みたいな、「私、頑張ってます!」アピール写真をインスタに上げる自分を好きでいいじゃないですか。結局、そういう「自分が興奮できるストーリー」こそが、学びを続ける原動力を生むからです。
「自分に合わない」なら無理しなくていい
もしかしたらこの先、第二言語習得論そのものをはるかに凌駕するような、リニアモーターカー並みに超特急の学習法が出てくるかもしれません。でも、それに振り回されることなく、自分のワクワクやドキドキを大切にして楽しく学んでいけたら、結局はそれが一番。
もちろん、時には歯を食いしばって頑張らなきゃいけない日もあると思います。でも、方法や理論に縛られ、自由を失って立てずに苦しくなるのは本末転倒。
だからね、どうか巷にあふれる「あの方法が正しい!」「効率がいいのはこっち!」という言葉に振り回されないでください。ノウハウばかり探し求めて時間を奪われた結果、肝心の「英語を勉強する時間」が減ってしまったら意味ないですもん。
あなたは、あなたのペースで、今日も前に進む。それだけで、本当にすごいことです。大事なのは、うまくやることよりも、諦めずに続けること。面白味を感じなければ続かないし、しんどいだけだと心がついてこない。だからもっと自分の心に正直でいてください。
ワクワクしながら自分らしく進んでいけたら、きっとそれが一番の近道になるはずです!
井上智介先生の最新著書はコチラ!
(1) 『みんなのネガティブ感情のおてあて』
(2) 『「考えなくていいこと」リスト:心がスーッと軽くなる49のヒント』
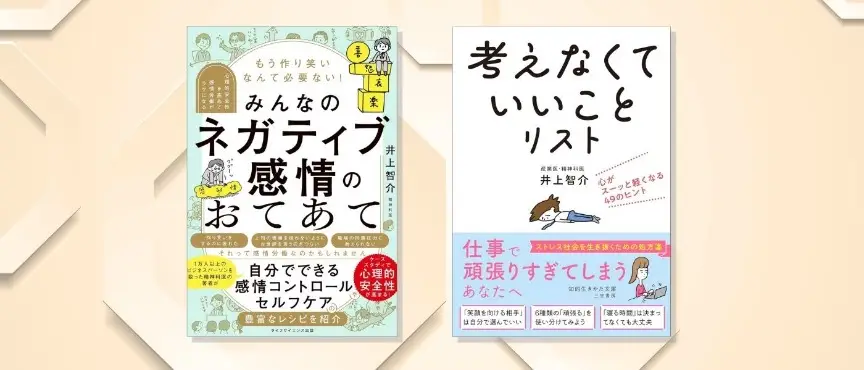
❖ 『みんなのネガティブ感情のおてあて』
ケーススタディで心理的安全性が高まる!
1万人以上のビジネスパーソンを救った精神科医の著者が自分でできる感情コントロールやセルフケアの豊富なレシピを紹介
作り笑いをするのに疲れた……。
上司の機嫌を損ねないようにお世辞を言うのがつらい・・・・・
職場の同調圧力に耐えられない……。
そうしたあなたの中のネガティブ感情は感情労働のせいなのかもしれません。
感情労働とは、「周囲に不満を感じさせないように自分の感情をコントロールして、ポジティブに振る舞い、賃金を得る働き方」のこと。感情労働はあなたが気づかないうちに職場の中にそっと溶け込み、徐々に心をむしばんでいきます。でも、ネガティブ感情自体は決して悪いものではありません。適切な方法でコントロールすることが大切なのです。
本書は、感情労働のストレスを和らげるために効果的な自分でできる感情コントロール術やセルフケアのレシピを、様々な職種のケースタディを交えて豊富なイラストともに分かりやすく解説しています。
また、感情労働の負担を軽減させるために必須となる職場の心理的安全性の高め方のポイントや心身の不調を抱えてしまった時に役立つ「感情労働のおてあて」も紹介。ビジネスパーソンはもちろんのことハードな感情労働を要求される教師やメディカルスタッフにも読んでほしい日本一かんたんな感情労働の入門書が登場!
❖ 『考えなくていいこと」リスト:心がスーッと軽くなる49のヒント』
【考えすぎなければ、仕事も人間関係もうまくいく】
「つい頑張りすぎてしまう人」必読の1冊
職場の人間関係、仕事のやりがい、将来への不安などを考えすぎてしまい、自分で自分の心を追い込んでしまってはいませんか。
もっとラフに生きるために、「考えなくていいこと」は考えない。その具体策を、1万人以上の心を救ってきた著者が紹介します!
◎「苦手な人」が職場にいる → 「期間限定思考」で心に余裕をつくる
◎頼まれた仕事を「断れない」 → 「YESと見せかけてNO作戦」で断る
◎上司より先に「帰りにくい」 → 「ノー残業デー」を決めておく
◎何事にも「全力投球」してしまう → 「6種類の頑張る」を使い分ける
◎理不尽に怒ってくる上司がいる → 「凛とした自衛官」を目指そう
人間関係や環境に振り回されず、考えすぎないで仕事と向き合うためのコツを身につけましょう!
boocoで読める!アルクの新刊、続々登場
語学アプリ「booco」なら、アルクのベストセラー書籍150タイトル以上が、学習し放題!
「キクタン」など、アルクの人気書籍600冊以上に対応!購入した書籍の本文と音声コンテンツをスマホで手軽に使用できるだけでなく、学習定着度を高めるクイズ機能が、日々の力試しや復習をサポートします。さらに、Plusプランを購入すれば、150冊以上の書籍が学習し放題に!
また、boocoの「読む」では次のような使い方ができます。
① 学習したいページを見ながら音声を再生できる
② 文字サイズや画面の明るさを調整できる
③ 書籍内検索ができる
※ これらの機能には本書を含め一部の書籍が対応しています。