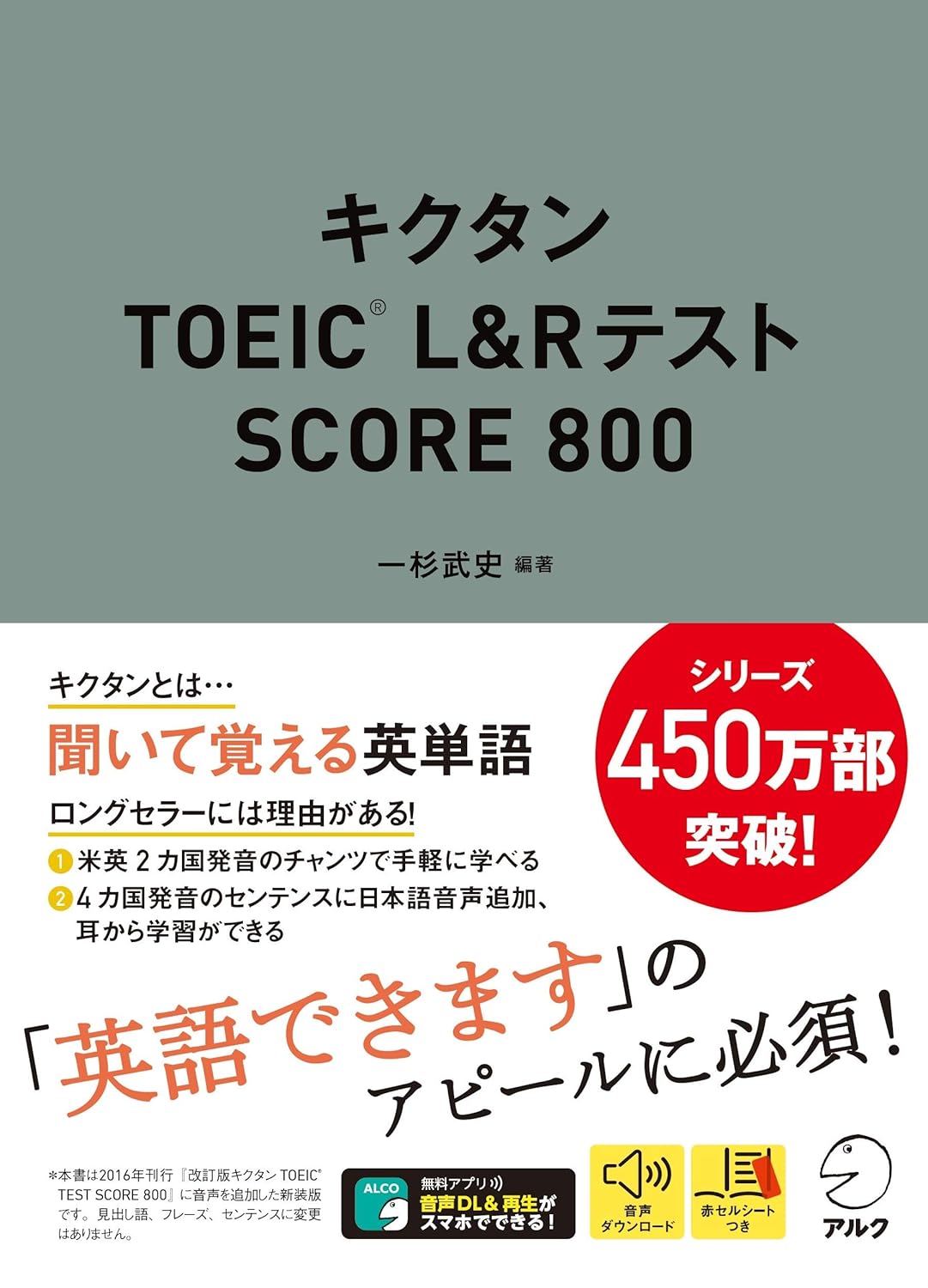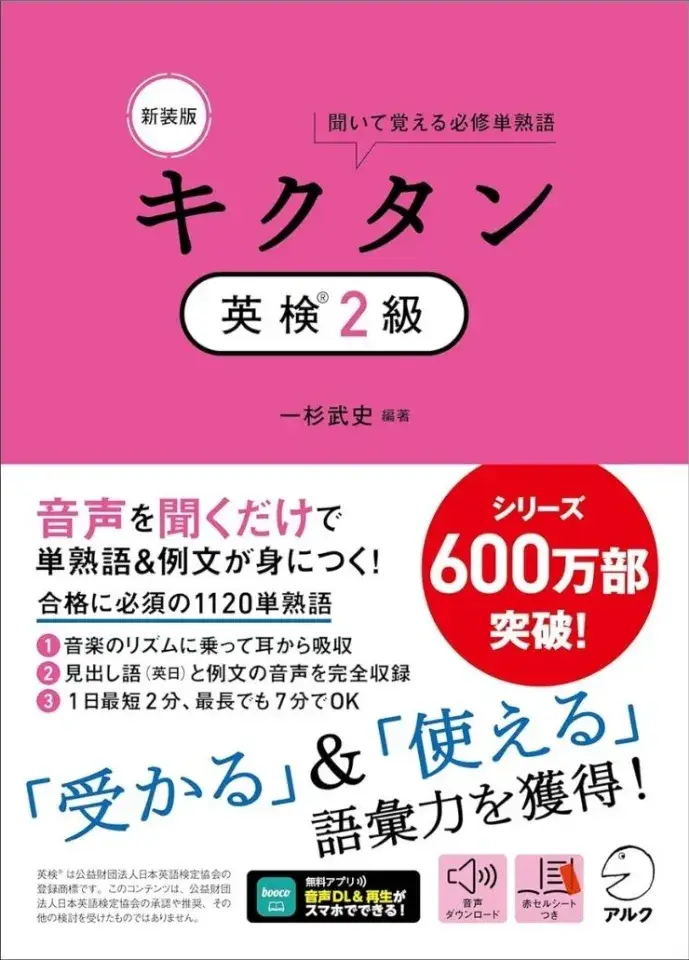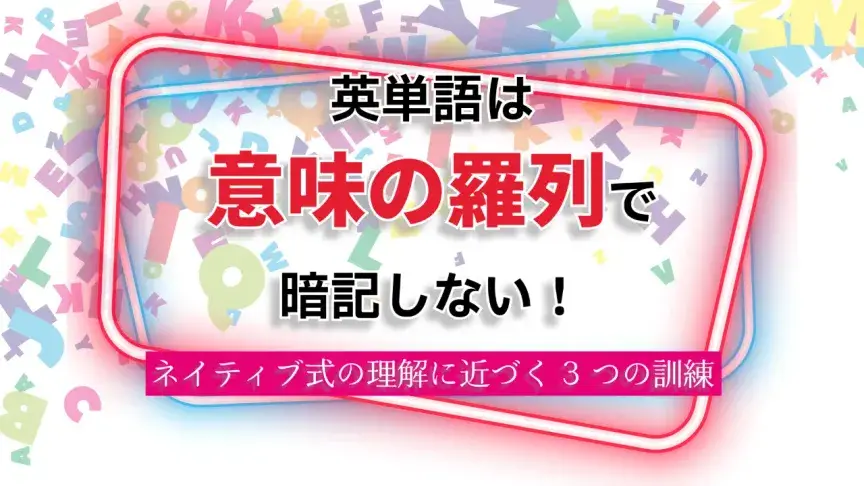
単語帳を開くと「①演じる ②演奏する ③実行する」といった複数の意味が並んでいます。多くの日本人学習者は、これを一つひとつ暗記しようとします。しかし、ネイティブにとって perform はあくまで「perform」でしかありません。ネイティブはどのように単語を理解しているのでしょうか。そして、その感覚に近づくにはどんな訓練が効果的なのでしょうか。
目次
英語も日本語のように「感覚」でとらえられる?
私たちは日本語の単語を「意味の一覧」で暗記したことはありませんよね。「走る」も「食べる」も、体験の中で自然に覚えてきました。
本来、英語も同じように“感覚”で理解できるはずです。
日本人は「意味リスト」で覚えがち
ところが学習の場面では、どうしても「意味リスト」で覚えてしまいがちです。日本の英語教育で最初に手にするのは、やっぱり単語帳。ページを開けば、
- perform=①演じる ②演奏する ③実行する
- run=①走る ②経営する ③流れる
と、番号付きでズラッと並んでいます。
まるで「この単語にはスイッチが3つあって、場面ごとに切り替えなきゃいけない」と言われているような気分になりませんか? そのせいで、「あれ、今は①でいいんだっけ? ②かな?」と立ち止まってしまう。
結果として、「知っているけど出てこない」単語が山のように増えてしまいます。暗記はしているのに会話で使えない・・・これは、多くの学習者がぶつかる典型的な壁です。
ネイティブは単語を“リスト”ではなく感覚でとらえる
一方で、ネイティブにとって単語はリストではありません。彼らは「perform=perform」としか思っていないのです。
たとえばperform。ネイティブは「遂行する」というひとつの感覚でとらえています。演技も演奏も手術も、「観客の前で・きちんと・やり遂げる」こと。だから文脈ごとに訳を切り替えているわけじゃないんです。
runも同じです。コアにあるのは「流れ続ける」というイメージ。人が走るのも、鼻水が出るのも、会社を運営するのも、ぜんぶ「流れ」で説明できます。
こうした「中心の感覚」を学習法の世界ではよく“コアイメージ”と呼びます。日本人が「別の意味」と考えている部分を、ネイティブはこのコアイメージの延長として自然に理解しているのです。だからいちいち頭の中で「①か②か③か」と仕分けをする必要がありません。
もう少しイメージを広げるために、日本語について考えてみましょう。たとえば「開く」という言葉。日本語では一語ですが、英語にするとopen(ドアを開く)、bloom(花が開く)、unfold(地図を開く)と、文脈によって違う動詞になります。
でも私たちは普段、「開く」という日本語をいろんな場面で使い分けていますよね。細かい違いを意識することなく、ただ「開く」として自然に口にしているはずです。つまり、英語も本来はそのレベルで感覚的に使えるものなんです。
ネイティブ式に近づく3つの訓練
では、どうすればその感覚に近づけるのでしょうか? ポイントは「暗記」から「イメージ」へのシフトです。
訓練1:単語の“核”をとらえる
単語に出会ったら、まずは「核」となるイメージをつかみます。
たとえばget。辞書には「得る」「到達する」「理解する」と並んでいますが、ネイティブの頭には「状態の変化・到達」というざっくりした感覚があるだけ。
「手に入れる」も「わかる」も「〜になる」も、全部「変化・到達」に含まれているのです。
訓練2:文脈ごとに覚える
単語だけでなく、実際に使われる例文ごとストックしましょう。
- She performed Hamlet on stage.(演技を遂行)
- She performed well on the test.(課題を遂行)
別の意味に見えても、「perform=遂行」という一本の線でつながっているとわかれば安心です。
訓練3:多読・多聴でイメージを積み上げる
教科書や辞書だけでは、イメージは固まりません。ドラマ、映画、ポッドキャスト、ニュース記事・・・いろんな場面で「この単語がこんなときに出てくるのか!」と体験していくことが大切です。
最初はぼんやりでも、繰り返し触れるうちに「ああ、この単語はこういう“空気”で使うんだな」という感覚が定着してきます。
単語帳はどう活用すればいい?
ここまで読んで、「じゃあ普通の単語帳は無意味なの?」と思った方もいるかもしれません。もちろんそんなことはありません。単語帳はあくまで“入口”としてとても役立ちます。
大切なのは、単語帳を「丸暗記の道具」としてではなく、「核となる感覚をつかむヒント集」として使うこと。語義がずらりと並んでいても、「この単語は結局どういうことを表すのか?」と一段上の視点で眺めると、コアイメージが浮かびやすくなります。
さらに、例文やフレーズのページを活用しましょう。
単語帳に載っている例文は、実際の文脈でどう使われるかを示してくれるサンプルです。意味のリストではなく、「どんな場面でどう響くのか」を確認する場として読むと、単語帳の価値がぐっと上がります。
まとめ
英単語を「訳語のリスト」として丸暗記するのは出発点にすぎません。ネイティブのようにコアイメージをとらえ、文脈ごとに理解し、多読多聴で感覚を積み上げる――。
この3つの訓練を習慣にすれば、「覚えたけど使えない」から「自然に出てくる」へと変わっていきます。今日からぜひ、単語帳を「意味リスト」ではなく「イメージをつかむツール」として開いてみませんか?
おすすめの単語帳
アルクが出版する「キクタン」シリーズは、まさに今回紹介した学習法と相性抜群。リズムに合わせて英単語とフレーズを耳から覚えられるので、意味のリストに頼らず「音と文脈のセット」で定着させることができます。
レベルや目的に応じて豊富なラインナップがそろっているため、受験英語からTOEIC、ビジネス英語まで、自分にぴったりの一冊が見つかります。
boocoで読める!アルクの新刊、続々登場
語学アプリ「booco」なら、アルクのベストセラー書籍200タイトル以上が、学習し放題!
「キクタン」などアルクの人気書籍800冊以上が音声対応。「読む」に対応した書籍では、本文と音声をスマホで手軽に利用できるほか、一部の書籍では、学習定着をサポートするクイズ機能で日々の復習や力試しも可能です。さらに、Plusプランに加入すれば200冊以上の書籍が学習し放題に!
boocoの「読む」機能では、次のような使い方ができます。
① 学習したいページを見ながら音声を再生できる
② 文字サイズや画面の明るさを調整できる
③ 書籍内検索ができる
※ これらの機能には一部の書籍が対応しています。