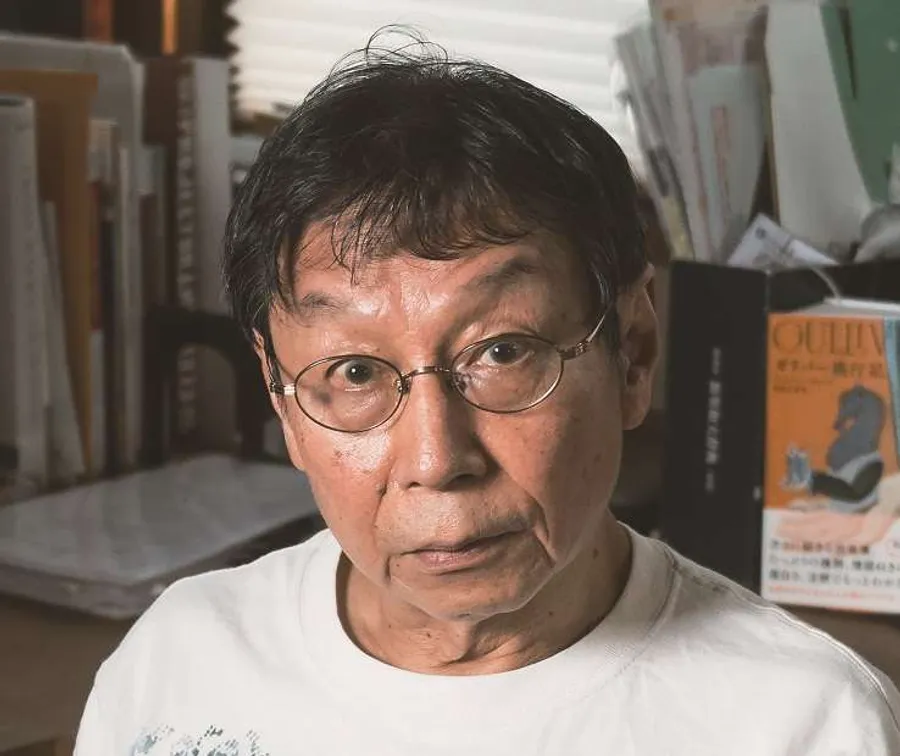ポール・オースターの小説世界への一歩は、間違い電話とともに始まります。翻訳家の柴田元幸さんと共に、オースターの作品冒頭の「一句」からひも解かれる、偶然の旅へと出掛けましょう。
It was a wrong number that started it, the telephone ringing three times in the dead of night, and the voice on the other end asking for someone he was not.
そもそものはじまりは間違い電話だった。真夜中にベルが三度鳴り、向こう側の声が、彼ではない誰かを求めてきたのだ。
—Paul Auster, City of Glass (1985)
物語のはじまりから、物事はあるべきでない方へずれていく。ずれはどんどん拡大していき、何かあるごとに、筆名で探偵小説を書いて空虚ながらも自足していた男は、深い闇をさらに深く堕(お)ちていく。そのすべてが間違い電話から始まったのだ。
だから「のはじまりは間違い電話だった」という訳は少し穏やかすぎる/当たり前に響きすぎるかもしれず、「それを始めた/始動させたのは間違い電話だった」という超直訳の方が、物語の精神には合っているかもしれない。日本語としてキザであるのが難だが。
いずれにしろ、一文で―正確には一文の3分の1以下で―読み手の興味をつかむ書き出しである。ポール・オースターほど、書き出しの一文で読者の心をつかむ書き手はいない。
These are the last things, she wrote.
これらは最後の物たちです、と彼女は書いていた。
—In the Country of Last Things『最後の物たちの国で』1987
For one whole year he did nothing but drive, traveling back and forth across America as he waited for the money to run out.
まる一年の間、彼はひたすら車を走らせ、アメリカじゅうを行ったり来たりしながら金がなくなるのを待った。
—The Music of Chance『偶然の音楽』1990
I was twelve years old the first time I walked on water.
12のときに、俺ははじめて水の上を歩いた。
—Mr. Vertigo『ミスター・ヴァーティゴ』1994
I was looking for a quiet place to die.
私は静かに死ねる場所を探していた。
—The Brooklyn Follies『ブルックリン・フォリーズ』2005
For almost a year now, he has been taking photographs of abandoned things.
もうほぼ一年にわたって、彼は捨てられた物たちの写真を撮りつづけている。
—Sunset Park『サンセット・パーク』2010
「最後の物たち」とはどういうことだろう。なぜ一年の間ひたすら車を走らせたのか。「水の上を歩く」とは? なぜ静かに死ねる場所を探すのか―あたかもゾウのように? 何のために捨てられた物たちの写真を撮りつづけるのか……。
ほかの多くの作家の場合、最初の数ページはまあ「様子見」であって、物語が始まるための舞台設定・準備期間という観があるが、オースターはそうではない。たったの一文で疑問が始動し、読み手の頭の中で仮設の物語が始まる。オースターを読むことは、その仮設の物語に、作者の繰り出す「本物」の物語が上書きされる快感に浸ることである。
そしてそのすべてが、小説第1作『ガラスの街』冒頭の、一本の間違い電話から始まったのである。その時代に、ナンバー表示だのモニター機能だのがなかったことは、物語にとって大きな幸いであった。
※本記事は『ENGLISH JOURNAL』2020年10号に掲載した記事を再編集したものです。
boocoで読める!アルクの新刊、続々登場
語学アプリ「booco」なら、アルクのベストセラー書籍200タイトル以上が、学習し放題!
「キクタン」などアルクの人気書籍800冊以上が音声対応。「読む」に対応した書籍では、本文と音声をスマホで手軽に利用できるほか、一部の書籍では、学習定着をサポートするクイズ機能で日々の復習や力試しも可能です。さらに、Plusプランに加入すれば200冊以上の書籍が学習し放題に!
boocoの「読む」機能では、次のような使い方ができます。
① 学習したいページを見ながら音声を再生できる
② 文字サイズや画面の明るさを調整できる
③ 書籍内検索ができる
※ これらの機能には一部の書籍が対応しています。

▼「booco」の無料ダウンロードはこちらから