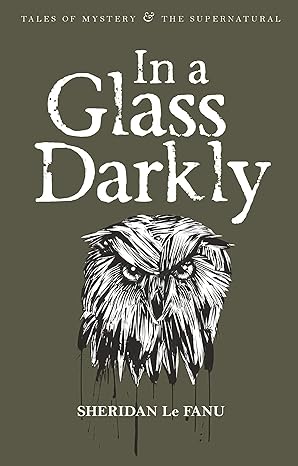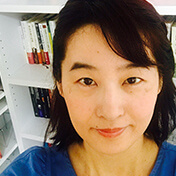時代を経て読み継がれる文学の名作には、「今」を生きるためのヒントやテーマが潜んでいます。この連載「現代的な視点で読み解く アクチュアルな英語文学」では、英文学と医学史がご専門の上智大学教授である小川公代さんが、主に18世紀以降のイギリス文学から今日的な課題を探ります。第6回で取り上げるのは、 アイルランド作家レ・ファニュの作品を原作とする異色の吸血鬼映画『カーミラ』 です。 #MeTooや#わきまえない女の時代 ならでは若い女性2人の姿とは?
性をテーマとするハリス監督の映画『カーミラ』
2019年に公開された、エミリー・ハリス監督による『カーミラ』(原題:Carmilla)は新たなヴァンパイア映画として紹介され、話題を呼んだ。しかし、この映画は厳密な意味で吸血鬼映画と呼べるのだろうか。
舞台は18世紀イングランド。15歳のララ(Lara)は、ある田舎町で父親と厳格な女性家庭教師ミス・フォンテーヌとともに3人で暮らしている。ある夜、馬車の事故でけがをしたという同年代の少女が屋敷に運び込まれるが、記憶を失っている。ララは彼女をカーミラと名付け、親密になるが、ララ自身は日増しに弱っていく。その様子を見て、家庭教師のミス・フォンテーヌがこの謎の少女カーミラが吸血鬼ではないかと疑い始める。
大筋ではアイルランドの作家ジョゼフ・シェリダン・レ・ファニュ(Joseph Sheridan Le Fanu、1814-73年)による同名の原作小説『吸血鬼カーミラ』(邦題はいくつか異なるものがある)のプロットをなぞってはいるが、肝心のカーミラの「牙」が一度も映し出されないばかりか(首筋の痕もない)、東欧ではなくイングランドの物語として描かれるのはかなり大胆な改変だと言わざるを得ない。
原作の主人公はローラ(Laura)という少女で、「故郷」(home)はイングランドだが、物語の舞台はスチリア(Styria)――オーストリアとハンガリーの境界の吸血鬼神話が伝えられている地方――に設定されている。それによって、レ・ファニュは彼自身のいわゆる「故郷」から離れた場所に「アングロ・アイリッシュ」(Anglo-Irish)として生きる存在の不安を浮かび上がらせることができた。
ちなみに、カトリック教徒が大多数のアイルランドでは長らく「迷信」(superstition)が信じられ、小説のカーミラは、いわばアイルランドの田舎の墓地に現れるという言い伝えの「バンシー」(ban si)の化身として描かれてもいる。レ・ファニュ自身は、プロテスタントの聖職者として生活しながら、イングランドからやって来た「アングロ・アイリッシュ」と呼ばれる支配層の先祖の血統を継ぎ、ローラと同じように自分にとっての「故郷」はどこなのか、確信を持てないでいた。
ハリス版『カーミラ』は、アイルランドとイングランドのはざまで生きる原作者のアイデンティティーの揺らぎに目を向けるというより、この完全に隔絶されたイングランドの田舎の世界で性の芽生えと解放を探究するララと謎の少女カーミラに対して、それを過度に抑圧しようとする家父長的な父親とその価値観を内面化した家庭教師のミス・フォンテーヌという対立軸に焦点が当てられている。それは、#MeToo運動やもっと最近で言うと#わきまえない女を主張する声が盛り上がる今の時代に女性監督が選ぶにふさわしいテーマでもあっただろう。
少なくとも厳密な意味でのヴァンパイア映画でも、アングロ・アイリッシュの両義性をはらむアイデンティティーの物語でもない映画『カーミラ』を世に送り出したハリス監督の想像力の発露を、レ・ファニュまでたどりながら、かつアクチュアルに考えてみたい。
吸血鬼に牙はあるか、ないか?
映画評には、ハリス監督による『カーミラ』の芸術性の高さを評価するものもあるが、原作からの大胆な改変に批判的なものが多い。先述したように、吸血鬼であるはずのカーミラが一度も「牙」をむかない。また、ララの首筋には牙を突き立てられた痕もない。
確かにこの改変は、これまでの同小説のアダプテーションと比べても吸血鬼色が格段に薄いと言える。例えば、1960年に製作されたフランス・イタリア合作映画『血とバラ』(原作:Et mourir de plaisir)におけるカーミラとジョルジアのレズビアンシーンはその後の女吸血鬼ジャンルに大きな影響を与えたが、貴族的、棺おけで眠る、心臓に杭を打たれて死ぬ、などの特徴は原作から忠実に引き継がれている。
また、『バンパイア・ラヴァーズ』(原題:The Vampire Lovers)も1970年のハマー・フィルム・プロダクションによるレ・ファニュの『吸血鬼カーミラ』の映画化で、イングリッド・ピットのエロティシズムが際立つ女吸血鬼映画の決定版とも言える。ここでもやはり「牙」は重要な要素の一つである。
レ・ファニュの小説『吸血鬼カーミラ』と比較しても、やはりハリス版のアダプテーションはオリジナルから決別する意思が圧倒的に明確に表れている。とりわけ注目すべきは、原作では重要な要素と見なされているヒロインの首筋の痕や、カーミラが吸血鬼であるという緻密な文献学的資料などを、ハリスは完全に排している点である。
ただし、この映画版が比較的忠実に再現している点があるとすれば、それは「幻覚」(hallucination)という症状を「夢」(dream)という現象で表現しているところである。レ・ファニュの小説では、吸血鬼という超自然的な存在と同程度に「幻覚」が強調されているため、おそらく、それを意識したハリスがララの「夢」に重要な役割を与えながら、原作との興味深いパラレルを作り出している。映画でも原作と同じように、カーミラが屋敷に運び込まれて以降、ララはおぞましい「夢」を見る。「夢」とも「幻覚」とも言えないヴィジョンをローラに何度も見せるレ・ファニュの語りを、現実と夢の境界が曖昧になる世界として映像でなぞるハリスの手腕は評価に値するだろう。
レ・ファニュの小説では、ヴォルデンブルグ男爵という人物が、カーミラが100年以上前に一度死んだ女性であり、今は吸血鬼として彷徨(ほうこう)していることを明らかにした上で、ローラの父親と力を合わせ、この怪物を退治する。しかし、ハリス版には、ヴォンデンブルグ男爵、あるいは彼と同じ役割が与えられる登場人物はいない。その代わりに、ミス・フォンテーヌがハンマーのようなものでカーミラの心臓をつぶして殺し、スクリーンにはその血だらけの死体が映し出される。太陽の日を浴びても灰と化すことはない。
ミス・フォンテーヌとミス・ギデンズの共通点
では、ハリス版では、なぜ吸血鬼カーミラの正体が暴かれる場面が完全に抜け落ち、代わりにミス・フォンテーヌと父親が共謀して、吸血鬼かどうか確証が得られない少女を殺害する結末に改変されたのだろうか。
おそらく、これまで100年以上も「加害者」として表象されてきた怪物カーミラを、性の解放を求めるヒロインとともに抑圧される「被害者」として表象するためだったのではないだろうか。映画を見終わった後、ミス・フォンテーヌの拡大解釈、あるいは妄想によって、カーミラという美しい少女が「吸血鬼」に仕立て上げられてしまったのではないかという疑いがどうしても消えないのも、これなら説明がつく。
このプロットの改変は、おそらくミス・フォンテーヌが抱える彼女自身の抑圧的な衝動、神経症的な傾向とも関係があるだろう。この性質を備える女性について考えるとき、真っ先に思い浮かぶのが、ヘンリー・ジェイムズによる1898年の小説『ねじの回転』(原題:The Turn of the Screw)を映画化した1961年の作品『回転』(原題:The Innocents)である。ジャック・クレイトン監督のこの作品では、まさに古い屋敷で家庭教師として雇われたミス・ギデンズ(デボラ・カーが演じた)の性の抑圧が執拗(しつよう)に描かれる。彼女は前任者の家庭教師など、性に対してみだらであるとうわさされる人々をことごとく軽蔑する。ミス・ギデンズがたびたび屋敷に出現する霊の存在を信じている点も、ミス・フォンテーヌの迷信深さと重なり合う。ミス・ギデンズが世話をする兄妹(マイルスとフロラ)を霊から守ろうとするあまり、その誤った正義感によって悲劇が導かれる結末――マイルスの死――は象徴的である。
ハリス版『カーミラ』でおそらく注目に値するのは、抑圧的なミス・フォンテーヌが、ララと彼女を魅惑するカーミラの関係を羨望(せんぼう)のまなざしで見つめながらも、セクシュアリティーや身体の神秘の探究は「悪魔的」だとして虐待にも近い、しつけを徹底的に行っていることだ。これはレ・ファニュの原作でも中心的なテーマであり、語り手ローラの育ちの良さが性的な表現を制限させてはいるが、ローラとカーミラは互いが欲望の対象となるレズビアン的な愛着を育んでいる。
ハリス版では、そのテーマがさらに強化され、ララとカーミラが互いに感じている性的興奮や2人が寝室や戸外で密やかに交わすキスや官能的な触れ合いが前景化されている。例えば、ララは自室で父親の図書室から持ち出した解剖学の本の図版を眺めながら、うっとりする。左手でその図版を写しているところを目撃したミス・フォンテーヌは、その左手が使えないよう縛る。このような家庭教師の過干渉はたとえ18世紀イングランドのモラルに照らしても、異常な行為に見える。かといって、ララもミス・フォンテーヌの命令に従順に従うばかりではない。カーミラと連帯して2人で自由を謳歌(おうか)するのだ。
性への好奇心を隠さずレズビアン的な関係を探究するカーミラとララを「悪魔的」と形容し、抑圧的に振る舞うミス・フォンテーヌの不気味さは際立つばかりである。カーミラとララがまさに体を重ねようとしているときに部屋に入り、その2人の姿を目にした彼女は、ララが日に日に体が弱っていることや村で同じような症状で亡くなった人が3人いるという事実から、カーミラが吸血鬼に違いないと断定する。そこには証拠と呼べる材料はほとんどない。事故に遭った場所で発見されたいかがわしい本くらいであろう。カーミラが一度も吸血鬼として誰にも「牙」をむいていないことを考えると、最後の最後まで彼女が本当にヴァンパイアだったのかという疑念は晴れない。
アダプテーションとは、新たに生み出される文化的土壌によってさまざまに変容する作品である。そう考えれば可能性としては、この映画『カーミラ』は、冤罪から引き起こされた「魔女狩り」の物語への翻案という解釈もあり得る。あるいは、家父長的な社会において、少女たちの、あるいはセクシュアル・マイノリティーの声が奪われている現状を揶揄(やゆ)する作品にもなっているのではないだろうか。あるいは、ミス・フォンテーヌのクィア性を読み取ることも可能かもしれない。彼女のララへの異常な執着は、彼女自身の同性愛を暗に示すものとして解釈することもできる。カーミラが映画の中で「吸血鬼」であることが証明されないのも、このような解釈からくみ取ることができるのではないだろうか。
レ・ファニュの『吸血鬼カーミラ』
以上の議論を踏まえると、ハリス版が大胆にも改変に踏み切った背景には、レ・ファニュの異性愛偏向型の物語への反発もあったのかもしれない。
彼はアングロ・アイリッシュの末裔(まつえい)として吸血鬼小説を書いたが、そこに描かれるヴァンパイアのカーミラは、アイルランドの言い伝えとして知られる「バンシー」(ban si)の化身として登場する。この言い伝えによれば、霊(si)は吸血鬼ではないため、レ・ファニュはドン・オーギュスタン・カルメによる『精霊示現、ならびに、ハンガリー、モラヴィア等の吸血鬼あるいは蘇れる死者に関する論考』(1746年)につづられた吸血鬼伝説や、メアリー・シェリーやバイロン卿とともに怪奇物語をつづったポリドリによる『吸血鬼』などから着想を得て *1 、いわば折衷型のゴシック小説を書いた。
そういう影響下でレ・ファニュが生み出した『吸血鬼カーミラ』という小説は、あくまで家父長的な、ヘテロセクシュアルな枠組みの中にあった。カーミラがローラの母方の先祖でもあるカルンシュタイン伯爵夫人マーカラであったことが、吸血鬼に関して膨大な知識を備えたヴォルデンブルグ男爵の精力的な調査により明らかになるのだが、人間であった時代のカーミラは異性愛者であったことが語られている。
ローラの父親がこの博学のヴォルデンブルグ男爵に女伯爵マーカラの正確な墓地の位置をどのように突き止めたのか尋ねると、男爵は自身の先祖でもある「ヴォルデンブルグ」という、モラビアにいた貴族男性の日録や論文に言及しながら、次のように答えている。
伝統や言い伝えは、もちろん多少なりとも変色し、歪曲(わいきょく)されております。彼は確かにモラビアの貴人と言ってよいのかもしれません。モラビアに住居を移していましたし、貴族でもありましたので。しかし、彼は実は上スチリアの出身なのです。ここでは彼が少年時代、 美しい少女マーカラ・カルンシュタインと、相思相愛の間柄であったとだけ申し上げておきましょう 。彼女が若くして他界し、彼は絶望のどん底に突き落とされました。
Le Fanu, p.318. 日本語訳と太字は筆者による
この物語の骨子はあくまでヘテロセクシュアルな悲恋であることが強調されている。吸血鬼カーミラを退治することに成功したヴォルデンブルグ男爵によれば、彼の先祖である貴人が崇拝していたマーカラという女性が吸血鬼になり、貴人は彼女が「それよりもはるかに恐ろしい状態」に変化してしまうことを危惧し、彼女を救おうと決心した。しかし最終的に貴人の死期が迫り、かなわなかったため、その意志を遠い子孫であるヴォルデンブルグ男爵が継いだという経緯がある。
小説の山場でもある第16章では、ヴォルデンブルグ男爵がどのような方法でカーミラが吸血鬼であることを突き止めたのかが解説されている。彼は、『死後の魔術』、アウグルティヌスの『死者たちのための配慮』(原題:De cura pro mortuis agenda)やジョン・クリストファー・ヘレンベルグによる『吸血鬼についての哲学的かつキリスト教的考察』(原題:Philosophicae et Christianae Cogitationes de Vampiris)やその他1000冊もの書物から得た知識だけでなく、判例の要約版までも所蔵しており、それらを基に、吸血鬼の実態を知り、棺の中を暴くことに成功した。また、「カーミラ」と呼ばれるこの美しい少女が100年以上生き続ける「マーカラ」であることを突き止めることができたのは、「カーミラ」(Carmilla)という名前が実は「マーカラ」(Mircalla)から一字の省略も追加もなく、いわばアナグラム的に作られた名前だったからである。最終的にこの女吸血鬼は血だまりと灰と化し、そのことで、疑う余地なく吸血鬼であることが証明される。
ハリス版では主人公のララが恣意(しい)的にいくつかの名前を挙げ、謎の美少女がその中から「カーミラ」という名前を選んでいる。原作ではこのアナグラムが吸血鬼の正体を突き止める鍵になっていることを考えると、この名前の恣意性は意図的であるように思われる。映画版では、「過去」のヴァンパイア神話と「現在」の少女たちの生を断絶させていることもうかがえる。すなわち、原作の『吸血鬼カーミラ』は、カーミラが正真正銘ヴァンパイアであることを幾重にも証明しようとする実証主義的な、あるいは文献学的な関心が核心部にある物語となっている一方で *2 、ハリス版はカーミラがヴァンパイアではない可能性をあえて残している。
ブラム・ストーカーの小説『吸血鬼ドラキュラ』もまた、ヴァン・ヘルシング教授や科学者のジャック・スワード博士が、科学や知力という手段を用いて主人公のジョナサン・ハーカーに加勢し、吸血鬼退治に挑む物語であり、明らかにレ・ファニュの『吸血鬼カーミラ』のアダプテーションである。ヴォルデンブルグ男爵が誇示した知の権威はストーカーの作品では科学者たちに引き継がれたというわけだ *3 。弁理士ジョナサン・ハーカーはトランシルヴァニア奥地の城に住むドラキュラ伯爵を訪ね、イギリス移住のための手伝いをするうちに彼の恐ろしい正体に気付く。伯爵は海路でイギリスに向かい、ルーシー・ウェステンラを毒牙にかけ、その友人でハーカーの恋人でもあるミーナ(ウェルヘルミナ)にも接近する。生々しい吸血場面の記述などは少ないものの、ドラキュラ伯爵の魔の手が主人公ハーカーとのちに彼の妻となるミーナに忍び寄る場面は緊迫感がある。吸血鬼退治という名において人間を滅ぼす存在を消滅させる物語は、ハリス版では希薄になり、代わりにわきまえない少女が抑圧される家父長制の恐怖物語になっている。
結び
ハリス監督の『カーミラ』は、「牙」を映し出さないヴァンパイア映画として異例である。しかし、レ・ファニュの吸血鬼小説を翻案することで、家父長的な社会において、女性の欲望が、あるいは声が抑圧される現実を生々しく描くとすれば、おそらくこのような物語になる、と言いたいのだろう。
「牙」も「血」もほとんど描かれないヴァンパイア映画への批判はあるものの、カーミラの異性愛を美化するレ・ファニュの原作部分を消し去ることができれば、家父長的な異性愛偏重主義を批判するというもくろみはほぼ成功したと言えないだろうか。女性の性の解放を象徴する吸血鬼を「加害者」として退治するのではなく、逆に、抑圧される「被害者」としての女性の愁訴の声を届ける映画として解釈することもでき、そうすれば、家父長制批判というテーマが鮮やかに浮かび上がる。
また、『回転』の家庭教師ミス・ギデンズとの共通点が多数見受けられるミス・フォンテーヌの神経症や過度の抑圧を、男性中心社会、異性愛中心主義を深く内面化した女性の典型例として見ることもできるだろう。すなわち、『カーミラ』の主人公は、血を吸う怪物カーミラではなく、家父長社会に順応し過ぎた女性の一つの症例として浮かび上がるミス・フォンテーヌであるとも考えられる。事実、主演俳優の一人に家庭教師役のジェシカ・レインの名前が記されている。
次回は2021年4月2日に公開予定です。
参考文献
■Sheridan Le Fanu, In a Glass Darkly, “Carmilla,” ed. Robert Tracy (Oxford and New York: Oxford University Press, 1993)
▼Wordsworth Editions版
boocoで読める!アルクの新刊、続々登場
語学アプリ「booco」なら、アルクのベストセラー書籍200タイトル以上が、学習し放題!
「キクタン」などアルクの人気書籍800冊以上が音声対応。「読む」に対応した書籍では、本文と音声をスマホで手軽に利用できるほか、一部の書籍では、学習定着をサポートするクイズ機能で日々の復習や力試しも可能です。さらに、Plusプランに加入すれば200冊以上の書籍が学習し放題に!
boocoの「読む」機能では、次のような使い方ができます。
① 学習したいページを見ながら音声を再生できる
② 文字サイズや画面の明るさを調整できる
③ 書籍内検索ができる
※ これらの機能には一部の書籍が対応しています。

▼「booco」の無料ダウンロードはこちらから