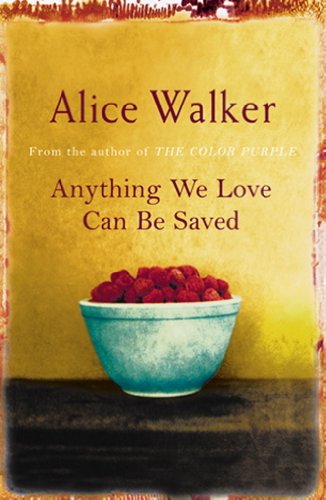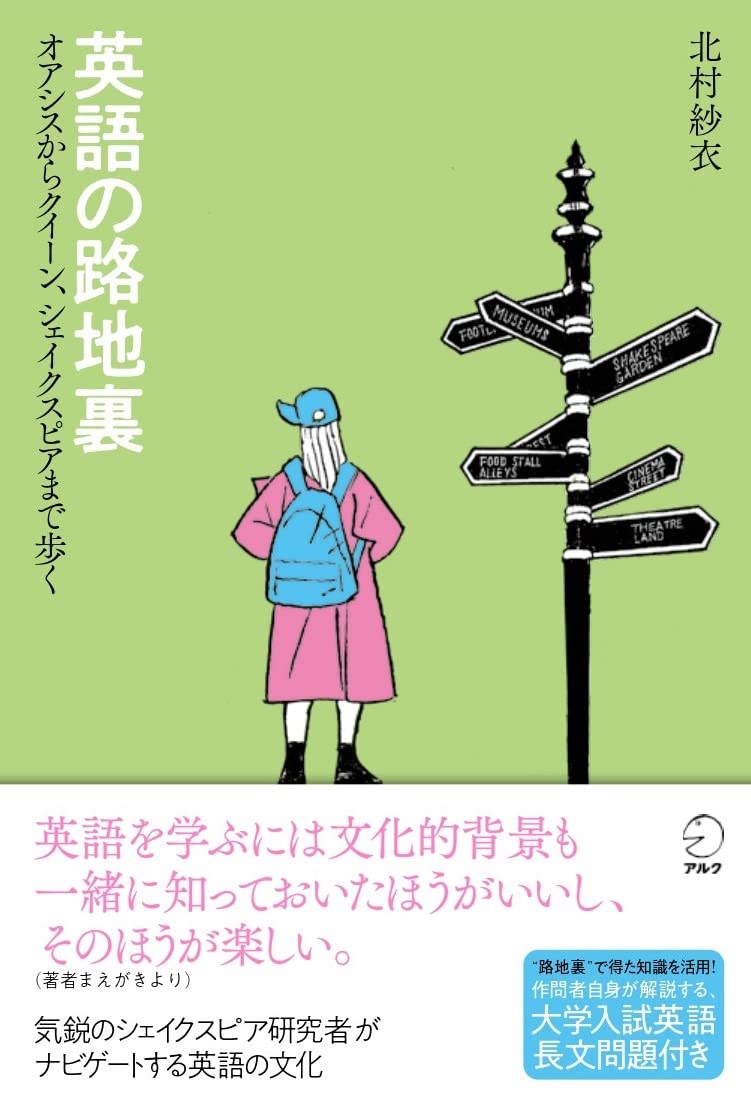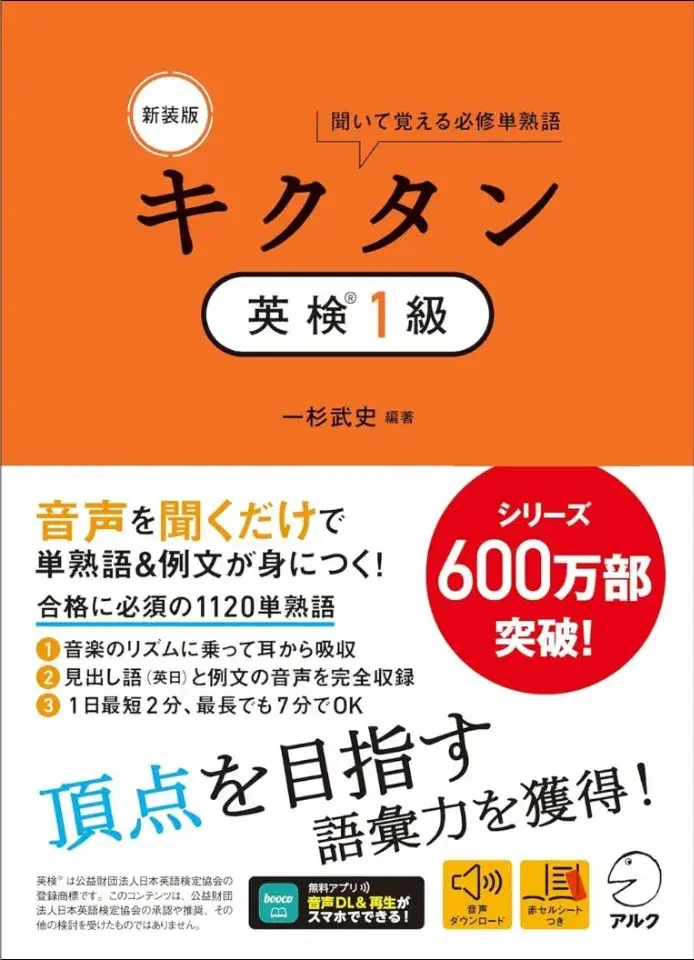英語は、文学、映画やドラマ、コメディーや歌などに楽しく触れながら学ぶと、習得しやすくなります。連載「文学&カルチャー英語」では、シェイクスピア研究者で大学准教授、自称「不真面目な批評家」の北村紗衣さんが、英語の日常表現や奥深さを紹介します。今回のテーマは、学校であまり習わない 「二人称複数」の用法 です。イギリスの俳優で出身地スコットランドの英語を話した ショーン・コネリー や、 バラク・オバマ前アメリカ大統領 の発言を例に解説。
トップ写真:山本高裕(編集部)
イギリスの名優ショーン・コネリーをしのんで
この原稿を書き始めた11月1日、スコットランド出身の映画俳優であるショーン・コネリーが90歳で亡くなったという訃報が入ってきました。
007シリーズのジェームズ・ボンド役や『薔薇(ばら)の名前』(1986)のバスカヴィルのウィリアム役などで知られる大スターであり、映画界からはコネリーを悼む声がたくさん聞こえてきました。往年のハリウッドをしのばせるゴージャスな迫力を持つスターだったため、スコットランドの前首相であるアレックス・サモンドは「世界で最も偉大なスコットランド人であり、本物のハリウッドスターの最後の生き残り」(※1)だったとコメントしています。
今回の記事では、そうしたコネリーを追悼する発言の中から、故人の話しぶりがしのばれるようなものを取り上げて解説してみたいと思います。
コネリーの思い出を振り返る英語ツイート
ショーン・コネリーの訃報に際し、『オーシャンズ13』の脚本家の一人であるブライアン・コッペルマンがコネリーと一緒に仕事をしたときの思い出をTwitterで語っています。 その長いスレッド で述べられているのは、コッペルマンと仕事仲間であるデヴィッド・レヴィーンが2004年、コネリーの出演作のために脚本の書き直しを頼まれたときの話です。
コネリーは非常に仕事熱心で、当時は無名の脚本家だったコッペルマンとレヴィーンとの関係も大変良好であり、真面目に作品に取り組んでいたらしいのですが、監督(このスレッドでは名前は伏せられています)がてんでダメだったせいで映画の企画はつぶれてしまったそうです。
コネリーの仕事ぶりはもちろん、ハリウッドで脚本のリライトがどう行われているかなども垣間見える面白い話なのですが、ここで注目したいのは、下に引用したコッペルマンの2つの投稿です。
どちらもダブルクォーテーションマーク(“ ”)で人の発言が囲ってありますが、それぞれの発言を誰が話したのかについては明示されていません。文脈からわかるので発言者が省略されているのですが、文脈以外に大きな手掛かりがあります。
Twitterの投稿なので表記などにちょっと一貫性がないため、少し直して書いてみます。最初のツイートには、次の会話が記されています。
“Should we get the studio or director on the speaker phone?”
“No. Youse’ll tell ’em what we’re gonna do.”
文脈からして最初の発言の“we”はコッペルマンとレヴィーンを指します。次がコネリーの発言です。 “(’)em”はthemの省略形 で、“the studio or director”を指します。「スタジオか監督を会議のスピーカーホンに呼びましょうか?」「いや、僕らがやることは君たちから先方に話してもらうようにしよう」というような会話です。
映画スタジオのスタッフがリライトについての会議に直接参加する必要はなく、決めたことを後からコッペルマンとレヴィーンから報告してもらうのでOKだろうという話の流れですね。
2つ目のツイートは、コッペルマンとレヴィーンがコネリー宛てに送った荷物が税関で止められてしまったときの話で、次のような会話が書かれています。
“You’re going to walk into customs and demand the package?”“Call youse fellas in an hour or so.”
“Call ”の前にはI’m gonnaなどを補ってみましょう。「直接税関まで歩いていって包みをよこせって言うつもりなんですか?」「1時間くらいでそっちに電話するからさ」という内容です。最初の発言がコッペルマンとレヴィーン、その次がコネリーの発言です。行動的なコネリーの性格がわかる会話になっています。
スコットランド男の話し方:youseとは
ここで注目したいのは、コネリーの発言にある“Youse’ll”や“youse fellas”です。
youse、あるいはyous という単語は学校英語ではほとんど習わないと思うのであまり聞いたことがない人も多いかと思うのですが、これは 二人称複数の代名詞で、つまり「あなたたち」という意味 です。「えっ、二人称複数の代名詞はyouでは?」と思うでしょうが、youは基本的に二人称の単数と複数、両方に使用されます。
以前 この連載で解説 したように、昔の英語ではthouが二人称の単数、youが二人称の複数という使い分けがあったのですが、今はyouに一本化され、thouはヨークシャーの一部などを除くとほとんど使われていません。しかし、話していて二人称の単数と複数を区別したいときは結構あるので、英語圏の各地で youの複数形が方言として発達 しています。
youseやyousはアイルランド(※2)や スコットランド(※3)で使われている二人称複数の代名詞です。 イングランドの北方やアメリカ、オーストラリア など、もともとこうした単語が使われていた地域から移民してきた人々が多く住んでいるようなところでは、今も高齢者が使っている(※4)ようです。アメリカでは、特にフィラデルフィア近郊でよく使われます。
ショーン・コネリーはスコットランド人であることに誇りを持っており、スコットランドの独立を支持し(※5)、いつも 出身地であるエディンバラ辺りの方言を話して (※6)いました。美声のコネリーのおかげで、エディンバラ方言が好ましいアクセントとして広く認識されるようになったのではないか(※7)という話もあるくらいです。
このツイートでコッペルマンは、コネリーが話していたスコットランド方言をおそらくそのまま書いているのではないかと思われます。 スコットランド人がよく使うyouseが出てきていて、わりとフランクな感じのしゃべり方がそのまま表現 されています。
映画ファンであれば、スレッドをちゃんと全部読んでいなくても、こうした発言がコネリーのものだということが勘でわかるように書かれています。いかにも 有無を言わせぬスコットランド男といったような口調が(ちょっと盛っているのかもしれませんが)再現されているからです。
二人称複数代名詞のバラエティー:you guys, you all
二人称複数代名詞を表す言葉はほかにもあります。
地域ごとのバラエティーがたくさんあるので一般化は困難ですが、 アメリカ英語で二人称の複数を明示したいときによく使われるのは2語のyou guys です。一見、代名詞っぽくないのですが、まるで代名詞のように使われます。
『エンターテインメント・ウィークリー』のインタビュー映像では、バラク・オバマ前大統領が最後に“ Thank you guys.”(皆さん、ありがとう)と述べており、これは Thank you.のyouのところを複数形にしたもの と考えることができます。
guyは主に男性を指すのですが、 アメリカ英語のyou guysは相手の性別を問わず広く使われている ようです。例えば、CNNニュースのフッテージでは、オバマ前大統領がガールスカウトの少女たちに対して“What are you guys doing in my yard?” (君たち、僕の庭で何してるのかな?)と聞いています。
オバマ前大統領は教養人らしいかなりわかりやすいアメリカ英語を話します。さらに、これらの動画ではいずれも子どもに優しく話し掛けるような文脈で代名詞のようにyou guysを用いています。you guysはアメリカ英語では標準的な表現として使用されていることがわかります。
一方、 アメリカの南部ではyou allとか、それを短くしたy’allが二人称複数の代名詞として使用 されることがあります。オックスフォード英語辞典によると、アメリカの中部やカリブ海地域でも使われることがあるようです。
guyは主に男性を指す言葉だということもあり、 ジェンダーニュートラルな表現を好む人はyou allやy’allを用いる ことがあります。アフリカ系アメリカ人のフェミニストで作家であるアリス・ウォーカーは、you guysが男性ばかりを指しているように聞こえるため、you allの方が好きだそうです。
連載終了のごあいさつ
2019年の10月から始めてきたこのミニコラム連載ですが、著者の多忙のため、今回の連載をもっていったん終了することとなりました。連載が電子書籍となって2冊刊行され、皆さまに読んでいただけてとてもうれしく思っています。現在、次の著書の執筆を行っており、なんらかの形でまた皆さまと書籍や記事という形で会うことができますと幸いです。1年以上の間、どうもありがとうございました。
参考文献
■Alice Walker, Anything We Love Can Be, Ballantine Books, 2012.
▼電子書籍版
■“you-all, pron.” OED Online, Oxford University Press, September 2020, www.oed.com/view/Entry/232148. Accessed 2 November 2020.
■“yous, pron.” OED Online, Oxford University Press, September 2020, www.oed.com/view/Entry/232182. Accessed 2 November 2020.
北村紗衣さんの新刊
注目のシェイクスピア研究者、北村紗衣が、海外文学や洋画、洋楽を、路地裏を散歩するように気軽に読み解きながら、楽しくてちょっと役立つ英語の世界へとご案内。英語圏の質の高いカルチャーに触れながら、高い英語運用能力を得る上で重要な文化的背景が自然と身に付きます。“路地裏”を抜けた後は、“広場”にて著者自身が作問し解説する「大学入試英語長文問題」も堪能できる、ユニークな英語カルチャーエッセイ。
(※1) https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-54761824
(※2) https://www.irishtimes.com/culture/heritage/the-correct-youse-of-english-1.1623440
(※6) https://www.irishtimes.com/culture/film/james-bond-actor-sean-connery-dies-aged-90-1.4396636
boocoで読める!アルクの新刊、続々登場
語学アプリ「booco」なら、アルクのベストセラー書籍200タイトル以上が、学習し放題!
「キクタン」などアルクの人気書籍800冊以上が音声対応。「読む」に対応した書籍では、本文と音声をスマホで手軽に利用できるほか、一部の書籍では、学習定着をサポートするクイズ機能で日々の復習や力試しも可能です。さらに、Plusプランに加入すれば200冊以上の書籍が学習し放題に!
boocoの「読む」機能では、次のような使い方ができます。
① 学習したいページを見ながら音声を再生できる
② 文字サイズや画面の明るさを調整できる
③ 書籍内検索ができる
※ これらの機能には一部の書籍が対応しています。

▼「booco」の無料ダウンロードはこちらから