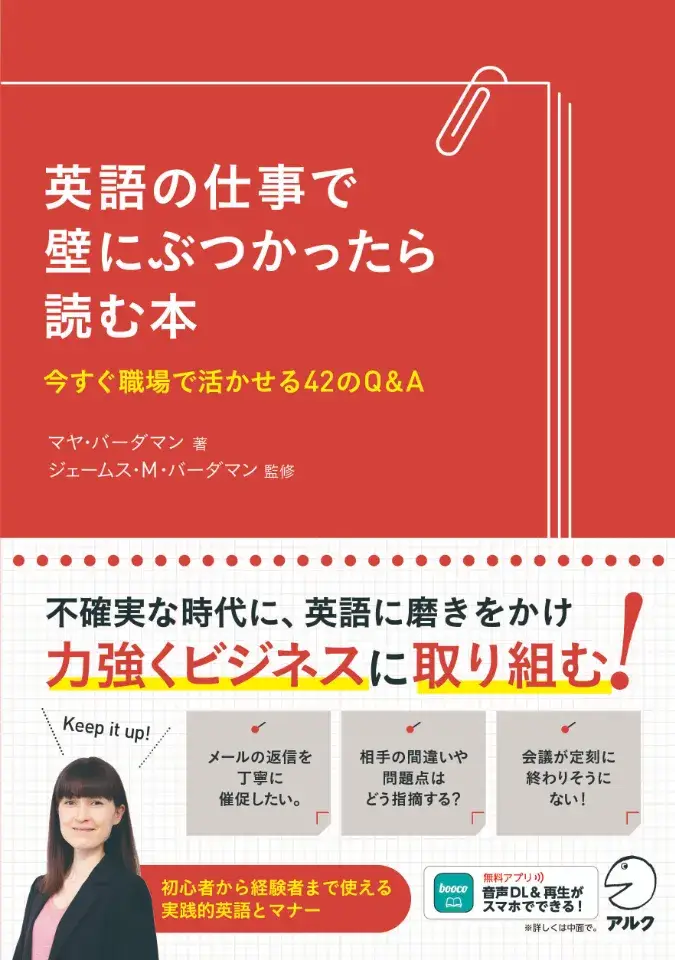テレワークなどで、ウェブでのビデオ会議や電話会議の機会が増えています。顔が見える場合も見えない場合も、通信環境などが 原因 で、直接対面の英会話や英語のビジネス会議とは異なる注意が必要です。何千回と電話会議を通訳してきた同時通訳者の小熊弥生さんによる電子書籍『 「英語で電話会議」の教科書 』から、アドバイスを紹介します。日本語のオンライン会議にも役立つヒントがいっぱいです。

- 作者: 小熊弥生
- 出版社/メーカー: アルク
- 発売日: 2018/11/15
- メディア: Kindle版
- この商品を含むブログを見る
電話会議で気を付けたい英語の単語と発音
「電話会議向きの単語や表現なんてあるの?」と思うかもしれませんね。それが、あるのです!
というのも、電話会議ではどうしても 回線の状況が悪くて相手の言うことが聞き取りにくかったり、こちらの言うことが通じなかったり、という事態が発生 します。
ですから、そのような状況でもできるだけ伝えられるよう、 聞き取りやすい単語や表現を使い、聞き取りやすい発音をする ことを心がけましょう。英語力に自信がある人も、ぜひ気を付けてやってみてください。
改めて 確認しよう">電話会議の状況を 改めて 確認しよう
まず、電話会議にはどのような問題点があるのか、 改めて 確認してみましょう。
- 顔が見えないので、表情から発言内容を補うことができない
- 口が見えないので、口の形から言葉を推測できない
- 誰の声かが分かりにくいので、慣れるまでは発言者の判別が難しい
- 参加者が移動中だったり、自宅にいたりすると、乗り物の音や子どもの声、犬の鳴き声など生活音で発言がかき消されることがある
- 参加者のマイクまでの距離や回線の状況で、音声が途切れることがある
- 参加者の声質や発声がマイクで拾いにくい場合、もごもごして聞き取りにくい
- スライドなどの画像を共有できない場合、耳から得られる情報だけで理解しなければならない
- 対面会議なら、不明点があってもすぐ隣の人に確認できるが、別回線の電話でもない限り難しい
- ネイティブスピーカーが多い会議では、スピードが極端に速く歯が立たない
- ノンネイティブで英語が苦手な人が多い会議だと、なまりが強く理解しにくい
電話会議は、海外出張よりコストも時間もかかりませんが、こうした 問題をあらかじめ想定して適切な準備 をしておかないと、かえって混乱を招き効率が悪くなってしまいます。
特に、 電話会議中に起こった混乱や誤解を解くのには、対面の3倍は 時間がかかる と言われています。ですから、時間や手間がかかっても1回の電話会議で正しく伝えられるよう、入念に準備をしておきましょう。
電話会議は、 メールと違って直接声でやり取り するため、対面会議ほどではないものの、 相手との信頼関係が構築しやすく なります。そのため、メールだけでやり取りするより良好な人間関係を築くことができ、困ったときに助けてもらえることも多くなるのです。
電話会議で英語を話すときの単語や発音について、次に紹介する点に注意しましょう。
キーワードには「音が長い単語」を使う
注意点のひとつ目は、 短い単語を避ける こと。電話会議では、回線の状況が良くなかったり、自宅から参加した人の背景で生活音がしたりして、音が途切れることがよくあります。
そんなとき、短い単語を使って話していると、単語ひとつを丸ごと聞き逃すと理解できなくなり、聞き返すことになるのです。
例えば、あなたが次のような発言をしたとしましょう。
△ Are you done?英語としては何の問題もありませんが、もし、doneのところで回線が途切れたらどうでしょうか?相手はあなたが何を聞きたいのか分かりません。この場合、次のように doneより長いfinished を使えば、相手が聞き取ってくれる 可能性 は高くなります。もう終わりましたか?
Are you finished ?もう終わりましたか?
句動詞を避ける
同じように「聞き漏らしを避ける」という理由から、ネイティブスピーカーがよく使う句動詞も避けたほうがいいでしょう。
句動詞というのは、 do、 make 、have などの基本動詞に前置詞や副詞句を組み合わせて独自の意味を表現するイディオム のこと。do away with ~(~を廃止する)、 make over ~(~を作り替える)など、大学受験のときに覚えたという方も多いのでは?
これらの句動詞は、 動詞も前置詞も音が短く 、どちらかでも聞き漏らすと意味が分からなくなります。ちょっとした回線の 不具合 でも音が途切れ、聞き返されることがあるので避けたほうがいいでしょう。例を挙げてみますね。
put off (延期する)→ postpone
call off(キャンセルする )→ cancel
carry out (実行する)→ execute
turn on (オンにする)→ switch on
go on (継続する)→ continue
look out for (注意する)→ pay attention to
go over (見直す)→ present / review
代名詞ではなく固有名詞を使う
先に 紹介した2つの例は、音が途切れることに対する対策でした。
今度は、「電話会議で相手が見えないことなどによる誤解」を避けるための注意点です。
本来、英語では代名詞を多用し、コミュニケーションの効率を上げています。しかし、電話会議で 代名詞を多用すると何を指しているのか分からなくなり、混乱のもと になってしまうのです。
気心の知れた相手とでも、電話会議のあとでお互い誤解していたことが分かり、あとの祭りということも少なくありません。
話している最中はまどろっこしいと思うかもしれませんが、できるだけ固有名詞を使って、 事前に 誤解を防ぎましょう。
次の例を見てください。
△ Can you make it in time for the promised delivery date ?make it という基本動詞と代名詞の組み合わせを使っていますが、そのように 曖昧に表現するのではなく、 具体的に 言いましょう。約束した納期までに間に合いますか?
例えば、finish building the patch(パッチの構築を終了)や produce the automobiles(自動車生産)といった具合です。
先ほどの例文は、次のようになりますね。
Can you finish building the patch in time for the promised delivery date ?他の例文を見てみましょう。約束した納期までにパッチの構築を終了できますか?
△ Can you please have her call me later?このように、代名詞をできるだけ避けて固有名詞を使うことで、音が途切れた場合にも聞き取りやすくなり、さらに、 誰が聞いても「何をいつ誰がどうするか」が明確 になります。こうすることで、誤解を招かず、混乱を避けることができるのです。あとで彼女から私に電話するようにしてもらえますか?
↓
Mr. Takada , can you please have Takako call me?
高田さん、貴子さんから私に電話するようにしてもらえますか?
can’tやisn’tは使わない
もうひとつ、電話会議で覚えておきたいのが、 (助)動詞+notの短縮形を使わない ことです。
特に、can’t、isn’t、didn’tには注意が必要です。これらの単語の n’tの部分は音がとても短いので、同時通訳者にとっても聞き取りが難しい のです。さらに、n’tがあるかないかで正反対の意味になるのですから、非常に重要です。
難しい上に重要なので、同時通訳の最中、同じブースに入っている他の通訳者に助けてもらうこともあります。メモに「’」と書いて渡してくれたり、指でバツを作って教えてくれたり。いずれも「n’tが付いていますよ」という意味です。
これほど難しく、また重要なのですから、電話会議で発言するときには、できるだけcan’tやisn’tは使わないほうがいいと思います。まず No .と言ってから発言するか、n’tと略さずに、むしろnotを強調して話す ようにしましょう。
「~できません」と言うときは、can’tではなく、cannotと言ったほうがいいということです。
声の大きさは普段の2倍に
次に、声の出し方について考えていきましょう。
通訳として働いていて、 一番多い困り事は「声が小さくて聞こえない」 です。特に電話会議では、声が小さくて聞き取れず、言い直してもらうようにお願いしたことが数え切れないほどあります。
「声の大きさ」はあなたが思う以上に重要です。電話会議に出席するなら、自分のいつもの声の2倍の大きさで話す気持ちで頑張りましょう。
英語に自信がないと、つい声が小さくなってしまう気持ちは分かります。しかし、とにかく相手が聞き取れる音量を出さないことには、会議は始まりません。
発音が多少間違っていても、聞き取れる大きさの声で話して いれば、相手が文脈からあなたの意図を理解してくれる確率は格段に上がります。
発声はできるだけ 腹式呼吸 を行い、おなかの底から声を出して話すようにします。また、日本語で話すときより 感情表現を大げさ にすることで、声のトーンからもあなたの意思が伝わります。
多少日本語が交じっても、発音が悪くても構いませんから、英語に自信がない人ほど、頑張って、大きな声で大げさに話すようにしましょう。
これだけは守りたい発音のルール
先ほど、「英語に自信がなくても大きな声で話そう」と書きました。これはその通りなのですが、 無視できないのは「発音のルール」 です。これを無視してしまうと、あなたの英語に慣れている人には理解できても、そうでない人には分からないという状況になってしまいます。
基本的に「発音ルール」はもちろん守ったほうがいいのですが、発音記号を覚えることにはあまり意味がないと思います。というのも、いくら熱心に発音記号を覚えても、話す瞬間に発音記号を思い出すことはできないからです。
それよりも、ごくシンプルなルールを守って、実際に発音練習をしたほうがいいでしょう。 最低限守りたい6つのルール を挙げましたので、実際にやってみてください。
無声音:前歯の上下の歯で舌を軽くかんでスゥーと息を出す(thank、anything) /有声音:前歯の間に舌を挟みながら「ザー」という音を出す(the、that、 with )
(2) r
舌を巻き上げるのではなく、喉をふさぐように舌を引く。そのときに舌先が口内のどこにも付かないようにする
(3) l(エル)
舌先で前歯の(歯茎の)裏にしっかり触れる
(4) b
上下の唇を閉じた状態から、「ブ」の音を破裂させながらしっかり音を出す
(5) c
「スィー」と息を吐きながら音を出す
(6) p
「プ」の音を破裂させながらしっかり出す
いかがでしたか?『 「英語で電話会議」の教科書 』では、これらの注意点について、さらに多くの例文を紹介しています。
英語の会議で成果を出せる!小熊弥生さんの本
電子書籍 『「英語で電話会議」の教科書』 では、 英語の電話やテレカンファレンスで使える英語フレーズや準備方法 はもちろん、 会議やビジネス一般にも役立つノウハウやヒント を紹介しています。いつでも手元に置いて参照できる手頃な決定版としてご活用ください。
この記事で紹介した内容に加えて、会議の「 設定方法 」「 資料の活用法 」「本番の 流れのシミュレーション 」「相手を 説得する方法 」「 議事録とフォローメール の書き方」「急にアサインされたときの 直前の準備方法 」を網羅。
▼詳細・購入はこちら↓

- 作者: 小熊弥生
- 出版社/メーカー: アルク
- 発売日: 2018/11/15
- メディア: Kindle版
- この商品を含むブログを見る

文:小熊弥生(おぐま やよい)
https://www.sokupera-english.com/opt2/
株式会社ブリッジインターナショナル代表。TOEIC 280点から、独自の勉強法で半年後にTOEIC 805点を 取得 。短大卒業から3年半で通訳者デビュー。現在は自身の経験をベースにした英語学習サービスを 展開 。ひとりひとりの目的に合った効果的な学習プログラム作りを指南し、のべ1000人以上の英語力アップに貢献している。
速ぺらEnglish :著者がTOEIC 280点から各国首脳の同時通訳を担当するまでに実践した英語勉強法を伝授する、リスニング力とスピーキング力アップに特化したプログラム。
【トーキングマラソン】話したいなら、話すトレーニング。
語学一筋55年 アルクのキクタン英会話をベースに開発
- スマホ相手に恥ずかしさゼロの英会話
- 制限時間は6秒!瞬間発話力が鍛えられる!
- 英会話教室の【20倍】の発話量で学べる!