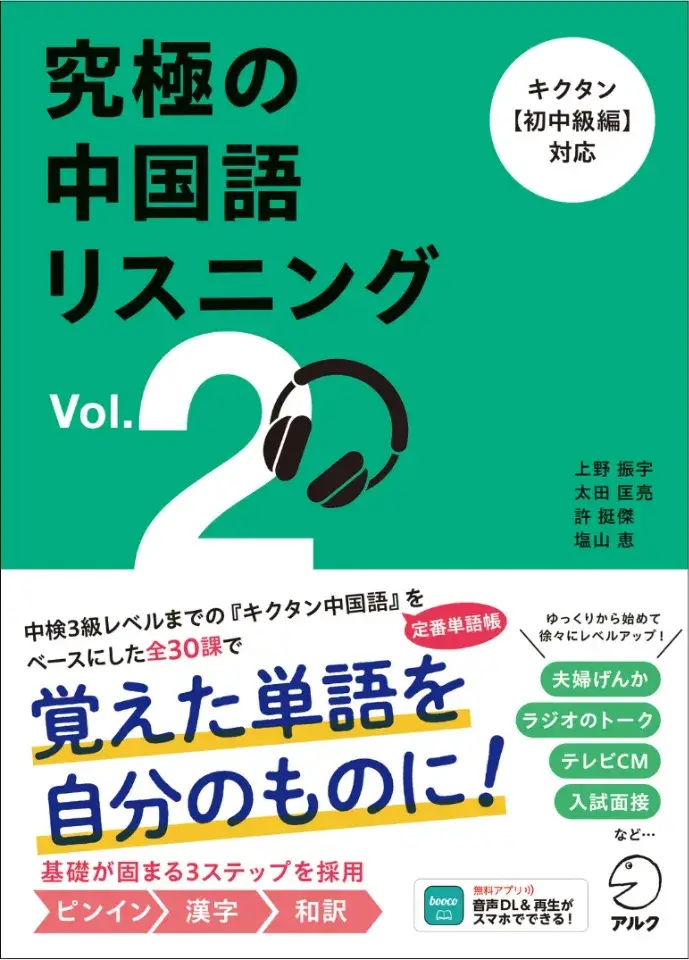世界を相手にビジネスを行うためには、英語力だけでなく、多様な文化を受け入れるグローバルマインドセット、つまり視野の広いもののとらえ方が必要となります。本コラムでは経営コンサルタントのロッシェル・カップさんに、グローバルマインドセット獲得のヒントを教えていただきます。
改善 しないのは能力が低いから!"> 改善 しないのは能力が低いから!
現在、会社のハンガリーの工場に赴任中のあなたは、現地採用の部下に対してとてもいら立っています。
彼は常に同じことをやり続けているだけでOKだと思っているように見え、違った方法を導入して、絶えず 改善 していく 改善 活動の必要性を分かっていないようです。
このような状況では、どのように対応するのが最も適切でしょうか?
つまり、「日本人のように 改善 をしないから、日本人よりもレベルが低い」などと決めつけてしまうのです。また、その部下は 改善 ができないと 判断 し、代わりに自分で 改善 活動を計画し、それを実行することをハンガリー人の部下に一方的に強要するという【b】の選択肢も、似たようなものです。しかしそのような行動を取ると、現地採用者の間で参加意識が生まれず、モチベーションの低下に繋がってしまいます。
改善 しない?">ハンガリー人はなぜ 改善 しない?
「 改善 しようとしない」ハンガリー人部下の行動の背景には、何があるのでしょうか? その鍵となるのは、「変化に対する態度」かも知れません。

上記の表で左側に位置する文化ほど、伝統を大切にし、現状維持を好む 傾向 があります。「壊れていないものを直す必要はない」と考えますので、やり方を 改善 して変えるよりも、従来のやり方に沿った方が良いと感じています。過去を模範として捉え、迅速な変化は好みません。
一方、右側の文化は、進歩と新規性を重視します。つまり、新しい方が良いと思っています。 過去よりも将来に目を向け、迅速な変化を好みます。
変化に対するスピード感覚が違う
このスケールで、日本はちょうど真ん中に位置します。急激な変化は好みませんが、持続的で着実な変化を歓迎します。「カイゼン」という概念を生み出した文化ですから。
日本人にとって 改善 が望ましいのは当たり前のことですが、右側の文化の人にとっては、それでは変化のスピードが遅過ぎるかもしれません。反対に左側の文化の人は、 改善 の必要性を感じないかもしれません。ハンガリーは左側にある文化なので、おそらくこのケースのハンガリー人従業員は、 改善 を求める上司の態度に戸惑っているはずです。「すでに素晴らしい品質なのに、なぜ変化が必要なのだろうか?」と思っているかもしれません。
このケースのような状況で、最も適切な対策は【c】です。ハンガリー人の部下は今までに、 改善 という概念に出合ったことがないかもしれませんし、そのような方法になじみがないかもしれません。しかし、それが なぜ求められるかを論理的に説明すれば、身に付けて実行しようと努力してくれるかもしれません 。ぜひトライしたいことです。
こちらもおすすめ!
ロッシェル・カップさんの本

- 作者: ロッシェルカップ,大野和基
- 出版社/メーカー: 集英社インターナショナル
- 発売日: 2017/08/07
- メディア: 新書
![]() 反省しないアメリカ人をあつかう方法34 (アルク はたらく×英語シリーズ)
反省しないアメリカ人をあつかう方法34 (アルク はたらく×英語シリーズ)- 作者: ロッシェル・カップ
- 出版社/メーカー: アルク
- 発売日: 2015/12/24
- メディア: 単行本
![]() 日本企業がシリコンバレーのスピードを身につける方法
日本企業がシリコンバレーのスピードを身につける方法- 作者: ロッシェル・カップ,到津守男,スティーブ・マギー
- 出版社/メーカー: クロスメディア・パブリッシング(インプレス)
- 発売日: 2017/07/18
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
![]() 日本企業の社員は、なぜこんなにもモチベーションが低いのか?
日本企業の社員は、なぜこんなにもモチベーションが低いのか?- 作者: ロッシェル・カップ
- 出版社/メーカー: クロスメディア・パブリッシング(インプレス)
- 発売日: 2015/01/30
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (2件) を見る
編集:GOTCHA!編集部![]()
執筆:ロッシェル・カップ
ジャパン・インターカルチュラル・コンサルティング社 社長。
異文化コミュニケーションと人事管理を専門とする経営コンサルタントとして、日本の多国籍企業の海外進出とグローバル人材育成を支援している。イェール大学歴史学部卒業、シガゴ大学経営学院卒業。日本語が堪能で、『 反省しないアメリカ人をあつかう方法34 』(アルク)、 『英語の品格』 (集英社) をはじめ、著書は多数。朝日新聞等にコラムも連載している。【1000時間ヒアリングマラソン】 ネイティブの生英語を聞き取る実践トレーニング!
![]()
大人気通信講座が、アプリで復活!
1982年に通信講座が開講されて以来、約120万人が利用した「ヒアリングマラソン」。
「外国人と自由に話せるようになりたい」「仕事で困ることなく英語を使いたい」「資格を取って留学したい」など、これまで受講生のさまざまな夢を支えてきました。アプリ版「1000時間ヒアリングマラソン」は、日常、ビジネス、フリートーク、時事英語、物語などの多彩なジャンルのコンテンツを収録し、さらに豊富なアウトプット練習や学習時間の計測などの機能を盛り込み、よりパワーアップして復活しました。
「本物の英語力」を目指す人に贈る、最強のリスニング練習
学校では習わない生きた英語
実際にネイティブスピーカーと話すときや海外映画を見るとき、教科書の英語と「生の英語」のギャップに驚いた経験はありませんか? 「1000時間ヒアリングマラソン」には、オリジナルドラマやラジオ番組、各国の英語話者のリアルな会話など、学校では触れる機会の少ない本場の英語を届けるコーナーが多数用意されています。
こだわりの学習トレーニング
音声を聞いてすぐにスクリプトを確認する、一般的なリスニング教材とは異なり、英文や日本語訳をあえて後半で確認する構成にすることで、英語を文字ではなく音から理解できるようにしています。英文の書き取りやシャドーイングなど、各トレーニングを一つずつこなすことで、最初は聞き取りが難しかった英文も深く理解できるようになります。
あらゆる角度から耳を鍛える豊富なコンテンツ
なぜ英語が聞き取れないのか? には理由があります。全15種類のシリーズは、文法や音の規則、ニュース英語など、それぞれ異なるテーマでリスニング力強化にアプローチしており、自分の弱点を知るきっかけになります。月に一度、TOEIC 形式のリスニング問題を解いたり、書き取りのコンテストに参加したりすることもできるため、成長を定期的に確認することも可能です。
「1000時間ヒアリングマラソン」は、現在7日間の無料トライアルを実施中です。さあ、あなたも一緒にランナーになりませんか?