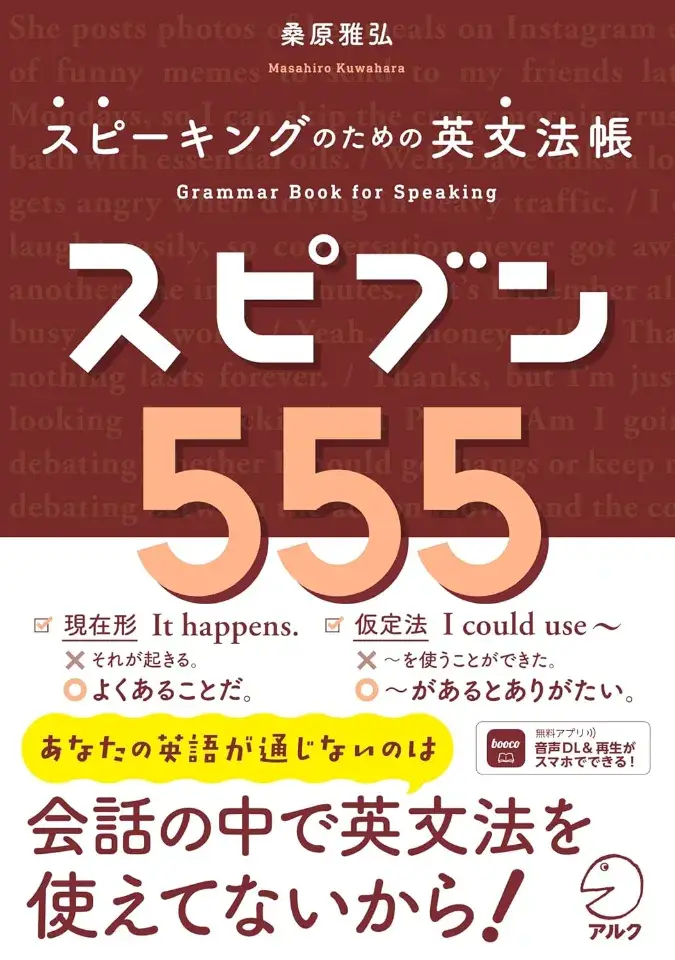人気YouTubeチャンネル「こたせな (KOTATSU&SENA)」 で知られる兄妹、たつやさんとせなさん。彼らの母・濱田まゆみさんによる著書『世界を友だちにする 英語キッズの育て方』(アルク刊)では、家庭でのユニークな英語教育や子育て哲学が紹介されています。今回は、その“実際のところ”を本人たちに根掘り葉掘りインタビュー。英語と日本語の間で育ち、自分の夢を見つけて突き進むふたりが語る、子ども時代のリアルとは――。
目次
こたせなはどう育った?人気の背景とリアルな歩み
ただいま人気急上昇中のYouTubeチャンネル「こたせな (KOTATSU&SENA)」は、現在 約744万人の登録者(6月24日時点)を抱え、動画の総再生回数は 約7.52億回 にも上る国内外問わず注目のYouTube兄妹チャンネルです。
その人気の背景には、英語と日本語を自在に使い分ける自然な会話力や、視聴者の共感を呼ぶ発信スタイルがあります。では、そんな彼らの“英語キッズ時代”は、実際どのようなものだったのでしょうか。
今回は、書籍『世界を友だちにする 英語キッズの育て方』にも登場するたつやさんとせなさんご本人に、当時の暮らしや体験についてじっくりとお話を伺いました。
家で英語、外では日本語だったってホント?

――小さい頃、ご家庭では英語、外では日本語という環境だったそうですが、実際はどのような感じでしたか?
たつや:僕の場合、家庭内では7割くらいが英語でした。昔のホームビデオを見ても、英語で話している場面が多いんです。親も英語で返してくれることが多かったですし、家で流れていた音楽や映画、アニメもほとんどが英語でした。特に覚えているのは、父が車で送り迎えをしてくれるときにかかっていたボン・ジョヴィやカーペンターズの曲です。ほとんど英語の曲しか聴いていなかったと思います。
せな:私も同じような感じで、よく覚えているのは海外ドラマの『24』が家でよく流れていたことです(笑)。それから、小学校高学年くらいになると、日本語の番組もよく見るようになりました。『ワンピース』や『ガキ使』、他にもバラエティー番組などですね。そこから日本語の割合が一気に増えたように思います。
――英語と日本語が混ざって、混乱するようなことはありましたか?
たつや:僕はとにかく日本語が苦手でした。英語と日本語では文法がまったく違いますし、生活も英語中心だったので、日本語の感覚が身につかず混乱してしまって。会話も本当に苦手でした。むしろ英語の方が自然に話せたくらいです。たとえば、「電車に乗る」と言いたいところを、“take the train”を直訳して「電車を取ってくるね」と言ってしまったり。英語の構文をそのまま日本語に当てはめてしまって、ごちゃごちゃになっていました。
せな:私もそうでした。でも、特に困ったり恥ずかしいと思ったことはなかったです。そういう環境が当たり前だったので。
――幼稚園に入ってから日本語が優勢になって、家でも日本語を話すようになったと思いますが、「やめなさい」と注意されたことなどはありませんでしたか?
せな:少し覚えているのは、私が日本語で一方的に話していると、母が「それ英語でどう言うの?」と軽く促してくれることがあったことです。でも、保育園での出来事をどうしても伝えたくて、日本語で夢中になって話していました。注意されたり怒られたりしたことはありませんでした。
――それで、徐々に日本語が優勢になっていったのですね。
せな:はい。今は英語と日本語、どちらも同じくらいのレベルだと思っています。日本の学校に通ったことで一時期は英語がかなり下手になってしまったんですが、高校や大学でまた英語力が戻ってきて、現在はバランスのとれたバイリンガルになれたかなと、自分でも思います。
――ご自身で「バイリンガルだ」と自覚されたのはいつ頃からですか?
たつや:全然意識してなかったですね。大人になってからようやく、「英語が話せるって強みになるんだ」と気づいたくらいで、当時はありがたみもまったく感じていなかったです。
せな:インターナショナルスクールに通っていたので、周囲にもいろんな言語を話す子がたくさんいました。だから、自分が特別だという感覚はまったくなかったです。英語を話せるのが当たり前のような空気で、みんな多言語を話すことが普通でした。授業もすべて英語だったので、自然と英語で考えたり話したりする癖がついていたと思います。
たつや:本当にそうですね。授業は基本的に英語で、先生への質問も友達との会話もすべて英語でした。日本語を話す機会が少なかったので、いざ使おうとすると、ぎこちなさを感じることも多かったです。たとえば、母のことを“マム(Mom)”と呼んでいて、友達に「まだママって呼んでるの?」と笑われたこともあり、英語と日本語の文化の違いを実感しました。
インターにも日本の学校にも通ったってホント?

たつや:僕は5歳からインターに通っていました。夏休みになると、日本の小学校に1カ月半くらい通っていたんです。インターの夏休みは日本より早くて6月上旬には始まるので、その期間に“転校”のような形で地元の小学校に行っていました。3〜4年ほど続けていましたが、あれはあれで楽しかったです。
――どうして行こうと思ったんですか?
たつや:もともと学校が特別好きだったわけではないんですけど、日本の学校には文化祭や体育祭などの行事があるじゃないですか。そういうのに憧れていたんです。なので、高校のときには真剣に日本の学校への転校を考えていました。実際に学校も探していたんですが、今通っているインターから日本の学校への転校は難しくて、結局そのまま卒業しました。
――せなさんはどうでしたか?
せな:私は正式に日本の学校に編入しました。小6から中2の1学期まで通っていました。近所の子たちがみんな日本の公立校に通っていて、話題がまったく違ったんです。「今日こんな歴史を習った」といった話題になると、私にはまったくわからなくて。「日本人なのに日本のことを知らなすぎる」と焦ったのがきっかけでした。
――自分から「行きたい」と?
せな:そうです。本当は兄のように夏休みだけ通いたかったんですが、私の時代にはその制度がなくなっていたようで、編入するしかありませんでした。最初は1年間の予定でしたが、思ったよりも楽しくて中2まで通いました。ただ、そのうち「将来に活かせるのはどちらだろう」と考えるようになり、最終的にはインターに戻ることに決めました。
――日本の学校で印象的だったことは?
たつや:やはり人数の多さですね。インターは1学年に30人ほどしかいないので、ずっと同じメンバーなんです。文化祭や体育祭も規模が小さくて、日本の学校のにぎやかな行事には強い憧れがありました。
せな:私は暗記がとても苦手だったので、テストが大変でした。通知表の平均は60点くらいでしたね。英語と数学は得意でしたが、それ以外の教科はついていけませんでした。でも、協調性はとても身についたと思います。逆に、それがつらく感じたこともありましたけど(笑)。
「やりたいことは何でもやらせてもらった」はホント?

――小さい頃、「これをやってみたい!」と思ったことってありましたか?それを実際にやらせてもらえた記憶ってありますか?
たつや:僕、自分から「これやりたい」と積極的に言うタイプではなかったと思うんですけど、言ったときには「いいよ」と基本的に受け入れてもらえていました。たとえば、大学は関西学院大学に行く予定でしたが、「俳優になりたいから演技の学校に進みたい」と伝えたときもOKしてくれました。ただし、「やらせてあげるけど、そのあとは自分で責任を持ちなさいね」というスタンスでしたね。
――止められたことはなかった?
たつや:一度もありませんでした。むしろ「これもやってみたら?」と提案されることもありました。ピアノはあまり好きではなかったのですが、「ピアノをやるならこれもやっていいよ」といった条件付きで勧められたり(笑)。
せな:私はかなり好奇心旺盛で、水泳、空手、ピアノ、バイオリン、学習塾など、いろいろ挑戦しました。どれも自分から「やってみたい」と言って、親も「いいよ」と受け入れてくれました。強く背中を押されたというよりは、反対されることが一度もなかった、という感じです。
――その育てられ方が、今にどう影響していると思いますか?
たつや:「自分でやらなきゃ始まらない」という行動力は、強く身についたと思います。やると決めたら資金面のサポートはしてくれましたが、あとは自分でやる、という環境でした。
せな:「やらなかった後悔」がないですね。やりたいと伝えればやらせてもらえたので、「親に止められたからできなかった」と感じたことが一度もありません。逆に、自分から言わなかったことは自分の責任と捉えるようになったので、「やりたいことは今からでもやろう」と前向きに考えるようになりました。
どんな未来を叶えたい?

――子どもの頃の夢はどんなものでしたか?
たつや:小5のとき、「俳優になりたい」と作文に書いたことがあります。発表したらクラスで笑われて、「夢って笑われるんだ」とすごく悔しかったんです。だから「いつか見返してやる」という気持ちが強くなって、それがずっと原動力になっています。
――それからずっと変わらず?
たつや:はい、まったくブレていません。高校生のときも大学進学の話があったものの、自分の中では俳優一本に絞っていました。関学には進学せず、俳優の道に進みました。
せな:私は何度も夢が変わりました(笑)。お花屋さん、カメラマン、弁護士・・・いろんな夢があって、どれも本気で目指していました。行動しながら「これは違う」「やっぱりこれがいい」と試行錯誤していた感じですね。今はアイドルを目指しています。
――アイドルを目指すきっかけは?
せな:最初はBTSやBLACKPINKなどのK-POPに影響を受けて、「こんなふうに表現できたら素敵だな」と思ったことがきっかけでした。歌って踊るだけでなく、音楽を通じて愛や平和、あたたかい気持ちを届けられる人になりたいと思うようになりました。見てくれた人が「明日も頑張ろう」と思えるような存在になれたらと思っています。
――その夢に向けて、日々意識していることや心がけていることはありますか?
たつや:僕は直感を信じることですね。「やってみたい」と思ったときは、まず行動してみる。そのスピード感に助けられてきたことが何度もあります。たとえば、妹が東京にいたとき「これ絶対バズる」と思ってすぐ連絡して大阪に来てもらって撮影したら、本当にバズった、ということもありました。
せな:私は「愛を持つこと」ですね。少し大げさかもしれませんが(笑)、音楽を通して社会の不条理にもメッセージを届けられたらと思っています。全員がそう思ってくれなくても、自分はそういう姿勢でいたいです。
こたせなの本が出たとき、どう思った?

――最後に、お母さまの本が出版されたとき、どう感じましたか?
たつや:まず単純に、「母と一緒に本を作れた」ことがとてもうれしかったです。濱田家の子育てが形として残るのは、本当にすごいことだと思いました。子どもの頃から、母が教材を作っている姿をそばで見ていたので、それに少しでも関われたのは感慨深いです。しかも、今回は僕や妹の声がそのまま反映されていて、「この経験が誰かの役に立つかもしれない」と思えるのがうれしいです。
せな:私は、「この本が正解だと思わないでほしい」と感じています。書かれていることは、私たちにとってうまくいったやり方ではあるけれど、それがすべての人に当てはまるとは限らないと思っています。ただ、こういう子育ての形もあるんだ、という新しい視点のひとつとして、読んでくれた方に受け取っていただけたらうれしいです。特に、完璧じゃなくても大丈夫なんだって、少しでも肩の力を抜いてもらえたらいいなと思います。
英語が話せるって、こういうことだったのか

――『世界を友だちにする 英語キッズの育て方』
「こたせなって、なぜあんなに自然に英語を話せるの?」——そんな疑問を持った方にこそ手に取ってほしい一冊が、濱田まゆみさんの著書『世界を友だちにする 英語キッズの育て方』です。
インタビューでも語られたように、2人の英語力は“特別な才能”ではなく、“日々の選択”の積み重ねから生まれたもの。そこには「英語=教科」ではなく、「英語=生きる言葉」として向き合ってきた家族の物語があります。
バイリンガル教育に興味がある方、ことばを通して世界を広げたい方、そしてこたせなをもっと知りたい方——この本は、あなたの「視点」を変えてくれるかもしれません。
●『世界を友だちにする 英語キッズの育て方』
濱田まゆみ 著
アルク