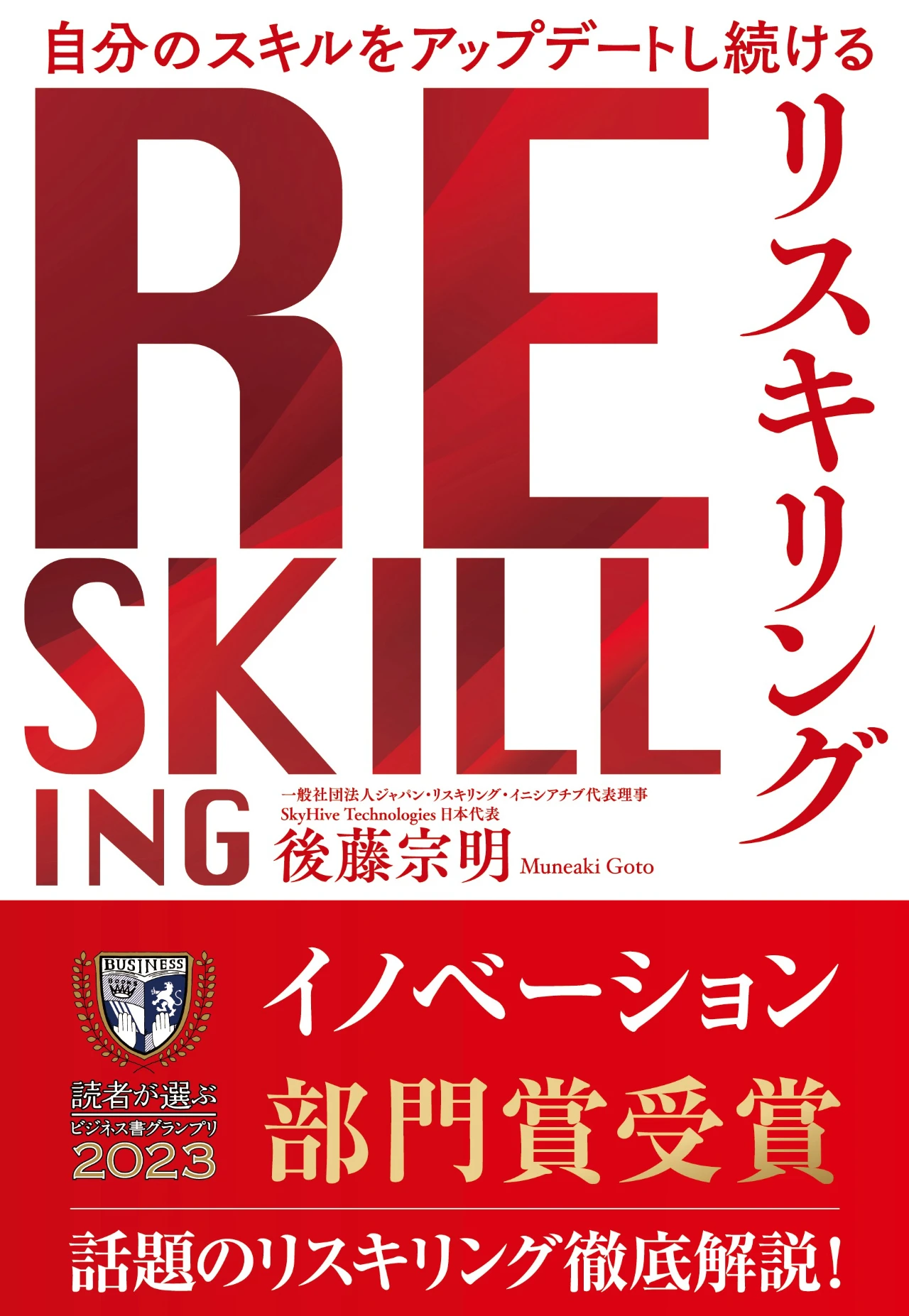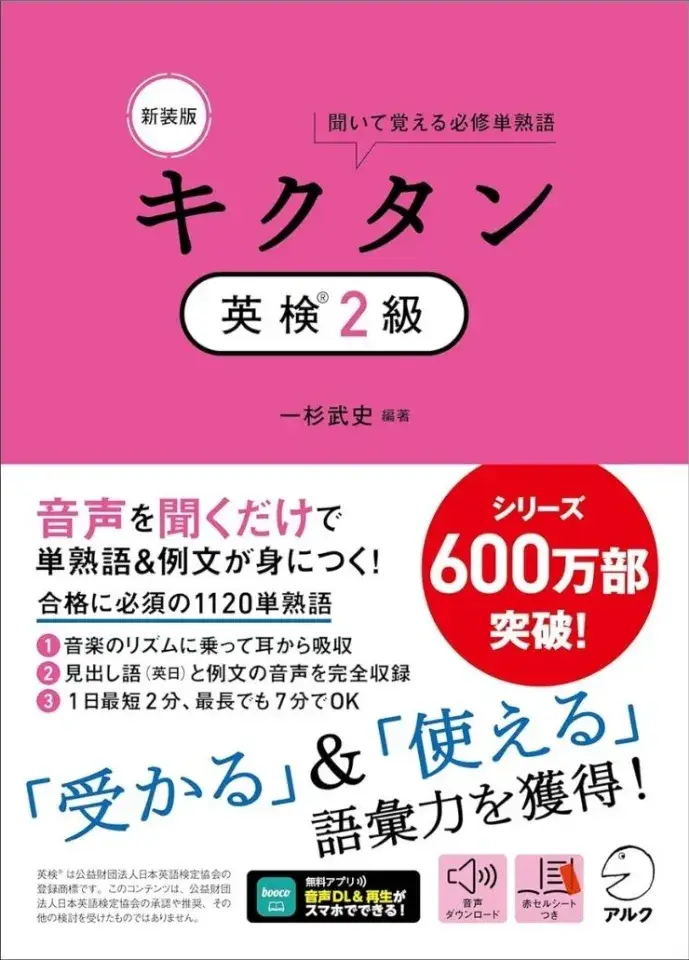日本で初めて、リスキリングに特化した非営利団体を設立した後藤宗明さんに英語リスキリングのメリットやおすすめの英語学習法についてお話しいただきます。第1回は、正しい「リスキリング」の理解と、今注目される理由について紹介します。
人生二度のリスキリング
皆さん初めまして、一般社団法人ジャパン・リスキリング・イニシアチブ代表理事の後藤と申します。日本でリスキリングを正しく広めるための政策提言や導入支援を行なっています。なぜリスキリングを広めている人が英語に関する連載をするの?と思われる方もいらっしゃると思うので、少しだけ自己紹介をさせてください。実は、大学4年生当時の内定式の際に受験した僕のTOEICの点数は380点でした。『TOEIC(R)テスト超入門キット』というアルクのCD教材を人事部からもらったことを今でも鮮明に覚えています。
僕は今まで人生2度、大きなリスキリングを経験しています。一度目は30代のとき、国内での仕事から海外での仕事にシフトしました。日本社会を飛び出して海外で働きたいと思うようになり、真剣に英語学習を頑張って、海外移住を実現しました。2度目は40代のとき、アナログな仕事からテクノロジーの分野にキャリアチェンジしました。その当時は「自分はリスキリングしてるんだ」なんていう感覚はなく(米国でリスキリングという言葉を知ったのは2016年のことでした)、生きていくために必死だっただけなのですが、振り返ってみると、仕事を通じて人生2回のリスキリングを行なっていたのだと言えます。
リスキリングとは、個人の自主的な学び直しではない
リスキリング(reskilling)は、リスキル(reskill)という他動詞が元になっていて、「(労働者)に(新しい)スキルを再習得させる」という意味になります。そのため、主語が組織、動詞がリスキル、目的語が従業員になるので、「組織が従業員をリスキルする」という使われ方をします。例えば企業の新しい事業戦略に基づいて、従業員の職業能力の再開発を行う、それがリスキリングの意味になります。これを働く私たちの視点に置き変えてみると、リスキリングとは、
「新しいことを学び、新しいスキルを身に付け実践し、新しい業務や職業に就くこと」
と言えます。日本ではデジタル人材育成に向けてリスキリングが注目された経緯がありますが、海外でリスキリングが注目され定着した理由は、technological unemployment(技術的失業)を防ぐために広まった経緯があります。技術的失業とは、テクノロジーの導入によりオートメーション化が加速し、人間の雇用が失われる社会的課題を指します。デジタル化が進む中で業務が自動化されていくので、なくなっていく仕事から成長分野の事業で仕事ができるようにリスキリングすることが求められているのです。
リカレント教育やスキルアップとの違い

今、日本ではリスキリングに「学び直し」という和訳が付きますが、この学び直しという誤った和訳が、大きな誤解を生み出しているように思います。その誤解の原因の一つは、リカレント教育とリスキリングを混同していることです。リカレント教育は、「人生100年時代に個人の関心に基づいて、時間と費用の捻出を行う学び直し」を指します。ところが、リスキリングは前述のように、企業などの組織が自社の変革に合わせて実施するもので、大きく異なるものなのです。
また、日本語で私たちが使ってきた従来型のスキルアップとの混同も多く見られます。まずスキルアップという言葉は和製英語で、海外では通用しない言葉です。英語では、スキルとアップがひっくり返ったアップスキリング(upskilling)という言葉が日本語のスキルアップに当たります。これは、例えば経理部で働いている方がより高度な経理のスキルを身に付けるといった、今までの延長上で上に行くイメージ、これがアップスキリングです。人事部が行ってきた従来型の研修もこれに該当します。
ところが、リスキリングは新しいことを学び、なくなっていく仕事から新しく生まれる成長事業で働くことを目的としているので、従来型の研修やOJT(on-the-job training)ではカバーすることが難しいのです。そのため、個人の自助努力では追いつけない急激な環境変化に対応するために、海外では国や地方自治体、企業が主体となって、なくなっていく業務、仕事から成長分野の業務や職業に就くことができるように、働く人々の支援をしているのです。
グローバル分野のリスキリングが注目される理由
リスキリングは成長事業への労働移動を実現するためのものなので、現時点ではデジタル分野のキャリアに就くこととほぼ同義で使われることが多いのですが、実はグローバルに活躍する人材を育成していくためのリスキリングが今改めて注目されているのです。デジタル化に出遅れ、大規模なイノベーション創出が起きづらい日本において、経済成長における外貨獲得のために、輸出競争力、観光産業の強化が求められています。
特に2023年になって新型コロナウイルス感染症が収束し、海外との交流が再開した現在、インバウンド観光や輸出機会の増大を担う人材の育成が急務となっているのです。少子高齢化に突き進む日本においては、デジタルツールを使いこなして海外とのグローバルな業務ができる人材の創出がかつてなく求められています。そのため、英語は単なる学ぶ対象ではなく、グローバルコミュニケーションという重要なスキルを身に付けるための入口として今まで以上に重要なのです。
次回から、デジタル分野とグローバル分野で活躍するために必要なリスキリングについてお伝えしていきますので、どうぞお楽しみに!
後藤宗明さんの本
「自分のスキルをアップデートし続ける『リスキリング』」
本連載で紹介する「英語に関するリスキリング」を含む、リスキリングの概要と実践するための方法をまとめた書籍『自分のスキルをアップデートし続ける リスキリング』が好評発売中です。
【1000時間ヒアリングマラソン】 ネイティブの生英語を聞き取る実践トレーニング!

大人気通信講座が、アプリで復活!
1982年に通信講座が開講されて以来、約120万人が利用した「ヒアリングマラソン」。
「外国人と自由に話せるようになりたい」「仕事で困ることなく英語を使いたい」「資格を取って留学したい」など、これまで受講生のさまざまな夢を支えてきました。
アプリ版「1000時間ヒアリングマラソン」は、日常、ビジネス、フリートーク、時事英語、物語などの多彩なジャンルのコンテンツを収録し、さらに豊富なアウトプット練習や学習時間の計測などの機能を盛り込み、よりパワーアップして復活しました。
「本物の英語力」を目指す人に贈る、最強のリスニング練習
学校では習わない生きた英語
実際にネイティブスピーカーと話すときや海外映画を見るとき、教科書の英語と「生の英語」のギャップに驚いた経験はありませんか? 「1000時間ヒアリングマラソン」には、オリジナルドラマやラジオ番組、各国の英語話者のリアルな会話など、学校では触れる機会の少ない本場の英語を届けるコーナーが多数用意されています。
こだわりの学習トレーニング
音声を聞いてすぐにスクリプトを確認する、一般的なリスニング教材とは異なり、英文や日本語訳をあえて後半で確認する構成にすることで、英語を文字ではなく音から理解できるようにしています。英文の書き取りやシャドーイングなど、各トレーニングを一つずつこなすことで、最初は聞き取りが難しかった英文も深く理解できるようになります。
あらゆる角度から耳を鍛える豊富なコンテンツ
なぜ英語が聞き取れないのか? には理由があります。全15種類のシリーズは、文法や音の規則、ニュース英語など、それぞれ異なるテーマでリスニング力強化にアプローチしており、自分の弱点を知るきっかけになります。月に一度、TOEIC 形式のリスニング問題を解いたり、書き取りのコンテストに参加したりすることもできるため、成長を定期的に確認することも可能です。
「1000時間ヒアリングマラソン」は、現在7日間の無料トライアルを実施中です。さあ、あなたも一緒にランナーになりませんか?