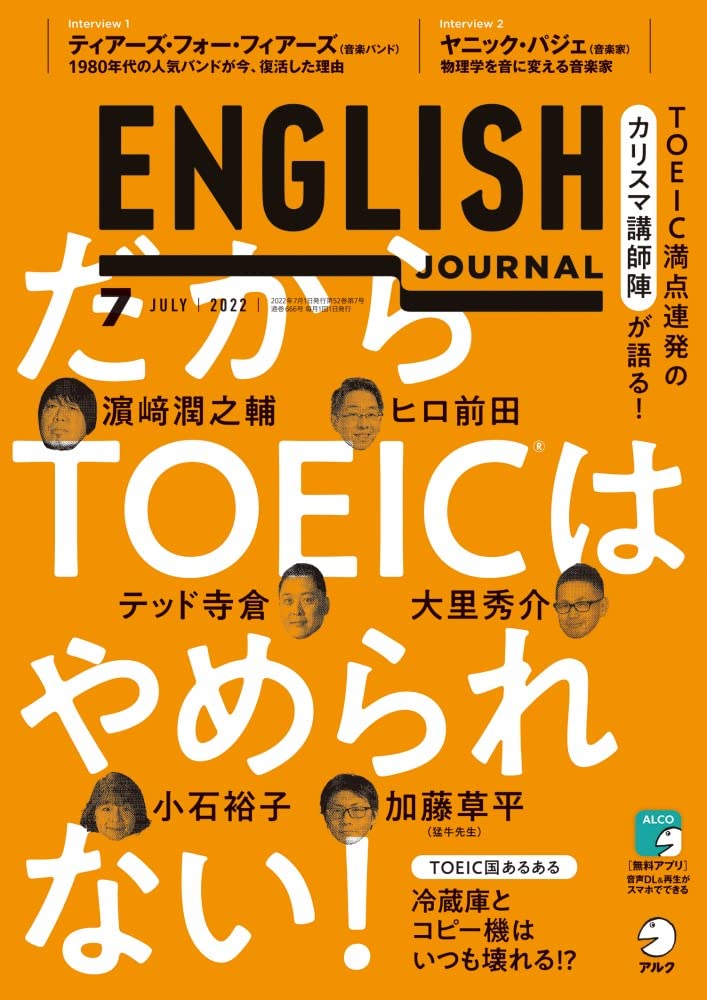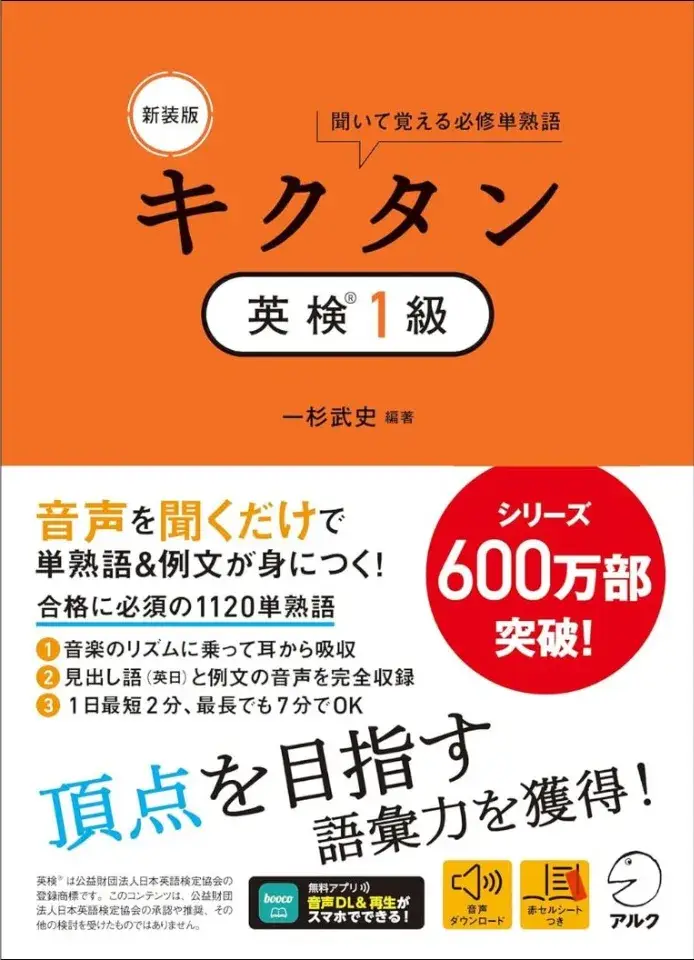写真:MARIO ANZUONI/ロイター
アルクの月刊誌『ENGLISH JOURNAL』は、毎月、さまざまな分野で活躍する方々の生の声をお届けしています。2022年7月号に登場するのは、今年2月に17年5カ月ぶりの最新アルバム『The Tipping Point』をリリースしたティアーズ・フォー・フィアーズ。1980年代に「シャウト」「ルール・ザ・ワールド」などの大ヒット曲を飛ばした彼がたどってきた道のり、音楽市場の変化、人生の次のフェーズに音楽で何を伝えていきたいかなどを語ります。
The Tipping Point ~ 結成から30年以上を経たバンドの「転換点」
第2次ブリティッシュ・インヴェイジョンと呼ばれた音楽ブームがある。1980年代前半、アメリカのポップ・シーンにおいて、イギリスのグループが次々に大ヒットを飛ばした現象だ。
第2次と言われるからには第1次があり、60年代半ばにビートルズやローリング・ストーンズ、デイヴ・クラーク・ファイヴ、キンクス、アニマルズなどのロックバンドが人気を集めた。
対して第2次は、テレビの音楽専門チャンネルMTVの成功に由来する面が大きく、時代的にニュー・ウェーブやシンセポップ・スタイルのアーティストが多い。ヒューマン・リーグ、デュラン・デュラン、カルチャー・クラブ、ユーリズミックス、ワム!、ABCなどがその一部だ。当時の洋楽を聴いていた人なら、必ず知っている名前だろう。
そんなムーブメントにあって、1985年に「Everybody Wants to Rule the World」「Shout」を連続で全米ナンバー1(イギリスではそれぞれ2位と1位)にランクさせ、一躍トップグループに躍り出たのがティアーズ・フォー・フィアーズ(TFF)である。
この2曲を含むアルバム『The Songs?from the Big Chair』は、英米アルバムチャート首位を獲得した。
メンバーのローランド・オーザバルとカート・スミスは、イギリスのバースに住む幼なじみで、以前から一緒にバンドを組み、1979年に結成したグラデュエイトで初レコーディング。それが短命に終わり、1981年に4人組TFFでデビューした。
グループ名は心理学者アーサー・ヤノフの著書『Prisoners of Pain』の章題に由来。1983年発表のファーストアルバム『The Hurting』は、全英チャート首位を記録している。
1989 年の3 作目『The Seeds of Love』からのシングル「Sowing The Seeds of Love」は、中期ビートルズをほうふつさせるサイケデリックなサウンドが話題になり、全英5位/全米2位と再びヒットした。
その後ローランドのソロ・プロジェクトと化した時期もあったが、2004年にコンビとして復活。ニューアルバム『The Tipping Point』は、それ以来の作品となる。
7月号のInterview 1はティアーズ・フォー・フィアーズ
ENGLISH JOURNAL 2022年7月号のInterview 1には、TTFのメンバーの1人、ローランド・オーザバルが登場。彼らは今年2月に17年5カ月ぶりの最新アルバム『The Tipping Point』をリリースして、注目を集めています。
1980年代を知る世代にとって懐かしいこのバンドも、若い世代にとっては「新しい発見」となっているようです。それを可能にした音楽市場の変化や、時間をかけてアルバム作りをしていた間に自身が経験した数々の個人的な出来事、そして現代の社会に向けて相棒のカート・スミスと共にどんな思いを込めてアルバムを制作したのかが、語られます。
Very thankfully and very luckily, the market has changed so that social digital media and streaming has created a irenaissance for us, and a lot of people are discovering us for the first time.
非常に運のいいことに、市場が様変わりして、デジタルのソーシャルメディアとストリーミング(・サービス)のおかげで、私たちにとってのルネサンスのようなことが起こりました、たくさんの人たちが私たちを初めて発見してくれたのです。
Because we’re no longer kids, we’re not blaming the establishment, because we are the establishment. We’re older than most of the leaders in the world, you know. And so we feel it’s our job to reflect back to society what is actually going on, and do it in a rnon-judgemental way such that the listener can judge for themselves how they feel about what is going on.
私たちはもう若者ではないので、体制を責めはしません、私たちもその体制側なのですから。世界のほとんどのリーダーたちよりも年上なのですからね。だからこそ、今、実際に何が起きているのかを映し出して見せること、それも、断定的ではないやり方で、起きていることを聞き手自身がどう感じるか判断できるようにすることが、私たちの仕事だと感じています。
ENLGISH JOURNALで、音声、スクリプト、和訳付きで、このロングインタビューを存分にお楽しみください。
動画が見えない場合は、YouTubeに移動してご覧ください。
【1000時間ヒアリングマラソン】 ネイティブの生英語を聞き取る実践トレーニング!

大人気通信講座が、アプリで復活!
1982年に通信講座が開講されて以来、約120万人が利用した「ヒアリングマラソン」。
「外国人と自由に話せるようになりたい」「仕事で困ることなく英語を使いたい」「資格を取って留学したい」など、これまで受講生のさまざまな夢を支えてきました。
アプリ版「1000時間ヒアリングマラソン」は、日常、ビジネス、フリートーク、時事英語、物語などの多彩なジャンルのコンテンツを収録し、さらに豊富なアウトプット練習や学習時間の計測などの機能を盛り込み、よりパワーアップして復活しました。
「本物の英語力」を目指す人に贈る、最強のリスニング練習
学校では習わない生きた英語
実際にネイティブスピーカーと話すときや海外映画を見るとき、教科書の英語と「生の英語」のギャップに驚いた経験はありませんか? 「1000時間ヒアリングマラソン」には、オリジナルドラマやラジオ番組、各国の英語話者のリアルな会話など、学校では触れる機会の少ない本場の英語を届けるコーナーが多数用意されています。
こだわりの学習トレーニング
音声を聞いてすぐにスクリプトを確認する、一般的なリスニング教材とは異なり、英文や日本語訳をあえて後半で確認する構成にすることで、英語を文字ではなく音から理解できるようにしています。英文の書き取りやシャドーイングなど、各トレーニングを一つずつこなすことで、最初は聞き取りが難しかった英文も深く理解できるようになります。
あらゆる角度から耳を鍛える豊富なコンテンツ
なぜ英語が聞き取れないのか? には理由があります。全15種類のシリーズは、文法や音の規則、ニュース英語など、それぞれ異なるテーマでリスニング力強化にアプローチしており、自分の弱点を知るきっかけになります。月に一度、TOEIC 形式のリスニング問題を解いたり、書き取りのコンテストに参加したりすることもできるため、成長を定期的に確認することも可能です。
「1000時間ヒアリングマラソン」は、現在7日間の無料トライアルを実施中です。さあ、あなたも一緒にランナーになりませんか?