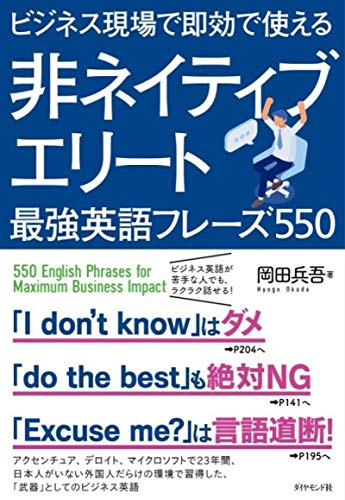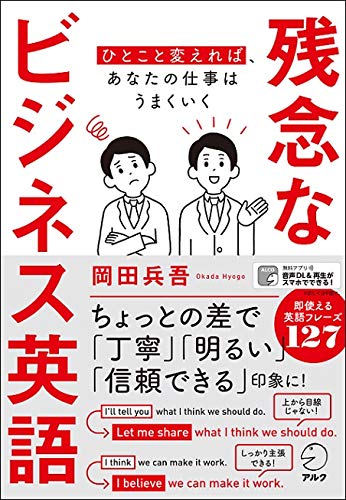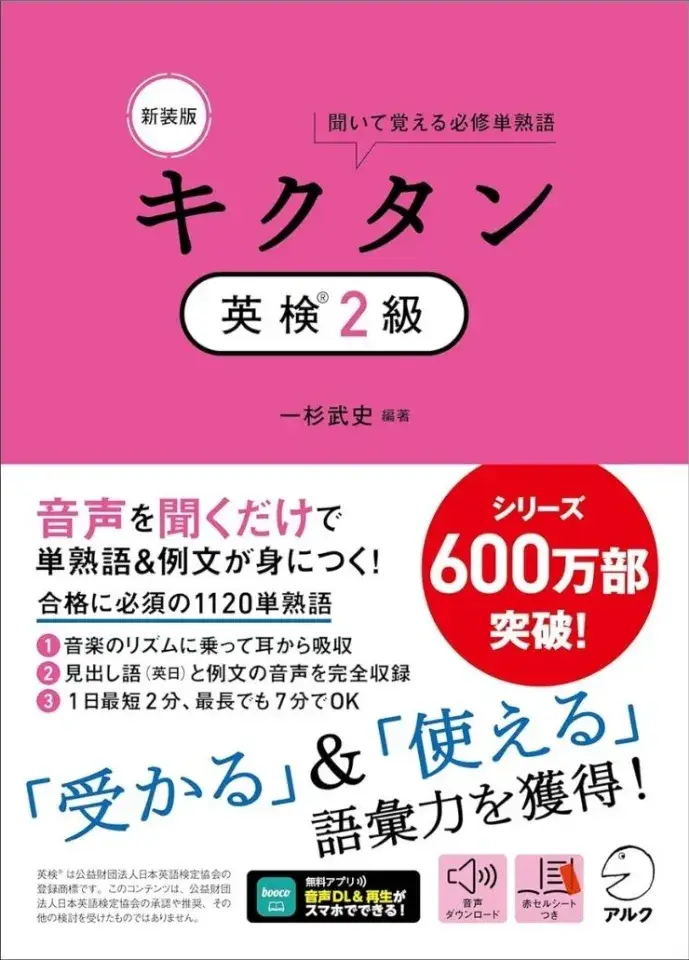グローバル社会で役立つ、日本人が使っちゃいけないビジネス英語のルールを、マイクロソフト シンガポール勤務の岡田兵吾さんが紹介します。第4回は、デキる非ネイティブ流「答えられない質問の回避法」です。
「分からない」をポジティブに伝えるには?
英語での会議や交渉の席。英語がうまい人に会話を任せて、発言もせず相づちだけでやり過ごしていませんか。
自分が英語を話す必要はないだろうと油断していると、自分の担当領域の質問を受けてしまい、外国人たちの注目を浴びながら、英語で回答せざるを得ない状況に陥るときもあります。
その際、すべての質問にその場で即答できるわけがないので、時折、「知らない」「分からない」と言うしかない場面もやってくる。そのような場面であっても、ポジティブが基本のグローバル社会で成功している非ネイティブは、 “I don’t know.” “I have no idea.”を使わない 。そんなことを言ってしまえば会話は即終了し、場合によっては相手を突っぱねたように感じるからです。
ではこんなときには、どう言えばよいか。例を見てみましょう。
I’m not sure . But I presume that it should be on track .わざわざ人に聞かれたのであれば、知らないことでも、“I’m not sure .”のあとに“but”をつけて、“I’m not sure . But ~”(確かではありませんが、~)で回答します。このフレーズを使うことで、「自信がない不確かな情報」であっても何かしらの情報を共有して、 サポートしようする意志が示せる のです。確かではありませんが、順調だと思います。
sure は「確信している」という意味です。これを否定形の“I’m not sure .”にすると、「確かではありません」のような曖昧なニュアンスになります。
一方で、記事の冒頭で紹介した“I don’t know.”や“I have no idea.”というフレーズは、「知らない」「まったく分からない」といった強くハッキリした意味を持つので、少しつっけんどんな回答になります。原則として、 海外でのビジネス会話では常にポジティブさが必要 です。ちょっとしたことでも、“I’m not sure .”を使ってソフトに回答します。
- I’m not sure .
- I don’t know. / I have no idea.
実際のところ、突然尋ねられても、こちらがすぐ答えられる内容ではないことのほうが多く、回答を知っているかいないかと聞かれたらなら、「 No 」となってしまうのが正直なところです。
だからといって、いつもバカ正直に「知らない」としか返せないと、「この人に聞いてもいつも情報が得られない。頼りにならない人」とネガティブな印象につながります。
日本語であっても「知らない」「分からない」を連発していたら、「この人、やる気あるのかな?」とマイナス印象につながるのと同じです。一回ぐらいの、“I don't know.” “I have no idea.”なら問題ないかもしれませんが、英語の語彙力が乏しいからといって「知らない」を連発しては、ビジネスパーソンとしては問題ありです。
I’m not sure . But I’ve heard that Brian used to launch a new logistic system.確かではないけど、以前ブライアンさんが、新しい物流システムを立ち上げたと聞いたことがあります。
I’m not sure . But I guess John may know.本当に知らなくて困ったとしても、上記のように回答して、少しでも情報提供することはできるはずです。会話をできるだけ「知らない」で終わらせないようにしましょう。確かではありませんが、ジョンさんならたぶん知ってるかも。
「ヤバい!答えられない!」そんな時の奥の手とは
また英語での会議や交渉の場でありがちなのが、こちらが答えに窮するような質問を受けてしまうときです。「詳しくないことについて質問された」「言葉を濁したい」「質問の真意を知りたい」といったとっさの瞬間、デキる非ネイティブは、 何度も連発できない奥の手 を使って窮地を脱しています。
奥の手フレーズ
How about you?メディアのインタビューではやってはいけない、必殺「質問を質問で返す」ですが、ビジネス英語では使える奥の手です。“ How about you?”で返すことの利点は、こちらは コメントを出さずして相手の意向を探ることができる ところです。あなたはどうお考えですか?
また、デキる非ネイティブは会話のネタを探るためにも“ How about you?”を活用しています。外国人と話をすると、相手が気を使って、会話が続くようにいろいろな話のネタを振ってくれることがあります。その質問に答えたあとに、今度はこちらから“ How about you?”で話題を継続させます。
たいていの場合、「振られた話題=相手も興味があること or 会話がしやすい話題」です。
外国人とそこそこ話したあと話題がない、と会話に困っている人は取り入れてみてください。「自分が会話しやすい話」に話題が移ることで、切れ切れだった会話が盛り上がります。
ちなみに 、会議などの司会進行の場でも“ How about you?”は使えます。
会議では一人でペラペラ話をして進行させる人もいますが、参加者全員の意見を引き出して確認しておかないと、あとで考えや情報にズレが生じます。
そんなミスを生まないために、“ How about you?”で意見を聞いておきます。さらに“ How about you, Richard?”(リチャード、あなたはどう考えますか?)というように、呼びかけを「対個人」にすると、より確実に意見を引き出せるはずです。
会議進行でこのフレーズを使う利点は2つあります。
- 「メンバーそれぞれを尊重しています」と気遣いを見せられる こと
- 確実に情報が 取得 できること
Would you like to introduce yourself?自己紹介されてはどうですか?
How is the marketing department doing?自分の考えに自信がなくて窮地に陥ったときや、外国人との会話が弾まないとき、“ How about you?”が使えることを思い出して試してみてください。マーケティング部はどうですか?
今回は、 言葉や回答に窮したときに使えそうな英語フレーズ を紹介しました。
適切な状況を理解しているか自信がなく英語で答えるのが怖いとき、相手の意向が見えずコメントをしたくないとき、 そもそも 何も考えていなかったときなど、いろんな「答えられない」シュチュエーションがあると思います。そんな「答えられない」ケースで、今回紹介したフレーズを使ってみてください。きっと役立つはずです。
STAY GOLD!
岡田兵吾さんの新刊はこちら!

岡田兵吾(おかだ ひょうご) @phoenix_hugo
マイクロソフト シンガポール アジア太平洋地区ライセンスコンプライアンス本部長。日本・韓国・オーストラリア・ニュージーランドの4か国のライセンス監査業務の責任者だけでなく、アジア全域のコンプライアンス対策およびデジタル変革を 推進 。また同社にて、アジア全域の働き方改革や国内外の大学・非営利団体でのリーダーシップ活動を評価され、数々の社内アワードを受賞。世界トップレベルの IEビジネススクール・エグゼクティブMBA 取得 。米国PMP(プロジェクト・マネジメント・プロフェッショナル)認定資格保持。著書に『ビジネス現場で即効で使える 非ネイティブエリート最強英語フレーズ550』(ダイヤモンド社)、『すべての仕事を3分で終わらせる外資系リーゼントマネジャーの仕事圧縮術』(ダイヤモンド社)がある。ダイヤモンド・オンラインにて「STAY GOLD! リーゼントマネジャー岡田兵吾の『シンガポール浪花節日記』」( https://diamond.jp/category/staygold )を連載中。人生目標は「ソーシャル・チェンジ」(社会変革)、座右の銘は「STAY GOLD!」
【1000時間ヒアリングマラソン】 ネイティブの生英語を聞き取る実践トレーニング!

大人気通信講座が、アプリで復活!
1982年に通信講座が開講されて以来、約120万人が利用した「ヒアリングマラソン」。
「外国人と自由に話せるようになりたい」「仕事で困ることなく英語を使いたい」「資格を取って留学したい」など、これまで受講生のさまざまな夢を支えてきました。
アプリ版「1000時間ヒアリングマラソン」は、日常、ビジネス、フリートーク、時事英語、物語などの多彩なジャンルのコンテンツを収録し、さらに豊富なアウトプット練習や学習時間の計測などの機能を盛り込み、よりパワーアップして復活しました。
「本物の英語力」を目指す人に贈る、最強のリスニング練習
学校では習わない生きた英語
実際にネイティブスピーカーと話すときや海外映画を見るとき、教科書の英語と「生の英語」のギャップに驚いた経験はありませんか? 「1000時間ヒアリングマラソン」には、オリジナルドラマやラジオ番組、各国の英語話者のリアルな会話など、学校では触れる機会の少ない本場の英語を届けるコーナーが多数用意されています。
こだわりの学習トレーニング
音声を聞いてすぐにスクリプトを確認する、一般的なリスニング教材とは異なり、英文や日本語訳をあえて後半で確認する構成にすることで、英語を文字ではなく音から理解できるようにしています。英文の書き取りやシャドーイングなど、各トレーニングを一つずつこなすことで、最初は聞き取りが難しかった英文も深く理解できるようになります。
あらゆる角度から耳を鍛える豊富なコンテンツ
なぜ英語が聞き取れないのか? には理由があります。全15種類のシリーズは、文法や音の規則、ニュース英語など、それぞれ異なるテーマでリスニング力強化にアプローチしており、自分の弱点を知るきっかけになります。月に一度、TOEIC 形式のリスニング問題を解いたり、書き取りのコンテストに参加したりすることもできるため、成長を定期的に確認することも可能です。
「1000時間ヒアリングマラソン」は、現在7日間の無料トライアルを実施中です。さあ、あなたも一緒にランナーになりませんか?