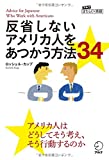世界を相手にビジネスを行うためには、英語力だけでなく、多様な文化を受け入れるグローバルマインドセット、つまり視野の広いもののとらえ方が必要となります。本コラムでは経営コンサルタントのロッシェル・カップさんに、グローバルマインドセット獲得のヒントを教えていただきます。
OJTはトレーニングに入らない!?
あなたはアメリカにある日系自動車部品メーカーで働いています。アメリカ人社員からこういったコメントがありました。
「会社は技術移転をすると言っていますが、私にはそうは思えません。正式なトレーニングクラスを開いたことがありませんし、マニュアルさえ存在しないのですから」
あなたのその質問に対する答えは、「われわれの哲学はOJTです」。
しかし、アメリカ人従業員はそれには納得しませんでした。どう対応すれば良いでしょうか?
ですから、多くの日本人はこういった否定的なコメントを受けることに慣れておらず、自動的に悪く解釈してしまう 傾向 があります。
しかし、 他の多くの文化では、こういったような発言は「文句」ではなく「建設的な 指摘 」と解釈され、実は評価されます 。
「OJT」は英語の on -the-job training の略なので、多くの日本人はそれがアメリカで広く使われている方法だと思っていますが、実はアメリカでは日常的にはほとんど耳にしない言葉です。対照的に、日本ではよく使われています。なぜでしょうか?
その理由は、教える方法 に関して の文化的な背景からです。
「教え方」にも文化による違いがある

上記のチャートでは、 左の方にある文化は徒弟制度的な教え方を好んでいます 。こういった文化の人は、時間をかけて仕事をすることで学ぶことができると思っています。なお、教室やセミナースタイルの勉強は、あまりに抽象的なので応用性が薄いと思っています。
一方、 右の方の文化はセミナースタイルや教室における勉強を好みます 。ものごとを学ぶに当たって、理論的な枠組みを勉強したがる 傾向 があり、言葉による説明が重要だと思っています。また、能力があれば、技術を早くマスターすることは可能であると思っています。
このチャートでは、日本はかなり左の方の文化で、アメリカはかなり右の方にあります。その違いがあるからこそ、このケースで見られる摩擦が生じます。
OJTの意義を説明し、より体系的に

日本人は教室における勉強にはあまり価値を置かないので、より役立つと確信している OJTに重点を置きます。 同時に 、OJTを通じて、従業員が必要な技術を自然に身に付けると期待しています。
しかし、アメリカ人にとって勉強は体系的なものなので、セミナースタイルや教室、マニュアルによる言葉の説明や論理を期待し、もしそれがないと教育を受けたとは感じません。
こういったギャップを埋めるために、【b】と【c】との両方の対応を推薦します。【b】によって、 なぜOJTは価値があるのか、OJTによって何を学ぶべきかなどの説明があれば、アメリカ人にとってもっと理解しやすい はずです。
そして、さらに 明確なスケジュールなど、より体系的な要素を入れると、アメリカ人は 安心 します 。そして、【c】を積極的に取り入れることによって、アメリカ人がより効率的に吸収できる形での情報提供が可能となり、教育の効率と効果が上がることによって、このケースで見られる不満は減少します。
こちらもおすすめ!
ロッシェル・カップさんの本

- 作者: ロッシェルカップ,大野和基
- 出版社/メーカー: 集英社インターナショナル
- 発売日: 2017/08/07
- メディア: 新書
![]() 反省しないアメリカ人をあつかう方法34 (アルク はたらく×英語シリーズ)
反省しないアメリカ人をあつかう方法34 (アルク はたらく×英語シリーズ)- 作者: ロッシェル・カップ
- 出版社/メーカー: アルク
- 発売日: 2015/12/24
- メディア: 単行本
![]() 日本企業がシリコンバレーのスピードを身につける方法
日本企業がシリコンバレーのスピードを身につける方法- 作者: ロッシェル・カップ,到津守男,スティーブ・マギー
- 出版社/メーカー: クロスメディア・パブリッシング(インプレス)
- 発売日: 2017/07/18
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
![]() 日本企業の社員は、なぜこんなにもモチベーションが低いのか?
日本企業の社員は、なぜこんなにもモチベーションが低いのか?- 作者: ロッシェル・カップ
- 出版社/メーカー: クロスメディア・パブリッシング(インプレス)
- 発売日: 2015/01/30
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (2件) を見る
編集:GOTCHA!編集部![]()
執筆:ロッシェル・カップ
ジャパン・インターカルチュラル・コンサルティング社 社長。
異文化コミュニケーションと人事管理を専門とする経営コンサルタントとして、日本の多国籍企業の海外進出とグローバル人材育成を支援している。イェール大学歴史学部卒業、シガゴ大学経営学院卒業。日本語が堪能で、『 反省しないアメリカ人をあつかう方法34 』(アルク)、 『英語の品格』 (集英社) をはじめ、著書は多数。朝日新聞等にコラムも連載している。