
翻訳者のエリザベト怜美さんが、多様な作家による作品を通して、文学をリアルに感じる読み方をお届けする連載「イギリス育ち翻訳者の英語文学へのいざない」。第2回は、100年近く前にイギリスで出版された ヴァージニア・ウルフの小説『オーランドー』 です。奇想天外とも言われる物語から見えてくる、現代を生きる「私」たちの姿とは?
歴史を駆け抜ける旅
ほとんど家で過ごす生活にも慣れてきたものの、たまにイギリスの街がふと恋しくなる。
せっかくなら、エリザベス王朝の貴族の屋敷から20世紀のロンドンの街並みまで駆け巡る旅がしたいと思い、ヴァージニア・ウルフのモダニズム小説『オーランドー』(原題:Orlando: A Biography )を読むことにした。

本作は、移ろう時代の中で身分や暮らしぶり、そして性別までをも変化させながら、300年以上の時を、ほとんど年を取らずに生き続ける詩人・オーランドーの伝記物語。
一見、突拍子もないような粗筋だが、流れるような文体で、軽快なユーモアがあふれ出ておりとても楽しい。
映画版では、アンドロジナスな魅力のあるティルダ・スウィントンが主演を務め、去年のウィーンのオペラ公演では、コム デ ギャルソン(「少年のように」の意)のディレクター・川久保玲が衣装を担当。
かつては、永遠の若さへの憧れという解釈を主流に、日本ではまず幻想文学として紹介され、近年ではジェンダーの流動性(gender fluidity)の文脈で大いに脚光を浴びている。
読み返されるたび表情をさまざまに変えながら、もう100年近く読み継がれてきた名作だ。
矛盾に満ちた存在
なぜ、『オーランドー』は世代を越えて私たちの心を捉えるのか。
それはきっと、「自分らしさとは何か?」というアイデンティティーへの疑問を抱えながら、喜びも悲しみも目まぐるしく生きる主人公の姿に、誰しも自分をいくらか重ねるからだろう。
エリザベス1世の寵臣、在トルコ英国大使、ジプシー、文学サロンの主人・・・と時代に合わせて異なる肩書きを持ちつつ、常にそこから逸脱し続けるオーランドーの半生。
すると、思わず、これまでの私を振り返らざるをえない。日本人として生まれ、英国へ引っ越して移民になり、日本に戻ると帰国子女と呼ばれ、そのうち哲学科の学生になり、骨董通りの会社員になり、独立して翻訳者になって・・・次々に社会的身分を変えながら、今の姿になった。

けれども、どの言葉も私を表すには十分ではない。なぜなら、それらの名前は社会のある特定の集団を示すものであって、どんなに尽くしても個人にはたどり着かないからだ。
一人の人間には、もっときめ細やかで、複雑な側面がある。
Nature , who has played so many queer tricks upon us, making us so unequally of clay and diamonds, of rainbow and granite, and stuffed them into a case , often of the most incongruous ...(“Orlando,” Virginia Woolf)そのように造られた人間は、中身も外見も一筋縄にはいかない。「自然は支離滅裂と謎が好きだから」(ウルフ、前掲書)、誰一人として、おおざっぱな肩書きの示す社会規範(social norm)にぴったりと収まることはないのだ。自然は人間に随分おかしないたずらをしてきたもので、粘土とダイアモンド、虹と花崗岩をいい加減に混ぜて、それを大抵の場合ひどくちぐはぐな容器に詰めこむ(後略)
(ヴァージニア・ウルフ『オーランドー』杉山洋子訳)
この「norm(規範)」という単語は「normal( 正常)」の語源であり、 従って 「正常」とは規格の範囲内という意味を指す。
掲げられた規範を常に逸脱しながら、オーランドーは風のように時代を駆け抜ける。それは、自分らしく生きる自由を追求する生き方だ。
いつも、ある程度、社会の習慣に適応し、少しばかりその気になるものの、最終的には自分の規格外の部分を愛して、自分らしく生きる道を選択する。
そこには、前よりほんの少し、大きくなった自由がある。
真の自由とは?
ただし 、自分自身として生きるには、「規範からの逸脱」としての自由だけでは不十分だ。
ある場面で、「真実」のラッパが吹き鳴らされ、目覚めたオーランドーの身体は男性から女性になる。それ以降、両性具有者として生きることにするが、さすがにしばらくして困惑し、オーランドーは胸のポケットにしまってある詩の原稿に手を当てる。
The distraction of sex, which hers was, and what it meant, subsided; she thought now only of the glory of poetry ...(“Orlando,” Virginia Woolf)「オーランドーは何者か?」という問いへの答えは、男か女か、はたまたそれ以外か、という枠組みに照らし合わされて決まるのではない。自分は男なのか女なのか、これはいったいどういうことなのか、というような性別の混乱は収まって、今はただ詩の栄光のみを思う(後略)
(ヴァージニア・ウルフ『オーランドー』杉山洋子訳)
オーランドーは、自分の書いた「詩」によりどころを見いだす。彼女となった彼のアイデンティティーは、規範や、規範からの逃走ではなく、自分で発揮した創造性に委ねられたのだ。
自ら観察し、望み、問い、感じ、作り出したものを確認することによって、ようやく自分の存在の確かさが生まれる。

コム デ ギャルソンの川久保玲は、あるときこのように述べた。
真のクリエイティビティ、真の自由というものは、あらゆる二元論、右と左、リアルとアンリアル、男と女などを超越した時に達成される。(『SWITCH』 Vol. 38 「COMME des GARCONS: Orlando」インタビューより)「男と女」のような、常識とされている考えを理解しつつも、そこで完結せずに未知の表現を生み出そうとすること。それと 同時に 、すでに「男と女」を越えた仕方で存在している自分の側面を発見すること。
それこそが真の自由の営みであり、自由を獲得していく生き方である。
「私」を定義するのは誰か?
時代によって、決まり事は変わる。
年を重ねると、おのずと身分も変わっていく。それを包み込む社会も、適切に言い表す言葉も、だんだん新しくなっていく。
その上、時に政治によって、災害によって、自由を求める戦いによって、もっと大きく変化することもある。
その最中で、「自分は何者か?」という疑問に答え、私という複雑な存在を定義するのは、いつだって自分自身だ。

私たちの持つ自己決定の自由は、これまで世界中で繰り広げられてきた、一人一人の自由を求める闘争によって、少しずつ拡張されてきた。
その壮大な自由精神の歴史の途上を、私たちは今も生きている。
小説『オーランドー』の物語は、初出版された日付と同じ1928年10月11日に終わりを迎える。それを受け、映画とオペラ作品の方も、クライマックスの場面が現代まで引き延ばされている。
これは、いつの時代も、私たちの物語なのだ。
次回は2021年8月20日に公開予定です。
文学を通じて英語力を強化したい人におススメの参考書はこちら!

こちらもおすすめ
▼エリザベト怜美さんの連載「イギリス育ち翻訳者の哲学的生活」
記事中の写真撮影:エリザベト怜美

エリザベト怜美(えりざべと れみ) 翻訳者。1991年、横浜に生まれ、イギリスで育つ。上智大学文学部哲学科卒。在学中から翻訳会社に勤務し、アートギャラリー、広告代理店を経て独立。主に、広告、海外ボードゲーム、映像作品の翻訳を手掛ける。ボードゲーム『プレタポルテ』『クロニクル・オブ・ クライム』『テインテッド・グレイル』翻訳。
Twitter: @_elizabeth_remi
boocoで読める!アルクの新刊、続々登場
語学アプリ「booco」なら、アルクのベストセラー書籍200タイトル以上が、学習し放題!
「キクタン」などアルクの人気書籍800冊以上が音声対応。「読む」に対応した書籍では、本文と音声をスマホで手軽に利用できるほか、一部の書籍では、学習定着をサポートするクイズ機能で日々の復習や力試しも可能です。さらに、Plusプランに加入すれば200冊以上の書籍が学習し放題に!
boocoの「読む」機能では、次のような使い方ができます。
① 学習したいページを見ながら音声を再生できる
② 文字サイズや画面の明るさを調整できる
③ 書籍内検索ができる
※ これらの機能には一部の書籍が対応しています。

▼「booco」の無料ダウンロードはこちらから
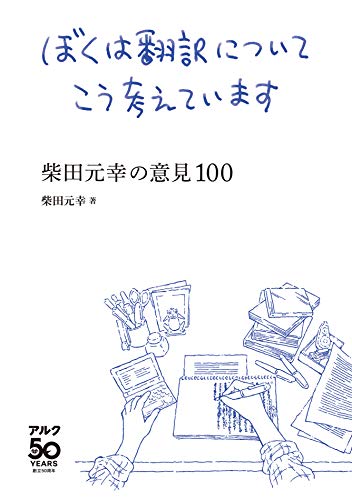





![『スピーキングのための英文法帳 スピブン555』[音声DL付]](https://image-ej.alc.co.jp/images/GamGSrTWRko6iAR2V9kR.webp)
