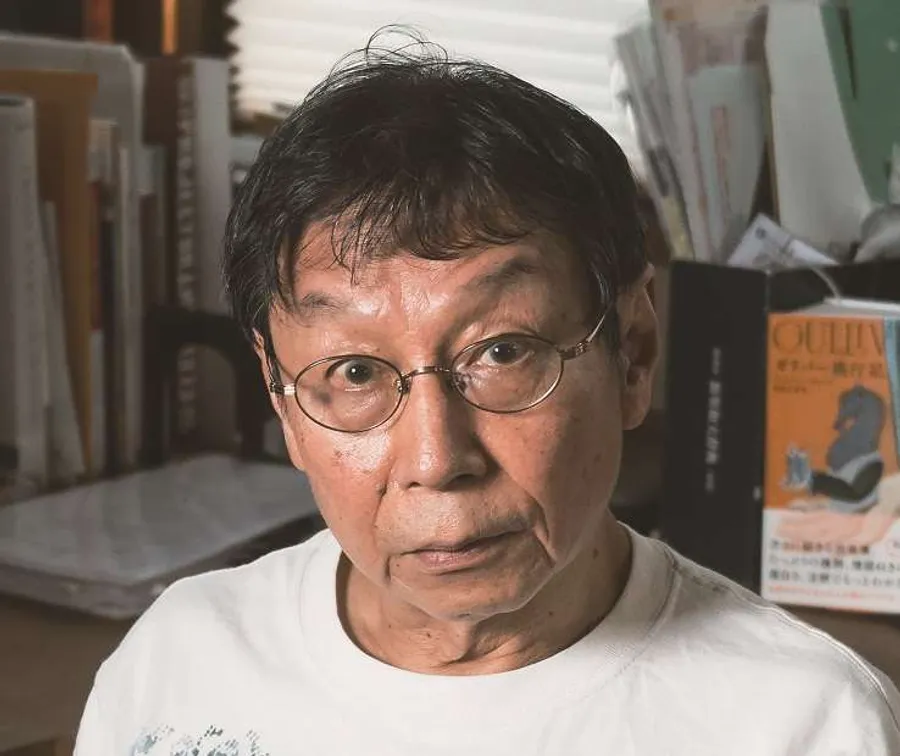今月ご紹介するのは、イーディス・ウォートンの『歓楽の家』からの一句。小説で描かれる男女の関係は、現代もあまり変わっていないのかもしれません。
We are expected to be pretty and well-dressed till we drop?
Edith Wharton, The House of Mirth (1905)
“Till we drop” というフレーズは、わりと呑気な文脈で使うことが多い。“Let’s shop till we drop”(買い物しまくろう)とか、weをyouに変えてBop Till You Drop(ぶっ倒れるまで踊れ)といえば名ギタリスト、ライ・クーダーの1979年のアルバムのタイトルである。
だが、20 世紀前半アメリカの代表的女性作家イーディス・ウォートン初期の傑作The House of Mirth(歓楽の家)にあっては、そんな呑気な話ではない。ヒロインのリリー・バートは、資産の後ろ盾のない女性が社会で地位を得るには容姿で勝負するしかない、と考えるだけの現実感覚の持ち主だが、その現実感覚に従って振る舞おうとする自分を是認しきれないだけの潔癖さの持ち主でもある。
上の一句の周囲を見てみよう。
Ah, there’s the difference — a girl must, a man may if he chooses.” She surveyed him critically. “Your coat’s a little shabby — but who cares? It doesn’t keep people from asking you to dine. If I were shabby no one would have me: a woman is asked out as much for her clothes as for herself. The clothes are the background, the frame, if you like: they don’t make success, but they are a part of it. Who wants a dingy woman? We are expected to be pretty and well-dressed till we drop — and if we can’t keep it up alone, we have to go into partnership.
(Book I, Chapter 1)
「そこが違うのよね――女は『やるしかない』で、男は『やりたけりゃやってもいい』」。リリーはセルデンを厳しい目で眺めわたした。「あなたの上着は若干みすぼらしい。でも誰が気にする? みすぼらしくたって、みんな、あなたを夕食に誘うのをやめはしない。もし私がみすぼらしかったら、誰にも相手にされない。女は半分中身、半分服で誘われるのよ。服は背景、枠組みみたいなもので、それだけでうまくいくわけじゃないけど、欠かせない要素ではある。むさくるしい女なんて、誰が相手にする? 女はくたばるまで綺麗でお洒落でいるよう求められてるのよ。で、それを一人でやっていけないなら、協力関係を結ぶしかない」
結婚を“partnership”と割り切ろうとするのがリリーの現実感覚だが、割り切りきれないところに彼女の悲劇がある。
リリーがここで話している相手のセルデンは、この小説でリリーのことを最も理解している人物である。だが金も権力もなく、無力である。そもそも19世紀~20世紀前半アメリカの女性作家の作品に出てくる男性は 、 大きく二つのタイプに分かれる。(1)金 も 権力もあるが女性に理解がない(ゆえに女性を助けてくれない)。(2)女性に理解はあるが金も権力もない(ゆえに女性を助けてくれない)。セルデンは言うまでもなく後者である。
――と、理解も金・権力もない人間が言えた義理じゃないのですが。
boocoで読める!アルクの新刊、続々登場
語学アプリ「booco」なら、アルクのベストセラー書籍200タイトル以上が、学習し放題!
「キクタン」などアルクの人気書籍800冊以上が音声対応。「読む」に対応した書籍では、本文と音声をスマホで手軽に利用できるほか、一部の書籍では、学習定着をサポートするクイズ機能で日々の復習や力試しも可能です。さらに、Plusプランに加入すれば200冊以上の書籍が学習し放題に!
boocoの「読む」機能では、次のような使い方ができます。
① 学習したいページを見ながら音声を再生できる
② 文字サイズや画面の明るさを調整できる
③ 書籍内検索ができる
※ これらの機能には一部の書籍が対応しています。

▼「booco」の無料ダウンロードはこちらから