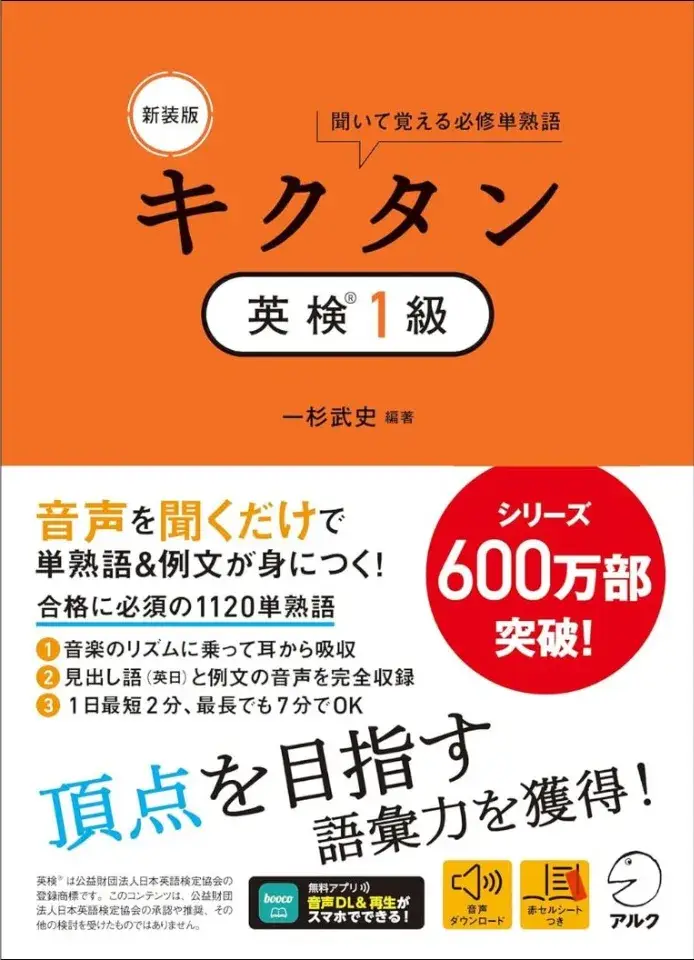働き方が多様化する昨今、長く働き続けるために、英語好きの方なら翻訳を仕事にすることを考えたことがあるのでは?でも、文書の翻訳とは違う「映像翻訳」は少し特殊な気がして、学習に踏み込めない方もいるかもしれません。この連載では、そんな一人だったGOTCHA!編集部員が、日本映像翻訳アカデミーとアルクが共同開発・運営する 「映像翻訳Web講座」 に挑戦する様子をお伝えします!
前回の記事はこちら
gotcha.alc.co.jpいよいよ映像翻訳講座の受講開始!
前回の記事 で映像翻訳の学習への意気込みを表明し、今回からはいよいよ、 「映像翻訳Web講座 ベーシックコース」 の受講スタートです。緊張もしますが、楽しみです。
「コースガイド」などが郵送で届く
受講申し込み後、数日で「コースガイド」などが郵送で届きました。同封物は下の画像の通り。郵送されてくる教材はこれらのみで、 あとは全てインターネット上で受講 します。

この中で 熟読しておくべきもの は、下の2つです。
- 「コースガイド」
- 「映像翻訳ハンドブック」
「映像翻訳ハンドブック」には、 「字幕・吹き替え翻訳の基本ルールと実例」 が詳しく説明されています。どれも、このコースにおいて非常に重要なことばかり。課題に 取り組む 上で必須の内容ですので、丁寧に読んでおきましょう。
そう言う私は、届いたら すぐに 読めばいいのにしばらく放置してしまい、第1回の課題に 取り組む に当たってやっと全部読みました。薄い冊子ですが、きちんと確認しながら読んだので、1時間はかかったと思います。 今後 重宝することになりそうです。
受講生専用サイト「manaba」にログイン
インターネット上での受講開始日の数日前に、 受講生専用サイト「manaba」 へのログイン情報などが記載されたメールが届きました。受講生はこのサイトを通して、学習や課題の 提出 、返却された課題の受け取りなどを行います。
またもや数日間放置してしまいましたが(スミマセン)、ログインしてみると、下の画像のようなサイトでした。

ずらりと並ぶ「コンテンツ」を見て、「やらなきゃ~」というプレッシャーを感じます。赤っぽい色の印が付いている上部の「レポート」というタブをクリックして見ると、第1回の課題 提出 の期限は8月14日。あと10日余りしかありません!やる気を出します!
なお、 前回の記事 で紹介したように、このコースの 課題 提出 の頻度は2週間に1回 です。私のようにしばらく放置したりしなければ、1回分の課題に 取り組む 期間は14日間ありますので、ご 安心 ください。
第1回は短編映画の字幕翻訳!
やる気はあるはずなのに、「勉強」となるとなかなか取り組めなくて、締め切りギリギリになってしまうのはなぜなのでしょうか?なんと、第1回の課題の締め切り当日になって初めて学習に取り掛かるという、無謀なことになってしまいました。最初からダメダメです……。
当たり前のことですが、課題に取り組んだら、 提出 前に少なくとも一晩は寝かせて見直し をした方がいいです。と、頭では分かっているのに~!決して私のまねはしないようにしてください!第2回目以降は課題がさらに大変になってくると思いますので、 今後は もっと早くから 取り組む よう肝に銘じたいと思います。
気を取り直して。第1回から第3回では、 5分程度の短編映画を3回に分けて字幕翻訳 します。第1回の課題では、全編を見た後、冒頭の3分の1を訳します。映画は、ネタバレはできませんが、気持ちがほんわかするストーリーです。
動画とPDFのコンテンツで学ぶ
学習内容は、 動画とスクリプトなどのPDF で構成されています。動画は、 受講前に講座案内のサイトで、講座で使用するソフトの 動作 確認 をしておいたので、問題なく視聴できました。
第1回の動画は、次の3つです。
- 映画全編
- 第1回で訳す分のみの映画
- Tips
第1回で提供されるファイルは、この3つ。
- 第1回で訳す部分の英文スクリプト(PDF)
- 回答・質問用紙(Word)
- 自習ドリル(PDF)
自習ドリルは プラスアルファの学習用 で、第1回のテーマは「調べ物編その1」。「調べ物は紙で」という忠告には耳が痛いです。ついインターネットで済ませてしまうので。
字幕翻訳のルールって大変?
いきなり翻訳するのか!と思いましたが、当然ですね、 自分でやってみないと学べません 。
第1回の課題を実際に訳し始める前に、映画を全編通して2回見ました。2回見ると、 1回目は気付けなかったディテールに気付く こともできます(と、昔、映画をひたすら見るという大学の講義で習いました)。こうして、 登場人物の性格や目的、ストーリーを 把握 して、翻訳に生かします。映画の内容について自分ではこう思うけど、ちゃんと 把握 できたのかな?と不安を抱えつつ、翻訳に 取り組み ました。
少し困ったのは、第1回の課題をする時点では、第1回の英文スクリプトしか見られないこと。 冒頭部分のせりふをどう訳すかは、残りの映画の内容とも関わる と思うのですが、第1回以降の内容の手掛かりは、映像と英語音声のみ。やはり、 英語リスニング力があるに越したことはない わけですね。全てを聞き取ることはできませんでしたが、話の流れと結末はだいたい分かったかな?と思いました。大きな勘違いをしていなければいいのですが。
最初は、正直に言って、細かいルールが多くて大変そうと思っていたのですが、訳し始めると、 制限範囲内で訳文を考えるのが、思いのほか楽しい! 何なのでしょうか、このワクワク感は?工夫の方向が合っているのかは分からないながらも、字数を短くするにはどうしたらいいかなども考えて、どうにか訳しました。
仕事などとの両立に不可欠な、時間の話
回答・質問用紙には、動画を見たり調べ物をしたりする時間も含めた所要時間も記入します。私の場合は、Tipsの動画を見る時間も含めて、約2時間20分でした。「映像翻訳ハンドブック」を読んだ時間も含めると、 3時間半ほどで第1回の学習に取り組んだ ことになります(自習ドリルの学習時間は除く)。
講座案内のサイトには、学習時間の 目安が「1日60分×週5日」 とあるので、本来はもっとじっくり 取り組む べきですね……。ただ、頑張れば(追い詰められれば?!)、この目安より もっと短い学習時間でも講座受講は可能 そうです。
……などとと言っておいて、第2回以降の課題で痛い目に遭うかもしれませんが、学習時間がどのくらいかかるかは、仕事や翻訳以外の学業や家事などがある人にとっては大問題。
私が以前、翻訳学校の通学コースに通っていたときは、平日は翻訳にきちんと取り掛かる時間を確保できなかったので、週末の半日を課題の翻訳 作業 に当てていました。仕事をやめて翻訳の勉強をしていたクラスメートは、毎週、数日間かけて課題を翻訳していたらしく、「すごいね」と言ってくれましたが、きっとその人は私よりも調べ物をしたり訳文を練ったりする密度が濃かったのだと思います。
思い立ったが吉日ですので、映像翻訳をやろう!と決心したら、 少しでも学習時間の確保が可能であれば、受講を始めてしまう のがいいのではないでしょうか。人それぞれ、そのときに自分が使える時間内で精いっぱいの学びをすれば、身に付くことがあると思います。現に私はその初めての翻訳講座の受講で、遊ぶ時間を削るなどして忙しくはありましたが、 漠然とした憧れだった翻訳が、身に付けたい技能 に変わりました。
課題ごとに質問もできる
課題 提出 の際には、今回の課題について質問することもできます。質問できるのは、1回分の課題 提出 につき1枚で1回まで。私は、 課題で難しくて自信がなかった部分 と、 字幕のルール について、1つずつ質問を書きました。
課題の添削原稿の返却(質問した場合はその回答も)と訳例が「manaba」にアップロードされるのは、 課題 提出 期限の2週間後 です。ああ、すごく緊張します。ドキドキドキドキドキ。
次回は、添削結果を大公開!する予定です。(答案が真っ赤っ赤だったら、恥ずかしくてできないかもしれませんが!)ではそれまで、第2回の学習に進もうと思います。
今回のポイント!
- 郵送で届く 「コースガイド」と「映像翻訳ハンドブック」は熟読 しておく。
- 受講開始日の数日前に 受講生専用サイト「manaba」 へのログインの案内メールが届いたら、 即、ログイン する。
- 2週間に1回、課題 提出 があるので、 早めに 取り組み 、 提出 前に見直す 時間を確保する。
- 講座に申し込む前に、講座案内のサイトで、 使用するソフトの 動作 確認 をしておく。
- 映画の一部分を翻訳する場合にも、 全体の内容を 把握 してから 訳し始める。
- 字幕翻訳は、 ルールに注意 しながら、工夫することを楽しんで訳す。
- 課題に 取り組む ときは、かかった時間のカウントと疑問点のメモを忘れずに行い、 提出 時に 所要時間と質問も記入 する。
映像翻訳Web講座 ベーシックコース

あなたに寄りそう!「映像翻訳Web講座」
時間の制約や通学距離などの事情から、通学受講を迷っていた方々におすすめ!パソコンがあれば、どこにいても受講できます。最短22カ月間で、プロの映像翻訳者になれます。まずは、ベーシックコースから。

受講体験者・文:アンズ(GOTCHA!編集部)
「手に職」をと、実務翻訳や文芸翻訳の講座を受講したことあり。映像翻訳は字幕・吹き替えともに未体験。最近はビジネス分野の実務翻訳でも動画の字幕・吹き替えの需要が増加しているという話を聞き、今回の受講へ。
boocoで読める!アルクの新刊、続々登場
語学アプリ「booco」なら、アルクのベストセラー書籍200タイトル以上が、学習し放題!
「キクタン」などアルクの人気書籍800冊以上が音声対応。「読む」に対応した書籍では、本文と音声をスマホで手軽に利用できるほか、一部の書籍では、学習定着をサポートするクイズ機能で日々の復習や力試しも可能です。さらに、Plusプランに加入すれば200冊以上の書籍が学習し放題に!
boocoの「読む」機能では、次のような使い方ができます。
① 学習したいページを見ながら音声を再生できる
② 文字サイズや画面の明るさを調整できる
③ 書籍内検索ができる
※ これらの機能には一部の書籍が対応しています。

▼「booco」の無料ダウンロードはこちらから