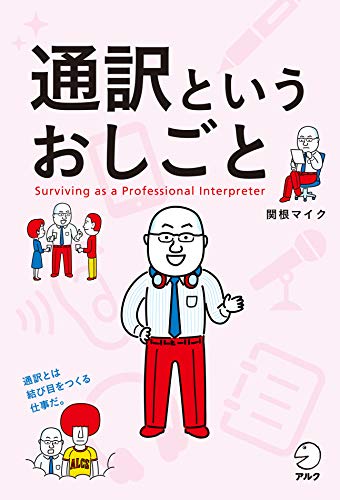フランス語・イタリア語と日本語の翻訳家・通訳者である平野暁人さんの連載「舞台芸術翻訳・通訳の世界」。ご専門の舞台芸術通訳の仕事や趣味とする短歌など、多角的な視点から翻訳・通訳、言葉、社会についての考察をお届けします。第3回は、翻訳と演劇で各人が果たす役割の比較がテーマです。
「訳者は役者」は本当か?
こんにちは。翻訳家で通訳者の平野暁人と申します。
前回 は、私が舞台芸術の通訳者として第一歩を踏み出したときのことをお話ししました。
そこで今回は、「舞台芸術と翻訳」をテーマにあれこれ書いてみようと思います。
誰が言ったか、翻訳の世界には「訳者は役者」という言葉があります。
と、ここまで書いてから不安になって調べてみたら、『アンネの日記』やアガサ・クリスティーのシリーズの翻訳で有名な深町眞理子さんがご自身の座右の銘として1970年代から提唱していらっしゃるそうです *1 。
危ない危ない。危うく大先輩にエア無礼を働くところだったぜ。
「他人が書いた言葉(原著/戯曲)を、自分という媒介(訳者/役者)を通して表現(翻訳/演技)する」といった類比に基づいて解釈すれば、この「訳者は役者」という格言は実に言い得て妙ですし、翻訳に本格的に取り組んだ経験のない人にも 割合 わかりやすいように思えます。実際、私自身もこの言葉を知ったときは、(世の中にはうまいことを言う人がいるなあ)と感心したものです。
でもこれ、本当に本当なのでしょうか?
翻訳書づくりと演劇作品づくり
などと、のっけから挑発的な書き方で叱られてしまいそうですが、私がこの金言に違和感を抱くようになったのは、まさに演劇の仕事を始めてからのことです。
戯曲を訳したり、それを台本に起こしたり、稽古場の通訳をしたりして演劇の作品づくりを少しずつ理解してゆくうちに、比喩とはいえ「訳者」と「役者」を等号で結ぶのは無理があるのではないかという気持ちがむくむくと湧き上がってきたのです。
一般に、書籍の翻訳に代表される「読むための翻訳」は、ごく単純化すると「原著→訳者→読者」という流れをたどります *2 。共訳だったり、下訳者が入ったりと関わる人が増えることはあっても、この構図は基本的に変わりません。
では、演劇づくりをこれになぞらえて「戯曲→役者→観客」としてみましょう。
すると・・・あれれ?演劇が好きな人なら、一つ重要な存在が抜けていることに気付くはず。そう、「演出家」です。演劇づくりにおいては、書かれた言葉である「戯曲」を表現する主体として「役者」のほかにもう一人、「演出家」という存在があるのです。
本稿をお読みくださっている方であれば、生まれてから一度もお芝居を見たことがないという方はあまり多くないのではないかと思います。少なくとも、「役者」と聞いてどんな仕事をする人なのかまったくイメージできない、ということはまずないはずです。
一方で、「演出家」は、舞台芸術の世界では極めて重要なポジションでありながら、その 具体的な 仕事内容は意外なほど知られていないように思います。
演劇における「演出家の役割」と「演出家と役者との関係」
では、「演出家」っていったいどういう存在なのでしょうか?
いろいろなスタイルの人がいるので一概に言えないのですが、強いて簡潔に表現すれば、「解釈する人」であり「決める人」という側面がいちばん大きいと思います。
まず「解釈する」とは、自分が演出を試みる戯曲に対し、核となり得るテーマは何か、どんな角度から切り込むのか、どういう側面に光を当てたいのか、今の時代状況に照らしてその作品を上演する意義とは、といった問いを立て、自分なりの作品観を明確に構築することです。
次に、「決める」とは何を決めるのかというと「すべて」です。
紙に始まり紙に終わる翻訳書づくりと違い、演劇は書かれた戯曲を三次元に起こしてお芝居にするわけですが、その際には当然、役者だけでなく、舞台美術、照明、音響、衣装、メイクといった、舞台を構成するさまざまな道具立てが必要となってきます。そして、それらすべてを最終的に「決める」のも演出家の仕事なのです。
こう書くと、演出家がなんでもできるルネサンス型万能人であるかのような誤解を与えてしまうかもしれませんが、もちろんそういうわけではなく、美術には美術家、照明には照明家、といった具合にきちんと専門のスタッフを起用してチームを組みます。
そして(多くの場合)、まず演出家から自分の作品観を各分野のスタッフに示し、話し合い、共有します。
これを受けて各スタッフは演出家から託されたイメージを具現化すべく、知識、技術、センス、根性、野望その他を総動員してさまざまにプランを練り、提案します。そうして集まってきた提案を検討し、時にはさらなる要求を課し、 改めて 検討し、といった 作業 を繰り返して、最終的にどの案でいくか「決める」のが演出家というわけです。
当然、スタッフもそれぞれに高度な専門性と美学を備えたクリエーターですから、意見が対立することだってあります。膨大な量の「ボツ」を経てようやく一応の「解」にたどり着くのが普通で、その点は作品づくりの現場であれば芸術に限った話ではないでしょう。
そしてこれら一連の 作業 は、「役者」 に関して も例外ではありません。
役者さんたちもまた、台本に書かれた 指示 や台詞(せりふ)、人物像を、演出家の作品観に沿って具現化しようと思い思いにプランを練り、提案します。たとえどんなに気に入っているプランであっても演出家の求めるイメージに合致しなければ意味がないので、OKが出るまでひたすらに過酷な試行錯誤を重ねるしかありません。
逆に言うと、役者本人はいまひとつだと思いつつ試したら、演出家が気に入ってしまったので採用、というケースもあります。ですから実を言うと、目の前で熱演している役者が実は自分の芝居にピンときていない 可能性 すらあるのです。ていうか、むしろ結構ある。けどひみつ(小声)。
ともあれそうやって、演出家と役者は互いに感性を刺激し合いながらさらなる表現の 可能性 を希求してゆくわけですね。
「訳者は役者」にとどまらない
以上、演劇づくりにおける演出家の役割、演出家と役者との関係を(あくまでも私なりの観点から)ざっと 整理 したところで、件(くだん)の「訳者は役者」という格言について 改めて 考えてみましょう。
すでに述べたとおり、翻訳書づくりと演劇づくりの最大の違いは、前者には演出家が存在しないという点です。換言すれば、演出家の役割である「解釈」と「決定」 に関して も翻訳者が担っているということです。
つまり、少なくとも演劇との類比で文芸翻訳を語るのであれば、「訳者は役者」であるのみならず、実は「演出家」でもあるのです。
では、「読むための翻訳」において「演出」に相当するのはどんなところなのかというと、これがまた感覚の問題というか、実際には演出に近い部分と演技に近い部分がグラデーションを成してつながっていてはっきりと分類するのはかなり難しいというのが正直なところ。威勢よくテーゼをぶち上げたくせして面目ない。ううう。
強いて例を挙げれば、地の文を「です、ます」にするのか、「だ、である」で訳すのかという点などは、それ一つで作品を貫く印象ががらりと変わるという意味で演技(=主に役者の仕事)というよりは演出の域に近いような気がします。
また、手前みそで恐縮ですが、2019年1月に上梓(じょうし)した拙訳書『隣人ヒトラー』(岩波書店 刊)では、物語冒頭の1929年当時に5歳だった少年が1939年に14歳で亡命するまでの成長過程をより鮮明に描きたいと考え、時間の経過に合わせて主人公の用いる終助詞や語彙のレベルを徐々に上げてゆくだけでなく、漢字仮名表記のバランスも、幼年期は平仮名を多くして歳を重ねるごとに漢字を増やすよう塩梅(あんばい)しました。
ノンフィクション作品であったこと、終始一貫して主人公の視点から一人称で語り下ろされる文体であったことなどに鑑みての 判断 でしたが、このように作品全体の構成を左右する仕掛け に関して はまさに「演出」と呼んで差し支えないと思います。
翻って、個々の登場人物の台詞を訳しているときは「役者」寄りの感性が働いている気がします。
実際の役者と違い、5人なら5人、10人なら10人のキャラクターをすべて一人で訳し分けなければならないので、いわゆる「キャラかぶり」を避けるために演出的な采配をしている面もありますが、少なくとも私の場合、会話部分はノリノリで何度も音読しながら微調整を重ね、各人物の個性を活写できるよう努めます。
近頃は窓を開けて仕事をしているので、ご近所の方はさぞ不気味に思っていらっしゃることでしょう。あ、それか気の毒がっているかも。いいんだ楽しいんだほっといてくれ。
編集者は演出家であり得るか?
ともあれそんなわけで、「訳者は役者で演出家」であり、翻訳とは「演出:オレ、主演:オレの一人芝居」というのが、演劇の世界でそれなりの時間を過ごしてきた私の実感にいちばん近いと言えそうです。
と、ここで締めてしまうと、「え、編集者の立場は?」という疑問の声が上がるような気がします。
確かに、訳し上がった原稿をいちばんに読んでくれるのは編集者ですし、その際は地の文、台詞、人物造形、改行や漢字仮名表記その他、幅広くチェックを入れた上で返送してもらい、翻訳者が再び 修正する 、という 工程 を繰り返すのが最も一般的な 作業 の進め方です。翻訳者の「提案」に応答する立場という意味で、演出家に近い役割をイメージする人がいるのも無理はないでしょう。
ただ、演出家と違って編集者は最終的な 判断 をするわけではありません *3 。もちろん、然(しか)るべく信を置いている編集者の言であれば訳者は心して傾聴しますし、訳文を磨くうえで有益なアドバイスは喜んでどんどん受け入れますが、最終的にどの表現を採用するかは翻訳者が決定します。原文を直(じか)に読んで解釈するのが翻訳者である以上、これは妥当な役割分担だと思います。
吾輩は翻訳家である。名前はもう有る。
最後に。
「演出だの仕掛けだのと言っているけれど、そういうのってぜんぶ原作者によって本文や行間に書き込まれているんじゃないの?」
「翻訳者は演出なんて考えず、自身を極力無色透明にして、原作の色に染まるべく努力すべきなのでは?」
「翻訳家が演出家気取りなんて自己 主張 強過ぎ」
といったご批判も、もしかしたらあるかもしれません。
こればかりは翻訳観をめぐる根源的な問いであり、千人いれば千通りの哲学があると思うので、軽々な応答ははばかられます。
が。
はっきり言って私個人は、自分を殺して原作に奉仕しようと思ったことはありません。
なぜなら、私自身が生き物で、ナマモノで、代替不可能な一回生をまとった特定個人である以上、私の身体を通過して訳出されたものには必ず私というフィルターで濾(こ)された痕跡が残るからです。
であるならば、その痕跡を積極的に残してゆけばこそ、ほかの誰でもない私という特定個人が翻訳する意義があるというものです。ひいては、ほかの人ではなく平野の翻訳で読みたい、と言ってくださる方も現れようというものです。
翻訳家の自己 主張 が強くて何が悪い!
むしろ 主張 してナンボじゃい!!
あーあ。
どうしよう。
すごく怒られそうなこと言っちゃった。
大人( ただし 概念としての)に嫌われそうなこと書いちゃったなあ。
せっかくここまでお行儀よく書いてきたのに。
まあいいか。
思えばお行儀の良いオレなんて、もとより「作・演出・主演:オレ」の一人芝居だもんな。
おあとがよろしいようで。
平野暁人さんの本「EJ新書」
人気連載「舞台芸術翻訳・通訳の世界」は、電子書籍のEJ新書『元劣等生が褒められ好きの通訳・翻訳家になって考えたこと』で読めます!書き下ろしの章「高い言語能力(日本語力)を成長過程でどう獲得したのか?」も必読です。
▼詳細・購入はこちら(各界の方々の推薦コメントあり)

- 作者:
![]() ▼ENGLISH JOURNAL ONLIN連載は本書刊行後も継続 ej.alc.co.jp *1 : https://www.yurindo.co.jp/yurin/17766
▼ENGLISH JOURNAL ONLIN連載は本書刊行後も継続 ej.alc.co.jp *1 : https://www.yurindo.co.jp/yurin/17766*2 :出版社や取り次ぎ、書店といった「流通」に関する話はここではおきます。
*3 :ここでは、地味で質素な文芸翻訳の世界を念頭に置いています。大手商業誌や人気漫画誌におけるベテラン編集者と駆け出し作家の関係などは、また違うかもしれません。
![]()
平野暁人(ひらの あきひと) 翻訳家(日仏伊)。戯曲から精神分析、ノンフィクションまで幅広く手掛けるほか、舞台芸術専門の通訳者としても国内外の劇場に拠点を持ち活躍。主な訳書に『 隣人ヒトラー 』(岩波書店)、『 「ひとりではいられない」症候群 』(講談社)など。
Twitter: @aki_traducteurboocoで読める!アルクの新刊、続々登場
語学アプリ「booco」なら、アルクのベストセラー書籍200タイトル以上が、学習し放題!
「キクタン」などアルクの人気書籍800冊以上が音声対応。「読む」に対応した書籍では、本文と音声をスマホで手軽に利用できるほか、一部の書籍では、学習定着をサポートするクイズ機能で日々の復習や力試しも可能です。さらに、Plusプランに加入すれば200冊以上の書籍が学習し放題に!
boocoの「読む」機能では、次のような使い方ができます。
① 学習したいページを見ながら音声を再生できる
② 文字サイズや画面の明るさを調整できる
③ 書籍内検索ができる
※ これらの機能には一部の書籍が対応しています。![]()
▼「booco」の無料ダウンロードはこちらから