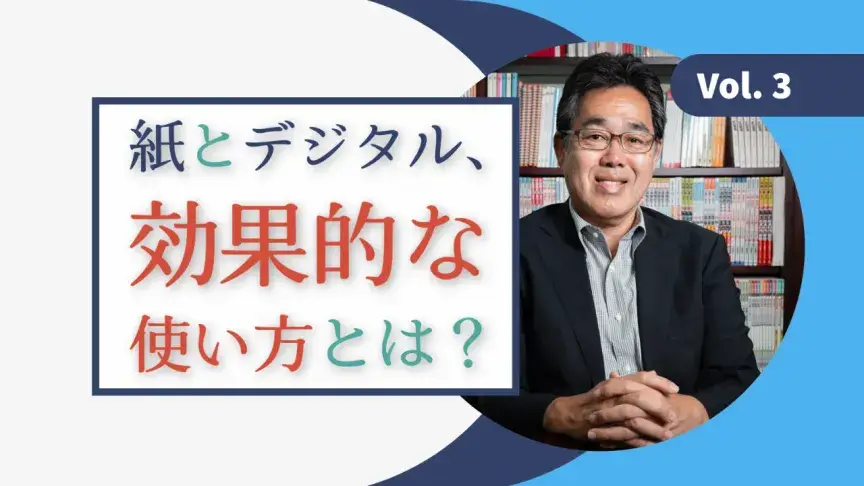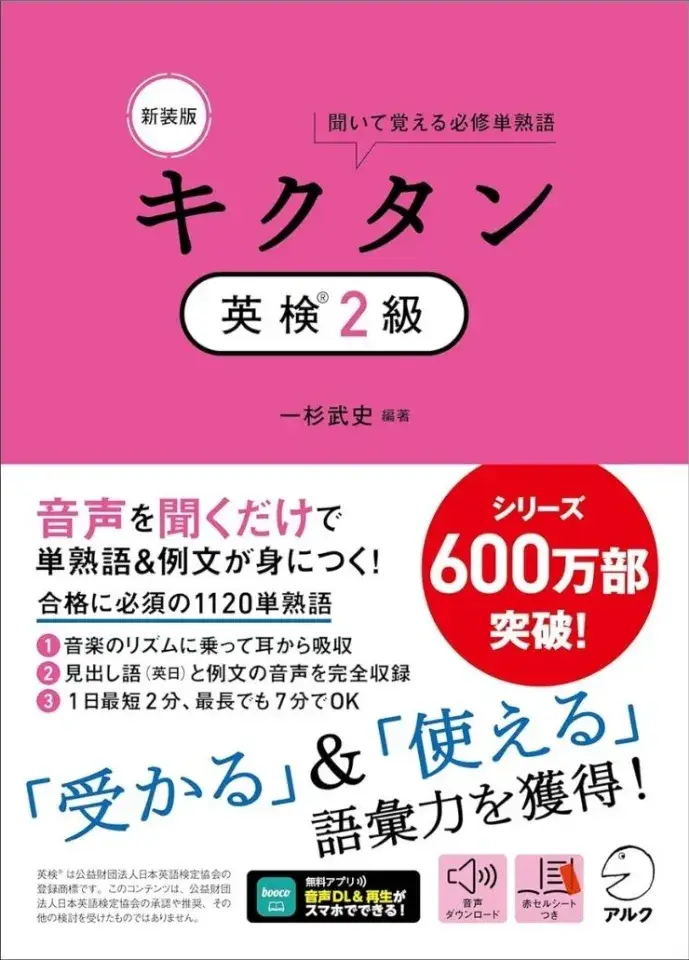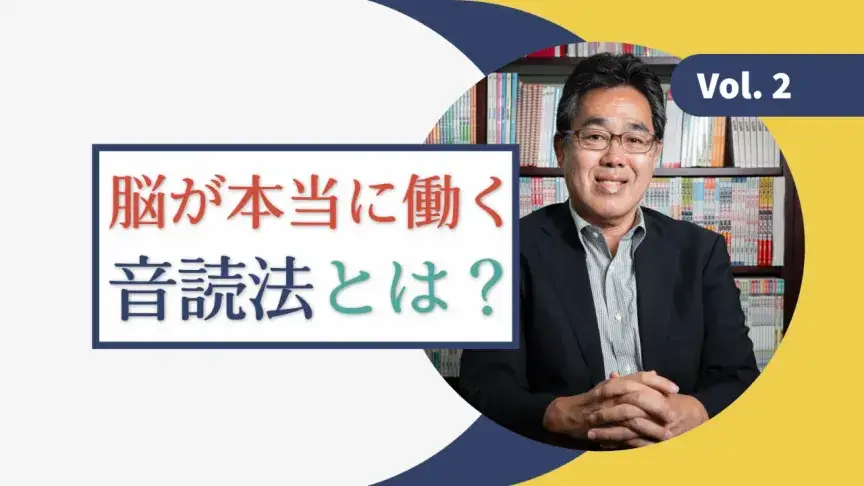
英語学習には「声に出す」活動が多くある。詩の暗唱や絵の説明、シャドーイングなどもその一例だ。だが、音読とこれらの活動では、脳に与える影響は異なるのだろうか?前回に引き続き、東北大学加齢医学研究所の川島隆太教授に、音読と類似する活動の違い、そしてそれぞれの脳への効果について話を聞いた。
第1回を読む
目次
川島先生のインタビュー動画
暗記したものを読むだけでは、脳はあまり働かない
音読に似た活動としてまず取り上げられたのは、詩や歌など、すでに暗記した内容を声に出す行為だ。川島先生はこう語る。
「いわゆる音読の場合は、目で見ながら声に出していく。これは脳がすごく働くのですけれども、覚えてしまったもの、これを声に出しても脳の働きは結構低くなってしまいます。ですから、脳トレ効果だけを求めるのであれば、やはり見ながら、できれば新しいコンテンツを読んでいただくのがいいと考えます」
文字情報の有無が、脳の働き方に大きく影響する。新しい内容を「読む」という行為こそが、脳への刺激になるのだ。
「ただ学習ということからいうと、記憶するまで読み込むことが大事ですから、そこは完全に(脳トレとは)分けて考えた方がいいですね」
絵を見て話すことも、脳は使う。ただし・・・
次に話題に挙がったのは、「絵を見て、それを言葉で説明する」という行為。これも一見、脳に良さそうだが、認知症予防との関係はどうなのだろうか?
「絵に描いてあるものを見て表現する、口に出すということ。これは脳を使うということはわかっています。かなり強く脳は活性化する。ただ、それがいわゆる認知症予防につながるかどうかということの研究はないです」
つまり、脳は確かに活性化するが、「予防につながるかどうか」はまだ証明されていない段階だという。
「多分、認知症予防につながるだろうと推測しますけれども、科学的にはまだまだ証明されていません」
シャドーイングは効果あり。ただし「スピード」が鍵
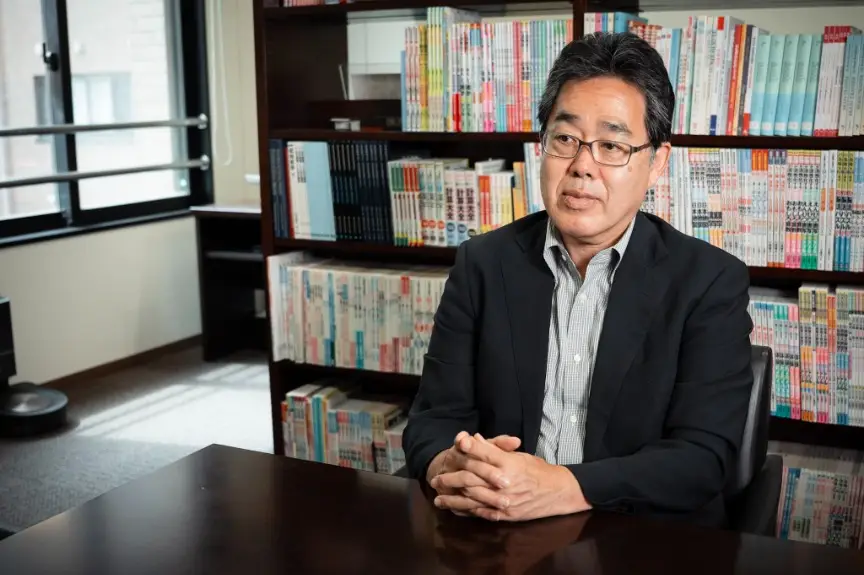
続いて話は、音声を聞き取って即座に真似する「シャドーイング」に移った。これは英語学習者にとってもなじみのあるトレーニング法だ。
「音として聞いたものを口に出す。英語のシャドーイングを行うと、前頭前野を含めて脳が動くことが新しい研究で明らかになっています」
最近の研究では、聴覚を通じて入ってきた情報を処理し、発話するプロセスが脳トレとして有効であることがわかっている。
「いわゆる聴覚で入った情報を処理して答えてもらうということによって、脳トレ効果ということもわかっています」
とはいえ、ここでもポイントになるのは「速さ」だ。
「先ほどの音読の場合とも一緒なんですけれども、できるだけ早くということが脳トレ効果を高めるコツですので、通常の学習とは違って、シャドーイングで脳トレ効果を強めようと思ったときには、早くしゃべるということを意識するのがポイントになります」
音読とシャドーイング、脳がより働くのは?
ここで素朴な疑問が投げかけられた。「音読とシャドーイング、どちらの方が脳は活性化するのか?」川島先生の答えは明快だった。
「脳活動の量というか、脳活動パターンからいうと、音読をした場合とシャドーイングをした場合、これは明らかに音読をした場合の方が脳はたくさん働きます」
その理由は、人間が「視覚優位」な生き物だからだという。
「我々人間は実は視覚の情報をたくさん使うように脳ができています。そのため、視覚野も非常に大きいですし、大脳の中でも視覚処理の領域では非常に多くの領域があります。それに比べて聴覚の領域というのは、我々人間の場合はどちらかというと余り進化していませんでした。今、私たちは視覚優位な生き物なので、やはり音読の方が脳はよく働きます」
「似ているようで違う」音読以外のトレーニング
暗唱、描写、シャドーイング―、どれも声に出すという共通点はあるものの、脳の使われ方には明確な違いがある。そして、認知症予防との関連については、音読の方が研究は進んでいるという現状も浮き彫りになった。
次回は、こうしたトレーニングを支える環境として注目される「デジタル教材」について、川島先生の見解を伺う。