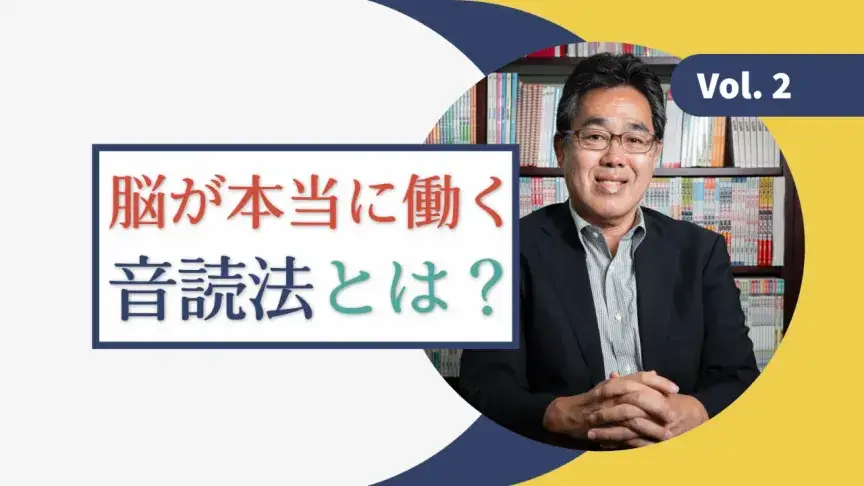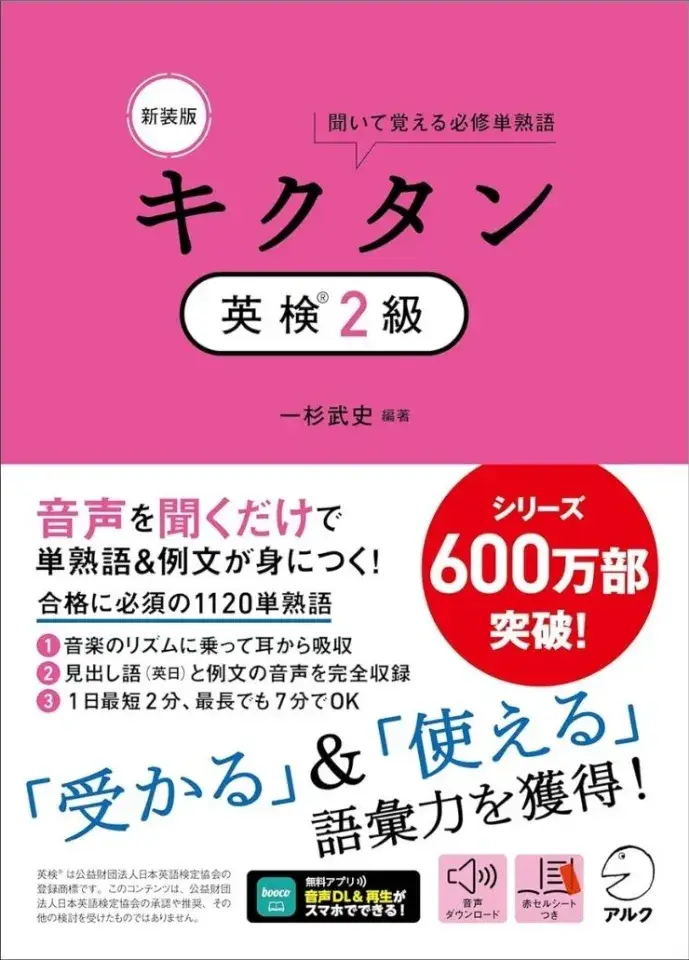英語の音読が記憶の定着や認知症予防に効果がある――そう聞くと、誰もが一度は試してみたくなるはずだ。だが、なぜ音読がそんなに良いのか、どんな方法が最も効果的なのか、そして英語で行うことに特別な意味があるのか。こうした疑問に答えてくれたのは、脳科学と脳トレ、学習療法の第一人者である東北大学加齢医学研究所の川島隆太教授。今回は、英語音読の科学的な効果とその活用法について、じっくりと話を伺った。
目次
川島先生のインタビュー動画
目で見て、声に出して、耳で聞く
まず、音読はどのような仕組みで学習に役立つのか。川島先生は、学習目的の音読には「意味を理解しながら声に出すこと」が大切だと語る。
「私たちの学んだことが脳に定着する、要は記憶するためには、たくさんの感覚情報をいっぺんに使った方がいいということがわかっています。見るだけですと視覚の情報しか使わない。でも、見て、それを声に出して読むということをすると、発声する運動の感覚、それから自分の声を耳で聞く、聴覚、これも加わります。それによって学習内容は定着しやすい。これはもう古くからわかっています」
文字を目で追い、声に出し、自分の声を耳で聞く――このようにして複数の感覚を同時に働かせることが、記憶の強化につながるという。
スピードが脳を鍛える鍵
一方、同じ音読でも「脳トレ」を目的にするなら、やり方が少し違ってくるという。
「特に脳を鍛えたいという場合には、速く読むということがとても大事です。脳を鍛える一つのコツは、できるだけ早く作業をするということ。これが脳を鍛える大原則の1つ目になります」
加齢によって処理速度が低下していく脳にとって、「速さ」は刺激となる。
「頭の中にコンピューターが入っていると思ってください。良いコンピューターというのは計算速度が速いのです。脳のコンピューターも歳をとると計算速度が遅くなっていってしまう。だから、行動も思考も遅くなるのですけれども、それをなるべく早く読むことによって、トレーニング効果をあらわして、脳の計算速度が上がります。これが直接脳トレ効果を導き出します」
日本語も英語も、音読の仕組みは同じ
では、英語の音読と日本語の音読では、脳の使われ方に違いはあるのだろうか?
「母語であろうと外国語であろうと、日本語であろうと英語であろうと、音読をすることによっての学習効果、それから音読を早く行うことによっての脳のトレーニング効果、これは同じです。ですから、そういう意味では英語が特別なわけではありません。ただ、英語であったとしても、きちっと声に出すことによって学習効果は高まり、早く読むことによって脳トレ効果があらわれます」
外国語を使うと、脳はより広く働く
とはいえ、外国語ならではのメリットもある。英語の方が脳を広く使うという科学的な根拠があるのだ。
「実際に脳の使い方を考えると、母語には日本語を使っているときよりも、外国語を使っているときの方がより広く脳を使うということがわかっています。ですから、そこから考えると、外国語を話す方(音読する方)が母語を音読するよりも効果が高いだろうというふうには考えられますが、これは(音読自体に)すごく効果がある中で、(英語の方が)外国語の方がさらに少し効果が高いというイメージを持っていただければいいと思います」
毎日じゃなくてもOK。「ちょっとでもいいから続ける」

では、どれくらいの時間、どれくらいの頻度で音読をすれば効果が出るのか。高齢者にとっては特に気になるポイントだ。
「これ実はちょっとでもやっていただければ効果があります。ただ、全体としての効果は最初何分間くらいで行ったか、それをどれぐらいの頻度で行ったかということの掛け算で、全体の効果が決まります」
「例えば1日の間で30分、音読したとしましょう。これを毎日繰り返していただければ早いうちに効果が出ますし、かなり忙しい方でも30秒だけ音読をする。でも、これでも1カ月ぐらい続けていただければ、やはり効果は出ます」
「実際、最先端の研究では、たった一度でもトレーニングをすると脳の機能がよくなるということがわかっています。そこから時間がたつとゆっくり下がっていくので、下がりきる前に次のトレーニングをする、下がりきる前に次のトレーニングをするというふうにすると、ゆっくりと階段を上るように脳の機能がよくなるというイメージを持ってください」
音読の頻度は「週3回以上」
忙しい現代人にとって、継続は大きな課題だ。週に何回行えば良いのかについても、川島先生は明快に語る。
「これまで脳のトレーニングの頻度ということでは、これまでの研究からは週に2回だと維持するのがやっとです。週に3回以上だとトレーニング効果が出ると考えています」
ただし、頻度や効果ばかりに気を取られてしまうと、本来の意味を見失ってしまうという。
「履き違えてはいけないのは、トレーニングが目的になってしまっては人生つまらないと思っています。要はトレーニングした結果として、よりよい自分の能力を獲得していって人生を楽しむということが目的ですから、トレーニング自体が目的化しないということは常に認識する必要があります」
第1回では音読の効果、やり方、頻度についてお聞きすることができた。次回は、「音読と似た活動でも認知機能の改善効果が得られるのか」について、川島先生に伺う。